対韓直接投資は半導体、IT分野に集中
最近の日韓経済関係を振り返る(後編)
2023年5月30日
「最近の日韓経済関係を振り返る」後編は、日本の対韓直接投資についてみることとする。前編は「韓国向け消費財輸出は回復へ」参照。
はじめに、日本の対韓直接投資の近年の動きをみる前に、長期的な趨勢について振り返ってみよう。
日本の対韓直接投資には、過去5回のピークがあった。1回目は1973年前後で、日本の人件費上昇と労働力不足を受けた労働集約型製造企業の韓国進出が相次いだ。2回目は1980年代後半で、1985年の「プラザ合意」後の円高を契機とした製造企業の韓国進出や、1988年開催のソウル・オリンピック需要獲得のためのホテル業の韓国進出が目立った。3回目は1990年代末で、アジア通貨危機による合弁パートナーの韓国企業救済を目的としたパートナー企業の持ち分取得が集中した。4回目は2000年代半ばで、液晶ディスプレイ関連を中心に韓国企業向け製造・販売拠点の構築が相次いだ。最後の5回目は2010年代前半で、半導体、有機ELディスプレイ、車載電池など幅広い分野の韓国企業向け製造・販売拠点を韓国に構築する動きがみられた。
日本の対韓直接投資は、5回目のブームの2012年に過去最高額を記録した後、減少に転じ、近年は盛り上がりに欠いた状況が続いている。
以下では、2019年以降を中心に、韓国の産業通商資源部の対内直接投資統計と日本企業のプレスリリースなどを基に、日本の対韓直接投資の動きを追っていきたい。
実質的には統計データ以上に不振だった日本の対韓直接投資
2010年以降の日本の対韓直接投資(実行ベース、以下同様)の推移は図のとおりだ。2012年に過去最高の38億4,847万ドルを記録して以降、2016年まで毎年減少が続いた。2017~19年は10億ドル前後で推移したが、2020年は、2003年(4億6,531万ドル)以降で最低の5億9,861万ドルを記録、対韓直接投資は一段と冷え込んだ。その後、2021年からは回復し、2022年は11億2,337万ドルと、3年ぶりに10億ドルを超過した。
なお、2012年に35.8%を記録した韓国の対内直接投資額全体に占める日本からの直接投資額の割合も低下し、2015年以降は1桁で推移している。韓国の対内直接投資での日本のプレゼンスもそれだけ低下したわけだ。
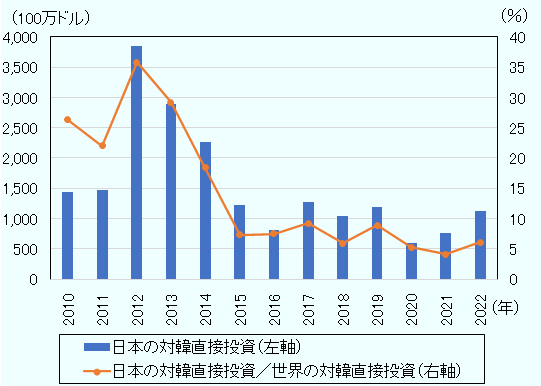
出所:産業通商資源部「外国人投資統計」データベースから作成
ここで留意すべき点は、2019年から2020年の日本の対韓直接投資が実質的には、統計データ以上に低調だったとみるべきということだ。金融・保険で、2019年に4億823万ドル、2020年に1億4,343万ドルというイレギュラー、かつ、大型の投資がそれぞれ1件あり、それらが対韓直接投資を大幅に引き上げたからだ。日本企業側のプレスリリースでの発表がないため、後掲の別表1には記載していない。しかし、韓国のロッテキャピタルの事業報告書をみると、これらがいずれも日韓ロッテグループ企業間での株主異動に起因したものであることが分かる(注1)。仮に、これらのイレギュラーな大型投資案件がなかったと仮定すると、日本の対韓直接投資は、2019年は7億8,342万ドルと2009年以来の8億ドル割れ、2020年は1998年(4億3,152万ドル)以来最低の4億5,518万ドルにとどまっていたこととなり、その不振ぶりがより鮮明になっていただろう。
対韓直接投資が実質的に不振だった理由は複合的
2019年から2020年にかけて日本の対韓直接投資が実質的に不振だったのは、以下の4つの要因が複合的に作用したためといえよう。
第1に、BtoB(法人向けビジネス)、BtoC(消費者向けビジネス)とも、日韓関係の冷え込みが影響した可能性がある。BtoBをめぐっては、韓国政府が2019年8月に発表した「対外依存型産業構造脱皮のための素材・部品・装備(注2)競争力強化対策-素材・部品・装備供給安定および自立化対策-」(以下「素材・部品・装備競争力強化対策」)が「脱日本」を目指したものだっただけに、日本企業としては韓国企業向け販売強化のための対韓直接投資に踏み出しにくかった可能性がある(ただし、対韓輸出を現地生産に代替する機会との考えに立てば、対韓直接投資不振の原因とはいえない)。BtoC 関連では、2019年夏以降に活発化した「No Japan」運動が展開する中では、日本企業は韓国進出を当然、躊躇(ちゅうちょ)したであろう。
第2に、2020年以降、新型コロナウイルス感染症拡大が影響したことが考えられる。特に、コロナ禍により国境を越えた人の流れが制限されたため、対韓投資の意思決定に係わる企業関係者が訪韓できず、対韓直接投資の決断ができなかったことが考えられよう。
第3に、特に製造業の場合、韓国企業の設備投資が盛り上がりを欠いたことが影響を及ぼした可能性がある。ちなみに、実質設備投資(需要項目別GDPベース)、実質機械受注額(民間、船舶を除く)のいずれも、2019年は前年に比べて減少し、2020年は前年比プラスに転換したものの、2018年の水準を回復する程度にとどまった。
第4に、そもそも直接投資は当該年の大型の直接投資案件の有無により大きく変動する。両年とも前述の日韓ロッテグループ企業間での株主異動を除くと、大型の投資案件がなかった。仮に、ある程度の規模の投資案件が1件でもあれば、状況が異なっていた可能性もある。
その後、日本の対韓直接投資は2021年、2022年と回復に向かった。特に、2022年は前述のとおり、3年ぶりに10億ドルを超過した。対韓直接投資の回復は、前述の4つの要因の一部が解消に向かったためと考えられる。特に、コロナ禍が落ち着いてきたことや、日韓関係が改善の兆しを見せてきたことなどが対韓直接投資の回復に寄与したものと考えられよう。
さらに、2019年以降の直接投資実績について、業種別にみよう(表参照)。製造業は2019年以降、毎年5億ドルを下回っている。特に、2020年は1億5,700万ドルと、1997年(1億2,231万ドル)以降で最も少なかった。2022年は4億4,955万ドルに回復したものの、2018年(4億6,827万ドル)の水準には至っておらず、回復の勢いは鈍めだ。製造業の内訳をみると、2022年を除き、化学工業が最も多く、製造業の対韓直接投資の主役になっている。他方、サービス業をみると、2019年、2020年は前述のように金融・保険が突出して多かった半面、それ以外の業種は全般に低調だった。2021年、2022年は卸売・小売業、情報通信などが比較的多かった。
| 業種 | 2019年 | 2020年 | 2021年 | 2022年 |
|---|---|---|---|---|
| 農・畜・水産・鉱業 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 製造業 | 468 | 157 | 329 | 450 |
 食品 食品
|
0 | 1 | 4 | 2 |
 繊維・織物・衣類 繊維・織物・衣類
|
6 | 0 | 0 | 0 |
 製紙・木材 製紙・木材
|
1 | 0 | 0 | 0 |
 化学工業 化学工業
|
224 | 73 | 104 | 128 |
 医薬 医薬
|
0 | 10 | 0 | 0 |
 非金属鉱物製品 非金属鉱物製品
|
3 | 8 | 0 | 0 |
 金属・金属加工製品 金属・金属加工製品
|
26 | 4 | 52 | 17 |
 機械装備・医療精密 機械装備・医療精密
|
102 | 2 | 86 | 137 |
 電気・電子 電気・電子
|
80 | 1 | 56 | 50 |
 輸送用機械 輸送用機械
|
8 | 50 | 21 | 112 |
 その他製造業 その他製造業
|
18 | 9 | 4 | 4 |
| サービス業 | 708 | 431 | 427 | 672 |
 卸売・小売業 卸売・小売業
|
111 | 40 | 155 | 111 |
 宿泊・飲食業 宿泊・飲食業
|
16 | 24 | 51 | 45 |
 運送・倉庫 運送・倉庫
|
4 | 1 | 0 | 0 |
 情報通信 情報通信
|
77 | 93 | 119 | 312 |
 金融・保険 金融・保険
|
492 | 261 | 85 | 171 |
 不動産 不動産
|
2 | 1 | 9 | 2 |
 事業支援・賃貸 事業支援・賃貸
|
3 | 3 | 0 | 2 |
 研究開発・専門・科学技術 研究開発・専門・科学技術
|
3 | 9 | 1 | 28 |
 余暇・スポーツ・娯楽 余暇・スポーツ・娯楽
|
0 | 0 | 0 | 0 |
 公共・その他サービス 公共・その他サービス
|
1 | 0 | 6 | 0 |
| 電気ガス・水道・環境浄化・建設 | 15 | 10 | 8 | 2 |
| 合計 | 1,192 | 599 | 764 | 1,123 |
| 製造業比率(製造業/合計) | 39.3 | 26.2 | 43.0 | 40.0 |
注:分類は韓国標準産業分類(KSIC)大分類ベース(製造業・サービス業は中分類ベース)。
出所:産業通商資源部「外国人投資統計」データベースから作成
製造業の対韓直接投資、半導体関連の化学企業に集中
次いで、2019年以降の日本企業の対韓投資事例について、(1)投資元の日本企業が製造業の場合、(2)投資元の日本企業が非製造業の場合の2つに分けてみてみよう(ちなみに、2010年代の日本企業の韓国進出事例については、ジェトロ・アジア経済研究所「日本の対韓直接投資の推移と現状-2010年代の韓国進出事例と在韓日系企業の第三国進出を中心に-![]() 」参照)。なお、本稿で取り上げる事例は、韓国国内での調達資金・内部留保を原資とした投資や、フランチャイズ展開といった実行ベースの直接投資統計に計上されない事例も幅広く含んでいる。
」参照)。なお、本稿で取り上げる事例は、韓国国内での調達資金・内部留保を原資とした投資や、フランチャイズ展開といった実行ベースの直接投資統計に計上されない事例も幅広く含んでいる。
まず、日本の製造業企業の対韓投資事例を総括すると、業種別には化学企業の事例が多く、販売先は韓国半導体企業が多いのが特徴だ(別表1参照)。
日本の化学企業の投資事例が多いのは、前述の対内直接投資統計の傾向と一致する。主たる狙いは、半導体企業を中心に拡大する韓国企業向け需要を取り込むことだ。つまり、顧客の韓国企業の近くで関連部材を生産すべく、韓国で生産拠点を新増設する動きがみられたわけだ。ちなみに、各社のプレスリリースをみる限り、韓国政府の「素材・部品・装備競争力強化対策」への対応に言及した事例はみられなかった。
日本の化学企業のうち、サムスン電子、SKハイニックスといった韓国半導体企業向けの関連部材工場を新増設した日本企業として、2019年は日華化学、東ソー・クォーツ、2020年は太陽ホールディングス、昭和電工マテリアルズ、2021年は日産化学、住友化学、トクヤマ、2022年はADEKA(同社は2023年にも生産設備増強計画を発表)、昭和電工、富士フイルムといった事例があった(企業名は発表当時)。半導体企業以外向けには、ダブル・スコープが韓国の車載電池企業向けのセパレータの生産を拡大している。世界の電気自動車(EV)市場の拡大を受け、韓国の車載電池企業が生産規模を拡大していることに対応したものだ。
2023年に入ると、ADEKAや出光興産が相次いで、韓国で半導体関連などの研究開発(R&D)拠点を新増設することを発表した。これらは、サムスン電子、SKハイニックスといった顧客企業の近くでR&D拠点を整備し、コミュニケーションを密にすることで、顧客企業のニーズ把握や共同開発を行うことを狙ったものだ。
化学企業以外でも、浜松ホトニクス(2020年)、堀場エステック(2021年)のように、韓国半導体企業向けの生産や販売体制を強化する事例がみられるなど、韓国の半導体企業の需要を取り込む動きが目に付いた。
さらに、韓国企業を買収した事例も散見された。多くは、韓国企業の高い技術力を評価し、自社の事業ポートフォリオを充実させる狙いだった。また、韓国市場での顧客基盤を獲得するための買収事例もみられた。
非製造業の対韓直接投資はゲーム・IT分野に集中
次いで、日本の非製造業の対韓投資事例を総括すると、ゲーム・IT分野に集中しているのが特徴だ。投資形態は、(1)支社・現地法人設立や既存拠点の拡充、(2)技術力の高い韓国企業への出資・韓国企業買収の双方の形態がみられた。前者は韓国市場獲得が主な狙いだ。半面、後者は韓国企業の保有技術を日本市場に投入する事例が散見された(別表2参照)。
ゲーム・IT分野以外の投資事例は、さまざまな分野に分散している。
さらに、投資会社の色彩の強い投資や、投資ファンドによる韓国のスタートアップ・ベンチャー企業などへの投資もみられた。この分野の投資は、日本企業のプレスリリースには掲載されていないものの、韓国メディアで報じられている案件も多多いため、実態としては別表2よりもかなり多いものと考えられる。こうした投資が、前述の表:業種別対韓直接投資の動向(実行ベース、2019~22年)の「情報通信」の日本からの直接投資を底上げしている可能性もあろう。
なお、BtoCの事例はあまりみられなかった。かつて、2000年代前半に、衣類・雑貨などのチェーンストア分野の有力企業が相次いで韓国に進出し、また、2010年代前半には、多くの外食チェーンが韓国に進出した。さらに、2010年代半ばには、ホテル・リゾート分野での進出が相次いだ。2019年以降、こうした分野の新たな韓国進出はほとんどみられなかった。複数の理由が考えられる。まず、韓国市場への進出が一巡し、新たに参入を検討している企業が少なかったことが考えられる。さらに、日韓関係の冷え込みやコロナ禍が拍車を掛けたものと考えられる。
BtoBの対韓直接投資は韓国企業の国内生産次第か
今後の日本企業の対韓直接投資について、どうみるべきだろうか。
BtoBについては、特に製造業の場合、日本企業の対韓直接投資は韓国企業向け販売を狙ったR&D・生産・販売拠点の構築の意味合いが強いため、今後の対韓直接投資の動向は、韓国企業が国内生産をどれだけ増やすかに掛かっているといえる。その意味で、日本企業にとっての最大の顧客である韓国半導体企業が国内で生産規模の拡大に動いていることは注目されよう。ちなみに、SKハイニックスは2022年9月、今後5年間に15兆ウォン(約1兆5,000億円、1ウォン=0.1円)を投じ、韓国中部の忠清北道清州市に半導体の新工場を建設すると発表した。2025年初めの完工を目指すとしている。サムスン電子は2023年3月、今後20年間に300兆ウォンを投じ、ソウル近郊の京畿道龍仁市に先端ファウンドリー(半導体受託生産)工場5棟を建設すると発表した。2029年ごろの稼働を目指すとしている。韓国政府も国内の半導体産業の生産基盤拡充に積極的だ。政府は2023年3月、京畿道龍仁市に世界最大規模のシステム半導体クラスターを構築する計画を発表した。
他方、BtoCについては、見通しはなかなか難しそうだ。別表2でみる限り、最近のBtoCの韓国進出事例は、皆無ではないものの、限定的だった。今後については、競争の厳しい韓国市場で差別化した商品・サービスを提供し続けられる日本企業がどれだけあるか、「No Japan」運動の再燃リスクを日本企業がどう判断するかといった点がポイントとなろう。
全社のポートフォリオ見直しにより韓国から撤退した事例も散見
韓国・国税庁「国税統計年報」によると、かつて増加傾向にあった在韓日系企業(現地法人)の数は2013年末の2,297社をピークに漸減傾向に転じている。2019年以降は、減少の速度が速まってはいないものの、漸減傾向が続いており、最新値の2021年末には1,855社になった。
在韓日系企業数が減少しているということは、新規に進出した企業以上に撤退した企業が多いことを意味する。ただし、撤退企業の多くは中小企業で、その中には、事業活動がほとんどないまま年月が経過し、遅れて現地法人の清算手続きを行うケースもあるもようだ。そうしたこともあり、韓国から撤退した日系企業の事例の把握は容易ではない。
このような中、2019年以降に韓国事業の撤退をプレスリリースで発表した主な日本企業の事例をまとめた(別表3参照)。
BtoC関連では、日韓関係の冷え込みやコロナ禍などによる韓国事業の停滞を受けて撤退を決定した事例が散見される。また、BtoC、BtoBを問わず、当該企業の個別の事情による韓国事業の業績不振により、韓国事業から撤退した事例もみられる。
半面、韓国事業自体の問題に起因した撤退というよりも、日本本社の経営戦略の見直しに伴って韓国からの撤退を決定した企業も少なくない。別表3で「事業ポートフォリオ」「選択と集中」「投資効率」「資本効率」といった用語が入っている事例がそれに該当する。つまり、本社が限られた経営資源のさらなる有効活用を目指し、全世界に展開する事業の見直しを行った結果、韓国事業が「非重点事業」に仕分けられ、韓国からの撤退を決定したというパターンだ。別表3でみる限り、これが韓国撤退の最も多い理由のようだ。
さらに、合弁会社における経営戦略に関して合弁パートナーとの意見の相違や、投資会社の資金回収による韓国からの撤退事例もみられた。
- 注1:
- 2019年は、韓国の公正取引法により、一般持ち株会社が金融・保険企業の株式を保有することが禁じられていることなどに対応し、韓国のロッテ持ち株などが保有していたロッテキャピタルの株式を日本のロッテファイナンシャルに売却したことによるもの。2020年は、韓国のホテルロッテなどが保有していたロッテキャピタルの株式を日本のロッテファイナンシャルに売却したことによるもの。
- 注2:
- 「装備」は、「製造装置」を意味する韓国語の漢字での表記。
最近の日韓経済関係を振り返る
- 韓国向け消費財輸出は回復へ
- 対韓直接投資は半導体、IT分野に集中

- 執筆者紹介
-
ジェトロ調査部中国北アジア課
百本 和弘(もももと かずひろ) - ジェトロ・ソウル事務所次長、海外調査部主査などを経て、2023年3月末に定年退職、4月から非常勤嘱託員として、韓国経済・通商政策・企業動向などをウォッチ。




 閉じる
閉じる






