2023年上半期も粘り強い米国経済、ソフトランディングへの期待高まる
2023年7月5日
筆者が年初に執筆した2023年1月10日付地域・分析レポート(以下、前回レポート)では、2023年の米国経済に対する悲観的な見方が強まっているほか、高インフレ・高金利の中で消費がどこまで持ちこたえられるかが景気動向を左右する、と述べた。2023年上半期を終え、成長ペースは鈍化するも、消費はいまだに堅調さを保ち、米国経済を下支えしている。長短金利の逆転が常態化・長期化しているため、今後の景気後退を見込む声が引き続きある一方、底堅い消費を理由にマイナス成長は避けられるというソフトランディングへの期待も高まっている。本稿では、米国経済の現況と今後の展望をあらためて概観する。なお、使用数値は6月23日の執筆時点の公表値に基づく。
成長ペース鈍化も、粘り強さを見せる
2022年上半期の米国経済は、高インフレや金融引き締めの影響などにより、2四半期連続のマイナス成長を記録した(図1参照)。景気後退入りが懸念されたが、同年下半期は2四半期連続で3%程度のプラス成長となり、上半期のマイナス分を取り戻した。2023年第1四半期(1~3月期)は前期比半減となる1.3%のプラス成長で、前期に急増した在庫投資が反動減で最大の押し下げ要因となったが、GDPの約7割を占める消費が最大の押し上げ要因となり、見た目以上に中身は力強い成長がみられた。
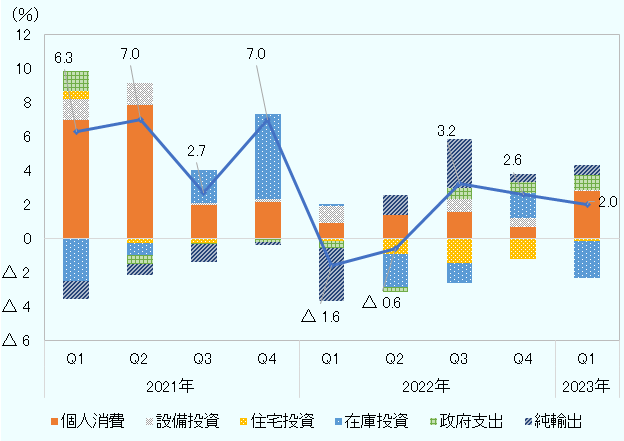
出所:米商務省
新型コロナ禍からの回復という中長期でみても、経済に粘り強さがある。図2のとおり、当初は政府支出が増加した。その後、巣ごもり需要などを背景に民間投資が増え、高インフレと高金利が顕在化し始めた2022年以降は、堅調な消費が成長を牽引している。なお、純輸出(輸出-輸入)は、輸出以上に輸入が回復しているため、大きく落ち込んでいるが、堅調な国内消費の裏返しであるともいえるため、必ずしもネガティブな動向ではない。
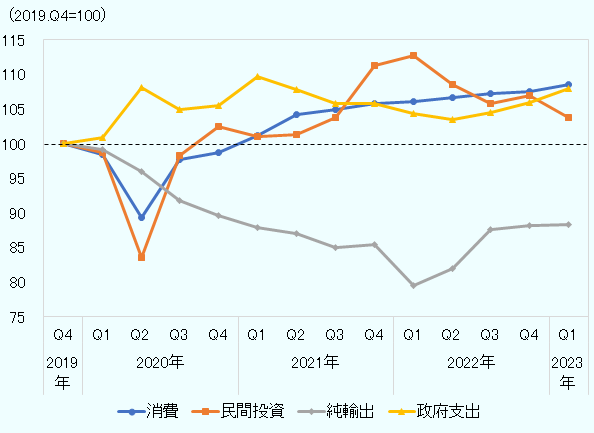
出所:米商務省
実質所得は横ばいだが、余剰貯蓄が消費の支えに
堅調な消費の源泉はどこにあるのか。フローの可処分所得(注1、図3参照)をみると、新型コロナ禍以降、名目所得は賃金の上昇により大きく伸びている。しかし、物価が賃金以上に上昇したため、実質所得は目減り、ないしはほぼ横ばいとなっており、購買力にプラスの影響はほとんどない。一方、前回レポートでも紹介したとおり、新型コロナ禍での行動制限による消費の抑制や政府からの現金給付により、余剰貯蓄は積み上がった。これが実質所得の停滞を補い、依然として堅調な消費を支えている構造は変わっていない。ただし、余剰貯蓄は残り約5,000億ドル(図4の緑色部分と赤色部分の差)で、ピーク時の4分の1まで減少しており、2023年中に尽きることが懸念されている。
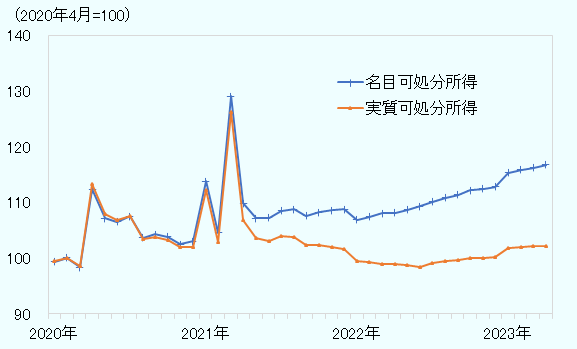
出所:セントルイス連邦準備銀行
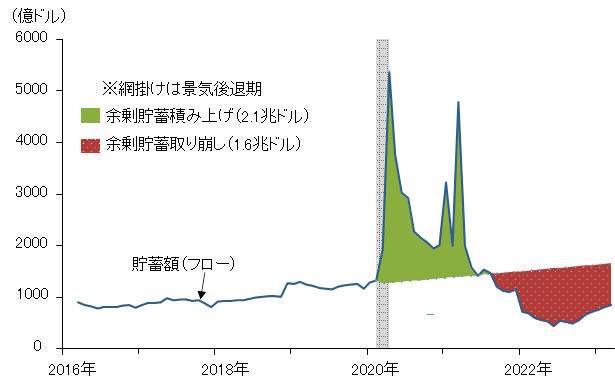
出所:米連邦準備制度理事会(FRB)
マークアップ率は急落、景況感は製造業で特に悪化
企業のインフレへの対応はどうか。マークアップ率(注2、図5参照)をみると、2021年は3.2%と2011年以降では最高を記録し、価格転嫁は順調だった。しかし、2022年はマイナス0.7%と、物価の鈍化以上に急落した。価格転嫁が難しくなっている現状にあるとみられ、企業の利益率は低下傾向にある。
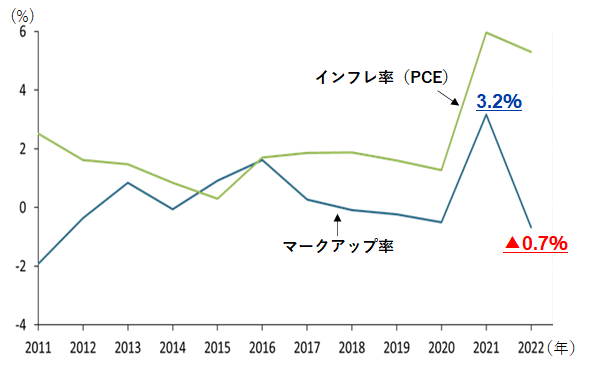
出所:カンザスシティ連邦準備銀行
先行きに関して、特に製造業の景況感指数(図6参照)は、2022年11月から一貫して、景況感縮小のサインである50を下回っている。サービス業はかろうじて50を上回り、景況感拡張を維持しているものの、トレンドとしては徐々に低下の兆しを見せている。前述した余剰貯蓄の縮小に伴い、消費意欲が減退する懸念と照らし合わせれば、今後の動向が不安視されている。概して、家計は堅調さを保っている一方、企業部門は息切れ感が目立ってきている現状にある。
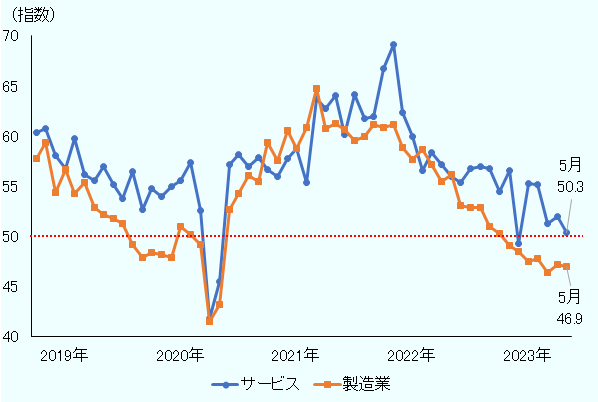
出所:全米供給管理協会
物価の高止まり続く、サービス価格の動向が今後を左右
2023年5月の消費者物価指数は4.0%(前年同月比、特記なき限り以下の数値は前年同月比)となり、1981年以来のピークである2022年6月に記録した9.1%から半分以下まで低下した。しかし、食料品とエネルギーを除いたコア指数は5.3%と、新型コロナ禍以降のピークである2022年9月の6.6%から低下しているが、鈍化の度合いは相対的に弱い(2023年6月14日付ビジネス短信参照)。ロシアのウクライナ侵攻の影響が緩和していくにつれて、食料品とエネルギーのインフレ率は、顕著に鈍化または低下した(図7参照)。一方、コア指数を構成する項目では、供給網の逼迫緩和の影響で、財が顕著に鈍化しているが、家賃など住居費や輸送サービスなどのサービス価格は鈍化の傾向を示すにいたっていない。ただし、急激な金融引き締めにより、住宅価格は鈍化している。このため、住居費は今夏ごろから鈍化する可能性がある。労働市場の逼迫により賃金の上昇圧力は引き続き強く、コスト転嫁というかたちで、サービス価格を中心に物価に上昇圧力がかかっている。サービス価格の先行きは、依然として不透明な状況だ。
食料品・エネルギー
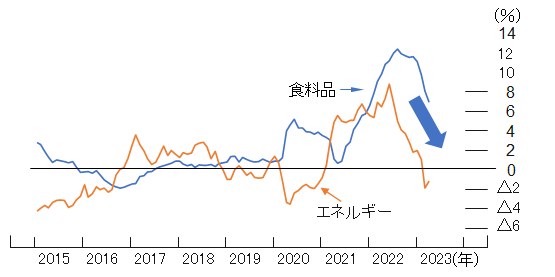
財・住居費・住居費を除いたサービス価格
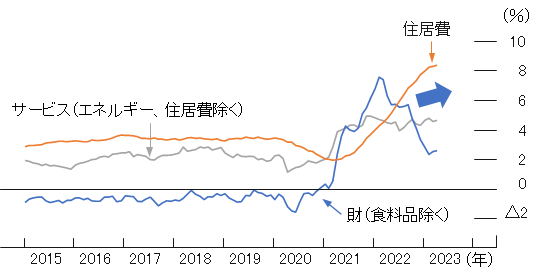
出所:米労働省、FRB
若年層の労働参加回復も、55歳以上は横ばい
前回レポートでは、55歳以上の労働参加率の回復が遅いことを指摘した。この状況は、2023年6月時点でも同じだ。図8のとおり、54歳未満の労働参加率は新型コロナ禍前をすでに超えているが、55歳以上は過去約2年間ほぼ横ばいだ。新型コロナ禍により、米国の資産価格は大きく上昇した。高齢層の方が家や株式などの資産を多く所有していることから、資産効果を若年層よりも享受していると考えられる。54歳以下と55歳以上で回復が分かれている理由は諸説あるが、これが、55歳以上の労働参加率が新型コロナ禍前の水準に戻らない一因と指摘されている。
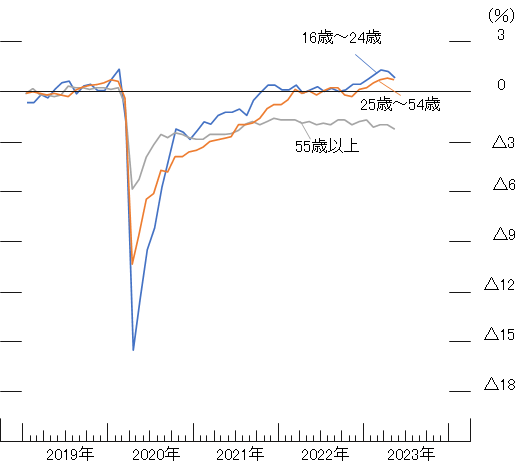
出所:FRB
出生率や人口増加率は低下傾向
2022年の合計特殊出生率は1.67で、人口維持に必要な水準の2.1(注3)を大きく下回っている。実際のところ、2.1を下回る状況は2007年以降一貫して続いている。米国の人口は、移民の流入数などが出生数を補うかたちで増加してきた。しかし、移民を含めた人口増加率も、新型コロナ禍の影響で2021年に建国以来で最低の前年比0.1%増となった。2022年は前年比0.4%増に上昇したが、低水準に変わりなく、生産年齢人口の増加は望みにくい状況にある(2023年6月2日付ビジネス短信参照)。55歳以上の労働参加率が回復しない状況も考慮すれば、労働の供給量は今後も低下する可能性がある。
なお、2023年4月の失業者1人当たりの求人数は1.79件で、前回レポート時点からほぼ変わっていない(図9参照)。労働市場の中でも、特に逼迫が顕著なサービス業では、賃金上昇率が6%程度で高止まりしている。前述したとおり、これが高インフレの大きな要因となっている。
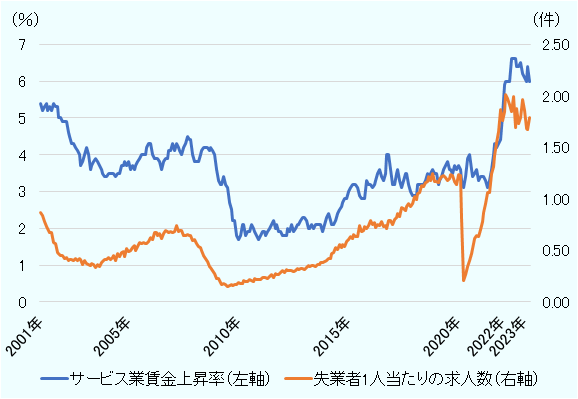
出所:セントルイス連邦準備銀行
FRBはさらなる金利引き上げを模索
米国連邦準備制度理事会(FRB)は2023年6月の連邦公開市場委員会(FOMC)で、政策金利(フェデラル・ファンドレート)の誘導目標を5.0~5.25%で据え置きいた。2022年3月から続く異例のペースの金融引き締めは一時停止された。しかし、併せて公表された今後の見通しでは、最終的な到達金利が5.6%と、前回のFOMCから0.5ポイント引き上げられた。すなわち、2023年内にあと2回の引き上げが示唆されている。また2024年に入っても、厳しい金融引き締めにもかかわらず、FRBのインフレ目標である2%は達成困難とみられる。政策金利は2024年末時点で4.6%、引き下げ幅は前年比1.0ポイント程度にとどまる見込みだ。
厳しい金融引き締めなどもあり、2023年と2024年の実質GDP成長率は1.0%との見通しが示されている。これは、定常状態の米国の成長率の半分にとどまる(2023年6月15日付ビジネス短信参照)。前述の労働市場の逼迫は、主に供給側の要因で生じている事象だ。金融政策は、基本的に労働供給に対し効果をもたらさない。例えば、金利を引き上げても、人々の労働意欲は刺激されない。他方、FRBは政策金利の引き上げを通じて、企業の投資コストを上昇させ、投資意欲を減退させることで、労働需要の低下や賃金に対する上昇圧力の緩和、高インフレの低下を図ろうとしている。
一方、金融引き締めによる景気の後退は、常に懸念されている。前回レポートでも紹介した長短金利の逆転現象は続いており、その期間は歴史的にみても長期化している。過去の事例をみると、景気後退の約1年前には、必ず長短金利の逆転現象が発生していた。こうしたことも景気後退懸念を高めている一因だ。また、長短金利の逆転により、銀行は利ざやを稼ぎづらくなっており、貸し出し態度は悪化している(図10参照)。シリコンバレー銀行に端を発した銀行セクターの信用不安は、ファースト・リパブリック銀行の破綻以降落ち着きを見せているが(2023年5月2日付ビジネス短信参照)、当局は今後、銀行に対する規制を強化する見込みとなっている。規制が強化されると、資産規模1,000億ドル~2,500億ドル程度の中堅・中小規模の銀行を中心に、財務状況の改善に向けて貸し出し態度をさらに悪化させ、個人や企業の信頼感が今後、低下する可能性がある。特に、中堅・中小規模の銀行による融資比率が高い商業不動産セクターへの影響が懸念されている。
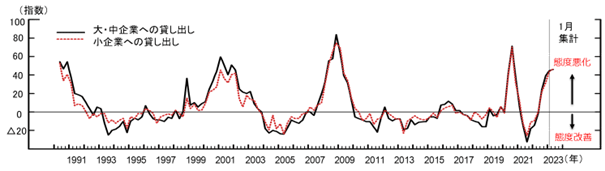
出所:FRB
まとめ
まとめると、要旨は次のとおり。
- 米国経済は鈍化傾向にあるが、いまだに大きな減速をみせてはいない。新型コロナ禍における余剰貯蓄を原資とした消費が下支えしている。他方、賃金以上のインフレにより、余剰貯蓄は徐々に減少しており、2023年中に尽きる可能性がある。消費の先行きは不透明であり、いつまで持ちこたえられるかが今後の鍵となる。
- インフレは減速しているが、サービス価格の減速は緩やか。サービス部門を中心に、労働の供給不足という構造的要因により、賃金は高止まりしている。また、賃金上昇分の価格転嫁がインフレを助長している。インフレ抑制の観点から、労働需給を緩和させ、賃金上昇率を抑えることが重要になる。
- 当局はインフレの抑制を優先し高金利を継続する見込みで、2023年は1%程度の経済成長率を企図している。市場では景気後退が濃厚という見通しが強いものの、堅調な消費により、ソフトランディングは可能という見方も根強い。
- 市場を混乱させた銀行セクターの信用不安は落ち着きをみせているが、当局は銀行に対する規制を強化する見込み。規制が強化されると、中堅・中小規模の銀行を中心に、財務状況の改善に向けて貸し出し態度を悪化させ、個人や企業の信頼感が低下する可能性がある。特に、中堅・中小規模の銀行による融資比率が高い商業不動産セクターへの影響が懸念される。
今後の景気に悲観的な見方が依然存在しているものの、前回レポートの執筆時に比べて、いまだ堅調さを保つ消費などを背景に、大幅なマイナス成長は避けられるのではないか、というソフトランディングへの期待や見込みが根強くなっている。インフレの抑制に向けて、ある程度の景気後退は許容されるべきと思う一方、2024年に大統領選挙がある中では、当局は大幅な景気後退を避けたいと考えているのが本音であろう。金融政策を中心に、インフレ抑制に向けた当局のかじ取りは、引き続き困難を極めそうだ。
- 注1:
- 税・保険料などを支払った後の所得。
- 注2:
- コストの上昇分を含む原価に対する利益の割合。
- 注3:
- 死者数は不変で、移民はゼロと仮定した場合の数値。

- 執筆者紹介
-
ジェトロ・ニューヨーク事務所
宮野 慶太(みやの けいた) - 2007年内閣府入府。GDP統計、経済財政に関する中長期試算の作成などに従事。中小企業庁や金融庁にも出向し、中小企業支援策や金融規制などの業務を担当。2020年10月からジェトロに出向し現職。




 閉じる
閉じる






