「スイーツとしてのわらび餅」で海外市場を開拓(日本)
原料生産から現地ニーズ対応まで、川崎大師・大谷堂の新たな挑戦
2025年10月6日
日本の菓子やスイーツは、味やフレーバーなどバラエティーに富む。キャラクターとのコラボレーションや、かわいらしいパッケージが魅力の商品も多い。日本独自の発展を遂げてきたと言える。他国にない独創性に評価が集まり、近年では海外市場でも人気が高まってきた。インバウンド観光客の増加に伴う認知度向上や、日本のアニメや漫画の世界的普及の影響もありそうだ。日本産菓子類の輸出が着実に増加しているのは、そのためだろう。 神奈川県の川崎大師にある大谷堂![]() は、国産本わらび粉などの原料や製法にこだわってわらび餅を製造する。代表取締役社長の大谷茂氏に、輸出状況や海外展開の取り組みなどについて聞いた(取材日:2025年8月14日)。
は、国産本わらび粉などの原料や製法にこだわってわらび餅を製造する。代表取締役社長の大谷茂氏に、輸出状況や海外展開の取り組みなどについて聞いた(取材日:2025年8月14日)。
菓子類輸出が増加、金額で香港、数量で米国が1位
全日本菓子協会(ANKA)「令和6年菓子データ」![]() (6.6MB)によると、2024年の日本の菓子の生産数量は198万4,654トン(前年比0.6%減)。生産額は2兆7,886億円(4.1%増)、小売販売額3兆8,785億円(5.3%増)だった。昨今は、製造コストなどの価格転嫁による商品価格の改定があり、消費者の節約志向が進んでいる。その影響に懸念がある一方で、新たな購買層として訪日外国人が増加する追い風もある。結果的に、生産・小売とも過去最高を記録したかたちだ。
(6.6MB)によると、2024年の日本の菓子の生産数量は198万4,654トン(前年比0.6%減)。生産額は2兆7,886億円(4.1%増)、小売販売額3兆8,785億円(5.3%増)だった。昨今は、製造コストなどの価格転嫁による商品価格の改定があり、消費者の節約志向が進んでいる。その影響に懸念がある一方で、新たな購買層として訪日外国人が増加する追い風もある。結果的に、生産・小売とも過去最高を記録したかたちだ。
菓子類全体の輸出を、2020年から2024年まで経年でまとめてみた(表、図参照/注)。輸出数量、金額ともに順調に増加し、2024年は過去最大の6万1,619トン、932億7,200万円だった。4年前の2020年(4万6,180トン、571億3,100万円)から輸出数量・金額ともに着実に増加していることがわかる。
2024年の実績を国・地域別にみると、金額ベースでは、最大の輸出先が(1)香港で187億7,600万円(前年比2.8%増)。(2)米国の180億7,100万円(28.2%増)、(3)台湾140億400万円(3.7%増)が続く。数量ベースでは、(1)米国(1万2,044トン)、(2)香港(1万1,579トン)、(3)台湾(9,467トン)の順になった。そのほか、韓国や、タイ、ベトナム、マレーシアなど東南アジアへの輸出が金額、数量ともに増加した。
主な輸出品目は、チョコレート菓子、キャンディー類、米菓(あられ、せんべい)など。米国や香港などでは、一目で日本産とわかるデザインや味などを背景にグミやソフトキャンディーの認知度が向上したことなどが要因だ(詳細は、ジェトロ「輸出品目別レポート 菓子」![]() (1.2MB)2025年7月)。
(1.2MB)2025年7月)。
なお、菓子は、農林水産省の輸出拡大実行戦略![]() (952KB)(2025年5月)の輸出重点品目に入っている。目指すのは、2030年までに輸出額を世界全体で2,050億円にすることだ(香港 243億円、米国 368億円、台湾 206億円など)。
(952KB)(2025年5月)の輸出重点品目に入っている。目指すのは、2030年までに輸出額を世界全体で2,050億円にすることだ(香港 243億円、米国 368億円、台湾 206億円など)。
| 国・地域名 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 数量 | 金額 | 数量 | 金額 | 数量 | 金額 | 数量 | 金額 | 数量 | 金額 | 前年比伸び率(%) | |||
| 数量 | 金額 | ||||||||||||
| 1 | 香港 | 12,629 | 15,423 | 13,755 | 17,806 | 11,958 | 16,304 | 12,104 | 18,266 | 11,579 | 18,776 | △ 4.3 | 2.8 |
| 2 | 米国 | 6,768 | 7,438 | 9,094 | 11,329 | 9,971 | 14,121 | 10,072 | 14,100 | 12,044 | 18,071 | 19.6 | 28.2 |
| 3 | 台湾 | 7,014 | 8,352 | 8,253 | 10,176 | 9,629 | 12,148 | 9,744 | 13,499 | 9,467 | 14,004 | △ 2.8 | 3.7 |
| 4 | 中国 | 8,399 | 12,843 | 10,298 | 16,280 | 11,427 | 17,777 | 8,819 | 13,331 | 6,960 | 10,857 | △ 21.1 | △ 18.6 |
| 5 | 韓国 | 1,492 | 1,576 | 1,901 | 2,063 | 2,721 | 3,398 | 3,786 | 4,698 | 5,092 | 6,544 | 34.5 | 39.3 |
| 6 | シンガポール | 2,335 | 2,983 | 3,119 | 4,239 | 3,359 | 4,979 | 2,659 | 4,331 | 2,550 | 4,623 | △ 4.1 | 6.7 |
| 7 | タイ | 973 | 1,081 | 1,280 | 1,371 | 1,638 | 1,896 | 2,082 | 2,340 | 2,125 | 2,601 | 2.1 | 11.2 |
| 8 | カナダ | 853 | 1,083 | 991 | 1,262 | 1,090 | 1,527 | 1,295 | 2,001 | 1,376 | 2,350 | 6.2 | 17.5 |
| 9 | ベトナム | 835 | 1,154 | 1,067 | 1,411 | 1,504 | 1,996 | 1,422 | 1,941 | 1,755 | 2,338 | 23.4 | 20.5 |
| 10 | マレーシア | 438 | 584 | 720 | 1,050 | 999 | 1,470 | 792 | 1,263 | 878 | 1,544 | 10.9 | 22.3 |
| その他 | 4,444 | 4,614 | 5,928 | 6,712 | 6,566 | 8,268 | 6,644 | 9,305 | 7,793 | 11,564 | 17.3 | 24.3 | |
| 世界 | 46,180 | 57,131 | 56,406 | 73,697 | 60,863 | 83,884 | 59,419 | 85,075 | 61,619 | 93,272 | 3.7 | 9.6 | |
出所:財務省貿易統計からジェトロ作成
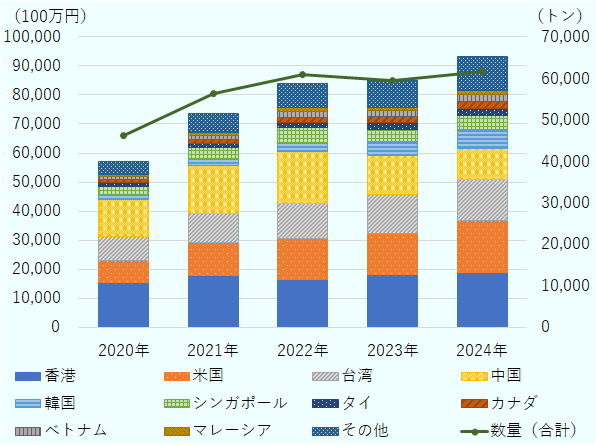
出所:財務省貿易統計からジェトロ作成
アニメ・漫画人気が日本産菓子への関心を後押し
日本のアニメや漫画に登場する日本食(すし、ラーメンなど)などと同様に、登場人物と同じ菓子を食べてみたいと関心を持つ人々が増えている。海外でなじみがないにもかかわらず「Taiyaki(たい焼き)」や「Mochi(もち)」などの和菓子が世界に広まっているのは、その一例だ。和菓子だけでない。洋菓子のフレーバーとして、「Matcha(抹茶)」や「Yuzu(ゆず)」が世界各国で定着した。
北米最大のアニメ関連展示会「アニメエキスポ2025」(2025年7月3~6日、米国ロサンゼルスで開催)には、日本食ブースエリアを設置。どら焼きやゴーフル、モチアイス、抹茶ラテなど、日本産菓子をプロモーションした。アニメや漫画と同様に、好評だったという(詳細は、2025年7月16日付ビジネス短信参照)。
もっちり食感、涼感のあるわらび餅に注目
ここからは、これから世界市場での注目が期待できる和菓子として、わらび餅を取り上げる。目下、インバウンド観光客に徐々に人気が出始めたところだ。
そもそも、わらび餅は、わらび粉、水、砂糖を鍋で火にかけ、冷やし固めた菓子だ。主材料のわらび粉は、山菜のわらびから作る。原料になるのは、葉や茎ではなく根の部分。そこから採れるでんぷんを乾燥させて粉末状にする。こうした製法は、日本人でもなかなか知らないだろう。食べ方としては、きな粉や黒蜜をかけるのが一般的だ。
食感(もっちりとして、ぷるぷる)や、透明感のある見た目が、涼感を呼ぶ。それだけに、夏によく食べられる。味覚も独特で、もちや他のスイーツと異なる。ヘルシーなイメージのため、日本人だけでなくグローバルで人気になる可能性を秘める。
ただし、課題もある。山菜のわらびは、採取やわらび畑での栽培、わらび粉への加工に非常に手間がかかるのだ。そのためわらび粉は、昔から希少かつ高価だった。現在、日本国内で一般販売されている商品には、いも類(サツマイモやタピオカなど)から採れたでんぷんを代用したもの(あるいは、これらをわらび粉と混ぜ合わせたもの)が多い。
川崎大師にてわらび餅専門店を創業、セレクトショップで大人気
真言宗智山派の大本山・平間寺は、「厄除けのお大師さま」として広く知られる。1128年建立の通称「川崎大師」だ。
その仲見世通りに2006年、わらび餅専門店「大谷堂」が開業した。大谷茂社長は川崎市生まれで、かねて菓子販売に携わってきた。多くの和・洋菓子を見て食べ歩く中で感銘を受けたのが、京都の嵐山で食べたわらび餅だった。大谷氏は、同店での修行を決意、嵐山の店主に懇願し「わらび餅作り」を一から学んだ。その経験を生かし、原料の選定や製法の改良を重ねた。そして、ついに「大谷堂のわらび餅」の完成に至った。
同社のわらび餅の種類は、数多い。きな粉や黒蜜をかけるほか、宇治抹茶、黒ごま入りきな粉、ほうじ茶入りきな粉などがある。そのほか、トロトロあつあつのわらび餅を釜からすくい、カップに盛り付ける「釜揚げわらび餅」も人気だ。
懸命な営業努力の結果、今では川崎大師の名物だ。「久寿餅(くずもち)」「大師巻き」「とんとこ飴(あめ)〔咳(せき)止め飴〕」などと並ぶ存在になっている。
初詣シーズンの年初は、多くの参拝客が訪れる。この時期の売り上げは、例年順調だ。しかし、それ以外のシーズンは伸び悩む。そのため、同社は閑散期の卸売り・小売りに、地道に営業活動を進めた。その結果、大手の日本食材のセレクトショップや百貨店などで販売してもらうことができ、高い評価を受けている。


台湾のFood Taipei2018に出展、海外への輸出を開始
そうした中、2017年に、地元金融機関の川崎信用金庫がジェトロ横浜を紹介。販路拡大の一環で、海外に展開する取り組みを開始した。食品分野の専門家と面談を重ね、海外展示会に向け準備。翌2018年、「Food Taipei2018」(台湾)のジャパンパビリオンに初めて出展した。会期中には多くの現地バイヤーや飲食店などから、引き合いがあった。初年度から海外展開の手応えを感じたという。このため、出展後も現地へ何度も出張して意欲的に商談・営業し、台湾への輸出に成功した。
大谷社長は、「中小企業が海外ビジネスを成功させるためには、現地でのエンドユーザー(実際に商品を使ってくれる飲食店などの顧客)を見つけることが最も大事」と、当時を振り返る。「日本側の商社、現地側の商社、卸売り、エンドユーザーを見つけて、つなげていくことがポイント。海外ビジネスも国内同様、根気強く熱心にアプローチをして人間関係を築くことがカギになる」と語った。
もっとも、新型コロナ禍の影響もあって、台湾への輸出は残念ながら途切れた。しかし、タイやベトナムなどには、輸出が継続している。海外売上高は現時点で、全体の5%ほど。デザートやスイーツを中心に同社商品を採用しているのは、目下のところ現地に進出する日系飲食店だ。しかしわらび餅の認知度・人気が高まると、スイーツの選択肢の1つとして現地系飲食店(スイーツ、日本料理など)でも販路拡大を期待できる。

「本物のわらび餅」づくりへの挑戦
海外展開を進めるにあたり、製造面での課題として、大谷社長は「本わらび粉の卸値がなぜこんなに高いのか」という壁に当たった。粉問屋、製粉メーカー、本わらび粉生産者からは、「日本国内で本わらび粉を作っている生産者が減っていて、いずれは手に入らなくなってしまうだろう」と聞かされた。生産者の高齢化で製法を引き継ぐ人がなく、それが生産量の減少につながっている。このままでは、日本の伝統的な本わらび粉の製造方法が途絶えてしまうと、危機感を感じた。
伝統的な製法を継承し、原料生産から取り組み、丹精込めて作ったわらび餅を拡販できないものか。「日本の食文化であるわらび餅を次世代につなげ、世界に広めたい」という大谷社長の強い思いの下、新たなプロジェクトが始動した。
大谷堂は2016年、山梨県北杜市小淵沢に約3,000坪(約1万平方メートル)のわらび畑を確保。畑が立地する南アルプス地域は、良質な水に恵まれている。そんな地で、自らわらび作りを開始したわけだ。また、約50年前まで本わらび粉を製造していた飛騨地域の村を知り、大谷社長自ら現地に赴いた。地元のお年寄りたちから本わらび粉の伝統的な生産方法を教わり、本格的に純国産のわらび粉製造を開始した。現在、わらびの根を年間で約2トン収穫。わらび粉を約40キロ生産している。生産は、今後さらに増やしていく予定だ。
さらに本プロジェクトを進めるにあたり2019年、資金調達手段の1つとして、川崎信用金庫からの提案でクラウドファンディングを活用した。また、こだわったのは、製造方法だけではない。マーケティング面で、商品のパッケージからウェブサイトまでデザインを一新。「ichi いち![]() 」として新規商品化し、「本物のわらび餅」を完成させた。
」として新規商品化し、「本物のわらび餅」を完成させた。
スイーツとしてのわらび餅、世界へ
「これらのストーリーとともに、高品質でおいしい、本物のわらび餅(Warabi-Mochi)を海外市場にもアピールしていきたい」と大谷社長は語る。
とは言え、伝統的な製造方法や既存の食べ方にこだわるばかりではない。むしろ、柔軟に新商品を開発できる食材という強みを生かしたい。実際、フレーバー(マンゴーやパイナップルなど)やトッピングなど、海外でのニーズや取引先からの要望に合わせてきた。また、パフェや、飲食店向けにデザート用の新規スイーツを生み出す余地もある。例えば、タピオカドリンクのように飲める「わらび餅ドリンク」などが生まれた。
新規性のあるメニューの開発と展開は、訪日外国人(インバウンド)への訴求力を高める。同時に、海外市場における現地ニーズへの対応にもつながる。インバウンドと輸出の両面で、わらび餅のグローバル展開が加速する可能性を秘めているわけだ。世界の消費者がスイーツとしてわらび餅を受け入れ、次の日本食材ブームにつながることを期待したい。



- 注:
-
ここで紹介した輸出実績は、農林水産省や全日本菓子協会の統計データと対象が異なる。そのため、相互に数値が一致しない。
本レポート上では、米菓などを含めた菓子類全体を扱っている。なお、対象のHSコードは、1704〔砂糖菓子(チューイングガム、キャンディーなど)〕、1806(チョコレートその他のココアを含有する調製食料品など)、1905〔パン、ペーストリー、ケーキ、ビスケットその他のベーカリー製品、米菓(あられ、せんべい)など〕。

- 執筆者紹介
-
ジェトロ農林水産食品部 市場開拓課調査チーム 課長代理
古城 達也(ふるじょう たつや) - 2011年、ジェトロ入構。人材開発支援課、ジェトロ横浜、ジェトロ・ニューヨーク事務所、ジェトロ諏訪を経て、2024年11月から現職。現在、農林水産物・食品の輸出に関して、各国の輸入規制、法令や市場情報などの調査や、日本企業からの輸出相談窓口を担当。






 閉じる
閉じる





