グローバル市場に挑む日本酒:中沢酒造の取り組みから見る可能性
2025年8月29日
近年、国内における日本酒需要は、消費者の嗜好(しこう)の変化や人口減少の影響を受け、縮小傾向にある。一方、海外市場では日本食ブームやインバウンド需要の高まりを背景に、日本酒の輸出は堅調に推移している。加えて、日本酒は、農林水産省の輸出拡大実行戦略![]() (2025年5月)において、輸出重点品目に指定されている。
(2025年5月)において、輸出重点品目に指定されている。
このことから、今後も輸出拡大が見込まれる日本酒の輸出実績や動向をまとめるとともに、近年、海外事業展開に積極的に取り組んでいる事例として、中沢酒造株式会社![]() (神奈川県足柄上郡松田町)にヒアリングした。同社は1825年創業、丹沢山系の伏流水と高品質な酒米を用いた全量手造りの酒造りを特徴とする。今回は、11代目蔵元の鍵和田亮氏(専務取締役)に海外展開の現状や今後の展望について聞いた(取材日:2025年7月15日)。
(神奈川県足柄上郡松田町)にヒアリングした。同社は1825年創業、丹沢山系の伏流水と高品質な酒米を用いた全量手造りの酒造りを特徴とする。今回は、11代目蔵元の鍵和田亮氏(専務取締役)に海外展開の現状や今後の展望について聞いた(取材日:2025年7月15日)。

産地呼称制度もテコに、着実に進展する日本酒の海外市場開拓
2024年の日本酒(HSコード=2206.00-200)の輸出額は、前年比5.8%増の434億5,630万円、輸出量は6.4%増の3万1,054キロリットルであった(図1参照)。輸出相手国・地域別にみると、1位の中国が前年比6.2%減の116億7,140万円(構成比26.9%)、2位の米国が同25.9%増の114億4,190万円(26.3%)、3位の香港が同15.1%減の51億1,680万円となった(11.8%)(表および図2参照)。
国税庁統計によると、日本酒の生産量は2015年度から2023年度の間に26.7%、販売(消費)量は29.7%、それぞれ減少した。国内市場での日本酒離れが懸念される中、輸出はこの間、対生産量比で4.1%から9.1%まで上昇しており(財務省貿易統計)、今後の事業の継続・成長を海外での販路開拓に求める日本酒生産者のさらなる裾野拡大が期待される(図3参照)。
なお、前述の農林水産省の輸出拡大実行戦略によると、日本酒は2030年までに輸出総額760億円(うち中国200億円、米国200億円、香港90億円など)を目標としている。
| 国・地域名 | 2022年 | 2023年 | 2024年 |
対前年比 (2023年/2024年) |
|---|---|---|---|---|
| 中国 | 14,161 | 12,447 | 11,671 | △6.2 |
| 米国 | 10,930 | 9,091 | 11,442 | 25.9 |
| 香港 | 7,116 | 6,024 | 5,117 | △15.1 |
| 韓国 | 2,523 | 2,905 | 3,744 | 28.9 |
| 台湾 | 2,222 | 2,677 | 2,670 | △0.3 |
| シンガポール | 2,326 | 1,510 | 1,484 | △1.7 |
| カナダ | 1,163 | 755 | 1,041 | 37.9 |
| オーストラリア | 932 | 645 | 782 | 21.4 |
| 英国 | 607 | 544 | 637 | 17.2 |
| フランス | 524 | 488 | 552 | 13.0 |
| その他 | 4,986 | 3,979 | 4,317 | 8.5 |
| 総計 | 47,489 | 41,063 | 43,456 | 5.8 |
注:HSコードは2206.00-200。
出所:財務省貿易統計からジェトロ作成
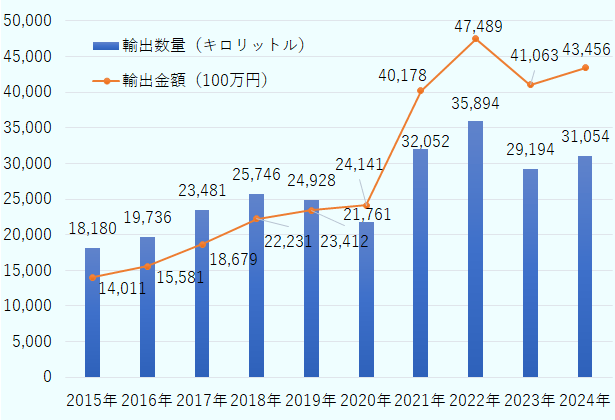
注:HSコード=2206.00-200。
出所:財務省貿易統計からジェトロ作成
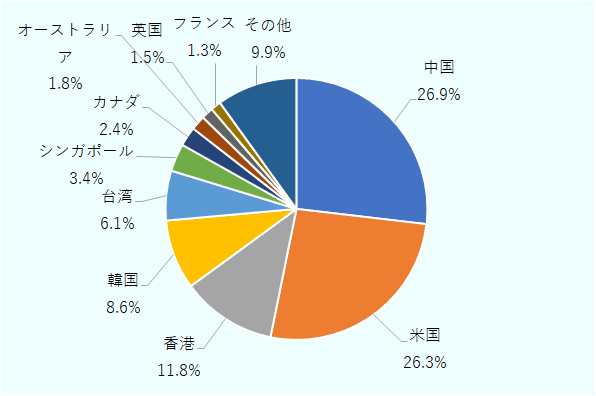
注:HSコード=2206.00-200。
出所:財務省貿易統計からジェトロ作成
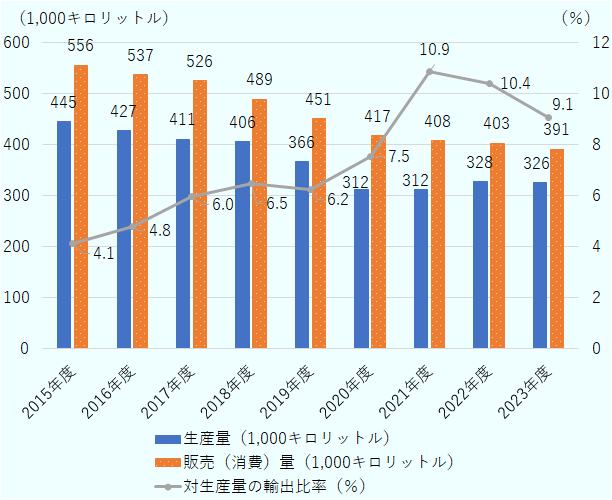
注:HSコードは2206.00-200。
出所:国税庁統計、財務省貿易統計からジェトロ作成
そうした中、農林水産省では、地域固有の自然的、人文的、社会的な要因の中で育まれてきた品質、社会的評価などの特性を有する産品の名称を、地域の知的財産として保護するため、地理的表示(GI)保護制度の整備を進めている。2015年には国レベルのGIとして「日本酒」が指定された。これにより、国内産米を使用し、日本国内で製造された清酒のみが「日本酒」として表示可能となった。さらに、地域別GI登録も進展しており、2023年以降「信濃大町」「岩手」「静岡」「南会津」「伊丹」「喜多方」「青森」などが新たに登録されている(注1)。先述したように、日本酒輸出は堅調に推移しており、国際市場には多くの日本酒が流通している。こうした状況では、他のアルコール飲料や競合する日本酒ブランドとの差別化がますます重要となっている。GI保護制度は、日本酒の品質や産地の特性を保証する制度としてだけでなく、地域ごとの歴史や風土に根差したストーリー性を付加することが可能となる。そのため、海外のバイヤーや消費者に対して強い訴求力となり得ることから、日本酒の持続的な海外展開を支える重要な要素となっている。
その成果として、インド政府は2024年4月1日付でGI「日本酒」を登録した。これにより、事実上輸入が規制されていた日本酒は、成分分析を経ずにインドへの輸出が可能となった(ジェトロ調査レポート「日本酒のインドへの輸出に係るルール変更、手続きについて」および2024年6月5日付ビジネス短信「インドの日本酒輸入に係る新制度を開始、地理的表示に登録」参照)。
東京五輪開催を契機に、新たな商品開発と海外販路開拓に着手
中沢酒造は、2015年ごろから、東京2020オリンピック競技大会開催を見据えたインバウンド需要の高まりに対応すべく、主に訪日外国人および日本酒に馴染みのない若者をターゲットとする商品「S.tokyo![]() 」の開発に着手した。これを契機に海外市場への関心も高まり、2018年には横浜銀行に輸出の相談を持ちかけたことをきっかけに、ジェトロ横浜を紹介され、輸出や展示会出展にかかる相談対応などの支援を受けることとなった。
」の開発に着手した。これを契機に海外市場への関心も高まり、2018年には横浜銀行に輸出の相談を持ちかけたことをきっかけに、ジェトロ横浜を紹介され、輸出や展示会出展にかかる相談対応などの支援を受けることとなった。

ジェトロのアドバイスのもと、初めての海外展示会出展に向けて、英語版の広報資料や商談資料、試食品などを準備した。2019年にシンガポールで開催された「Food Japan2019」のかながわよこはまブース(横浜貿易協会、ジェトロ横浜主催)に出展(参考:Food Japanウェブサイト参照![]() )。入念な事前準備に加え、現地では多くの商談を通じて積極的な商品のPR、売り込みを行い、現地企業からの引き合い獲得に成功した。同展示会では、マーケティング調査として、来場者に好みの商品を選んでもらう簡易的なアンケートを実施した。輸出事業を推進するため複数の商品を持ち込んだものの、「S.tokyo」が圧倒的な支持を集める結果となった。これを踏まえ、同社は自信をもって「S.tokyo」を輸出の主力商品として位置づけ、ラインアップを絞ることができたため、海外バイヤーから認識してもらいやすくなったことが取引先の拡大につながった。
)。入念な事前準備に加え、現地では多くの商談を通じて積極的な商品のPR、売り込みを行い、現地企業からの引き合い獲得に成功した。同展示会では、マーケティング調査として、来場者に好みの商品を選んでもらう簡易的なアンケートを実施した。輸出事業を推進するため複数の商品を持ち込んだものの、「S.tokyo」が圧倒的な支持を集める結果となった。これを踏まえ、同社は自信をもって「S.tokyo」を輸出の主力商品として位置づけ、ラインアップを絞ることができたため、海外バイヤーから認識してもらいやすくなったことが取引先の拡大につながった。
直後に新型コロナ禍という逆風に見舞われたものの、綿密な準備を伴うオンライン商談の活用により、海外展開への取り組みを継続した。現在では韓国、台湾、シンガポール、中国、米国、スペイン、ドイツ、フランスの8カ国・地域に輸出を行い、海外売上比率は約5%まで拡大している。同社は、輸出先のさらなる多角化ではなく、既存市場での販売数量の拡大を重視しており、日本酒の味や文化的背景を理解するバイヤーとの息の長い関係の構築を志向している。
また、インバウンド需要の高まりにより、酒蔵への外国人観光客の来訪はコロナ禍以前から増加傾向にあり、近年では電車に加え、遠方からレンタカーを利用してくる訪問者も増えている。特にアジア圏(シンガポールなど)からの観光客の増加を受けて、英語対応可能なスタッフを雇用するなど、受け入れ体制の強化、海外ファン層の拡大にも取り組んでいる。

伝統と革新を融合させ、市場のトレンドを押さえて海外展開を推進
「S.tokyo」は、白ワインに似たすっきりとした味わいと、従来の日本酒とは一線を画すモダンなパッケージデザインが、海外市場において評価獲得の要因となっている。特に、シンガポール市場では、対日インバウンド増や取り扱い店舗の拡大による飲酒機会の増加などを背景に、日本酒への理解が進んでいる。甘口から辛口・すっきり系への嗜好の変化が見られるなど、消費者ニーズの多様化も進展しており、同社商品の拡販に追い風となっている。
こうした市場動向も踏まえ、同社ではスパークリングタイプの日本酒や、国・地域ごとの嗜好に応じた販売戦略を推進する方針である。海外売上比率については、現状の約5%から10%への引き上げを目標としており、既存市場での販売拡大を軸に、持続可能な海外展開を目指している。

 と和釜
と和釜 (注2)(ジェトロ撮影)
(注2)(ジェトロ撮影)
国内の日本酒需要は縮小傾向に直面する一方で、海外では新たな成長の可能性を見いだし得る。その際、既に多くの日本酒が海外に輸出されて市場に出回っている中で、他の日本酒をはじめとした競合するアルコール飲料との差別化をうまく図る必要がある。各社の日本酒に、それぞれの伝統に根差した独自のストーリー性を持たせ、これを海外のバイヤー、消費者にわかりやすく伝えることが市場戦略として重要である。
中沢酒造のように、伝統的な酒造りを守りながらも市場の変化に柔軟に対応し、海外展開に挑戦する酒蔵の取り組みは、今後の日本酒輸出拡大に向けた良きモデルケースとなるだろう。地域資源としての日本酒の価値を世界に伝えるとともに、各国の嗜好や文化に寄り添った商品開発と市場戦略が求められる。

- 注1:
-
地域別GIの登録名称や詳細などは国税庁「酒類の地理的表示一覧」
 を参照のこと。
を参照のこと。
- 注2:
- 槽搾り機は、発酵が完了したもろみに圧力をかけながら、酒と酒粕(さけかす)に分離する伝統的な装置である。また、コメを蒸す作業(蒸きょう)には、昔ながらの和釜を用いている。

- 執筆者紹介
-
ジェトロ農林水産食品部 市場開拓課調査チーム 課長代理
古城 達也(ふるじょう たつや) - 2011年、ジェトロ入構。人材開発支援課、ジェトロ横浜、ジェトロ・ニューヨーク事務所、ジェトロ諏訪を経て、2024年11月から現職。現在、農林水産物・食品の輸出に関して、各国の輸入規制、法令や市場情報などの調査や、日本企業からの輸出相談窓口を担当。

- 執筆者紹介
-
ジェトロ農林水産食品部 市場開拓課調査チーム
庄田 幸生(しょうだ こうき) - 2025年、ジェトロ入構。現在、農林水産物・食品の輸出に関して、各国の市場情報や輸入規制、法令などの調査を担当。




 閉じる
閉じる






