インドから広がるQRコード決済革命
国家主導UPIの国際展開
2025年4月24日
インドにおけるデジタル経済の進展は著しく、特に決済分野では、国家主導の制度設計が実を結びつつある。その象徴が、2016年に導入された統合決済インターフェース(Unified Payments Interface:UPI)だ。UPIは、国内の金融包摂を大きく推進すると同時に、近年はその国際展開を通じて「インド型デジタル公共財」としての存在感を高めている。本稿では、UPIの制度的な構造と国際展開の現状を整理し、日本企業の対応や日本での制度設計への示唆を検討する。
UPIの制度設計と国内普及
UPIは、インド準備銀行(中央銀行、RBI)とインド決済公社(NPCI)が設計した即時決済インフラシステムだ。政府系機関が共通基盤としてのシステムを構築し、民間の銀行やフィンテック企業が多様なアプリケーションを提供する官民協働の構造を採用している点に特徴がある。これにより、公共性の担保と市場競争の両立を図っている。
また、UPIの普及を支えた制度的前提として、インド政府は2010年代以降、「アーダール(Aadhaar)」の付番を進めてきた。アーダールは、生体情報(指紋・虹彩)と顔写真が登録された全国民のデジタルIDだ。このIDの付番と、それを活用した銀行口座の一斉開設政策(Jan Dhan Yojana)の効果が大きい。2024年10月時点で、アーダール登録者数は13億8,400万人に上る。アーダールにより本人確認が迅速かつ低コストで可能となった。これまで金融サービスの枠外にあった多数の国民が公式の金融システムに初めてアクセス可能となり、UPIによる決済機能の恩恵を受ける土壌が整った。
こうして導入されたUPIは、政府の「デジタル・インディア」政策(注)、スマートフォンの普及、新型コロナウイルスのパンデミック下での非接触決済需要の高まりなどを背景に、短期間で爆発的に普及した(図参照)。今日では、銀行の支店のない農村部を含めたインド全域でUPIを通じた送金や支払い、公共料金支払いが日常的に行われている。
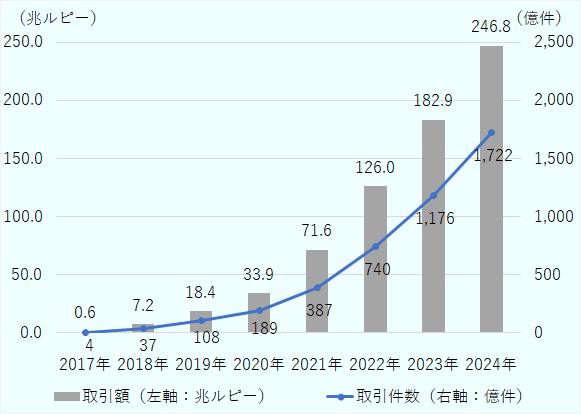
出所:インド決済公社(NPCI)公表資料を基にジェトロ作成
UPIは、日本のQRコード決済とは違い、インドの銀行口座とスマートフォンを持っていれば、誰でも無料で使える決済システムだ。利用者は、地場のフォンペ(PhonePe)、ペイティーエム(Paytm)、米国のグーグルペイ(Google Pay)など、UPIに対応した決済アプリをインストールし、自分の銀行口座を登録する。送金・支払いは携帯番号やQRコードを使ってリアルタイムで完了し、銀行名や口座番号の入力は必要ない。日本のPayPayや楽天ペイなどのQRコード決済は、プリペイド型やクレジットカード連携型なのに対し、UPIは銀行口座と直接つながっており、即時に口座からの引き落としが行われる。
国際展開と「制度輸出」の動き
UPIはインド国内での成功を機に、2021年以降、海外への展開を本格化させている。NPCIの国際部門NIPLが中心となり、南西アジアや中東、ASEAN、欧州での導入が進められている。導入形態は国ごとに異なるが(表参照)、インド国内でUPI登録済みの利用者が渡航先で現地のQRコードを使って支払いを行う形式が一般的だ。ただし、通貨換算や越境(クロスボーダー)送金といった本格的な国際決済については、シンガポールで一部実現している例を除き、多くの国では制度整備の途上にある。
| 国・地域名 |
導入 時期 |
対象利用者 | 備考 |
|---|---|---|---|
| ブータン | 2021年7月 | インド国内UPI登録済みの利用者 | 初の海外導入。ブータン王立通貨庁(RMA)と連携し、QR決済に対応 |
| ネパール | 2022年2月 | インド国内UPI登録済みの利用者 | 店舗などでのUPI決済は可能だが、個人送金(国際送金)機能は未対応 |
| シンガポール | 2023年2月 | 両国でUPI/PayNow登録済みの利用者 | シンガポールのペイナウ(PayNow)と相互接続済みで、個人間の双方向送金に対応。通貨換算機能も実装済み |
| フランス | 2024年2月 | インド国内UPI登録済みの利用者 | 観光施設を中心にQR決済導入。インド人観光客の利便性向上を目的とする |
| スリランカ | 2024年2月 | インド国内UPI登録済みの利用者 | スリランカのLankaPayはQR決済に対応。送金機能は今後導入予定 |
| モーリシャス | 2024年2月 | インド国内UPI登録済みの利用者 | 人口の多くを占めるインド系住民との文化的・経済的関係を背景に導入。主に観光客によるQR決済を想定 |
| アラブ首長国連邦(UAE) | 2024年7月 | インド国内UPI登録済みの利用者 | 現地店舗でのQR決済対応 |
出所:各国当局プレスリリース、各種報道を基にジェトロ作成
近年では、外国人旅行者の利便性向上を目的とした新たな取り組みとして、2024年7月に「UPI One World」が導入された。インドを訪れる外国人旅行者が現地の銀行口座を持たずとも、一時的にUPIウォレットを開設し、QRコードによる決済を利用できる仕組みだ。2023年9月にニューデリーで開催されたG20サミットで初めて紹介されたこともあり、まずはG20諸国からの渡航者を対象に展開されている。このような取り組みは、UPIをより多様な利用者や利用環境に対応させていく流れの一部といえる。
また、RBIは、国際決済システムの相互接続を目指す国際決済銀行(BIS)主導の構想「プロジェクト・ネクサス(Project Nexus)」に参加しており、シンガポール、タイ、マレーシアなどの即時決済システムとの接続が検討されている。これが実現すれば、Project Nexusに接続された国同士ならば、利用者は相手の国に関係なく、通常時と同じ操作で送金できる。相手には現地通貨で同時に振り込まれるようになる。つまり、日常の国内送金と同じ感覚で多国間の国際送金が可能となり、コストや利便性の面でも大きな前進が期待される。このような取り組みは、UPIの国際展開が単なる制度輸出にとどまらず、クロスボーダー決済インフラの制度間連携が進みつつあることを示している。
日本での制度設計と企業活動への示唆
インドのUPIが示す「公共インフラ+民間競争」の制度設計は、日本にとっても学ぶ点が多い。特にUPIはインド国民の大多数が日常的に利用しており、識字率や技術リテラシーが高くない層にも広く受け入れられている。このような普遍的な制度設計に加え、制度運用の枠組み自体に日本が学ぶべき点が複数存在する。
まず注目されるのは、官民の役割分担が明確に制度化されている点だ。UPIは、RBIとNPCIが共通基盤を整備し、その上で民間銀行やフィンテック企業が多様なアプリやサービスを提供する構造となっている。このように、政府系機関が中立的なインフラを提供し、民間が競争的にサービスを展開するという設計は、制度的な公平性とイノベーションの両立を意図した構造だ。
また、UPIが即時決済を原則無料で提供している点も重要だ。制度的に送金コストを抑えつつ、24時間、即時に利用可能とすることで、個人や企業を問わず、幅広く利用することができる。このようなコストと利便性の両立は、日本でも、キャッシュレス化を促進させる上で重要な論点となるだろう。
さらに、UPIは相互運用性が制度の根幹に組み込まれており、どの銀行口座、また、どのアプリでも、共通の操作で送金・受け取りが可能となっている。QRコードも統一されており、店舗側の負担を大幅に軽減している。実際には、PhonePeやグーグルペイなどのアプリ事業者が代理店網を通じてQRコードを配布することが多く、店舗が掲示するコードにアプリ名が表示されている例も多い。ただし、これらは共通規格に準拠しており、個別に契約を結ばずとも、銀行口座さえあれば受け取りができる。このような設計も、UPIの普及を支える制度上の特徴の1つといえる。
日本でも、QRコード決済の統一に向けて、「JPQR」と呼ばれる共通フォーマットの導入が進められている。複数の決済サービスに1つのコードで対応可能になるなど、標準化は一定程度進展している。しかし、支払い方式がプリペイド型、デビット型、ポストペイ型に分かれているほか、処理経路や入金タイミング、決済の即時性や手数料体系など、サービスごとの違いが残っている。UPIのように制度として相互運用性が確保されている仕組みとは、構造的に異なる。
UPIのような制度が日本に導入された場合、民間事業者の事業戦略や収益モデルに一定程度の影響が及ぶと考えられる。とりわけ、無料・即時・銀行口座直結というUPIの基本構造は、日本の既存のQRコード決済サービスが採用してきたチャージ型やクレジットカード連携型の仕組みとは根本的に異なる。日本国内で普及すれば、利用者の期待や加盟店側の対応が変化し、既存のビジネスモデルに見直しを迫る場面も出てくる可能性がある。
UPIのように、中立的な共通基盤の上で多様な事業者がサービスを競い合う構造は、制度的な公共性と民間活力のバランスを取る点で、日本での今後の制度設計や市場形成を考える上でも参考になるだろう。
おわりに
UPIは単なる決済技術ではなく、金融包摂、現金経済からの脱却、行政効率の向上といった多層的な政策目的を同時に実現している点で、国内外から注目を集めてきた。また、インド政府はUPIを国際社会に向けて「制度」として輸出しようとする姿勢を打ち出しており、南西アジアやグローバルサウスでのデジタル主権や政策的影響力の一翼を担っている。
今後、UPIをはじめとするインド発の「デジタル公共財」が国際標準として定着するか否かは、制度の透明性や信頼性、相互運用性の確保にかかっている。日本としては、制度の標準化や相互運用性の枠組みがどのようなかたちで構築されていくのか、注意深く見極めつつ、共創的に関与していくことが考えられるだろう。
- 注:
- 2015年に開始されたインド政府の国家ICT(情報通信技術)戦略で、行政サービスの電子化、デジタルインフラ整備、国民のITアクセス拡大を通じ、包摂的なデジタル社会の実現を目指す。

- 執筆者紹介
-
ジェトロ・ムンバイ事務所
篠田 正大(しのだ まさひろ) - 2013年、財務省入省。関東財務局で財政融資資金の運用などに従事したほか、国際局で外国為替市場の調査、外貨準備の運用、アジア近隣諸国との金融協力などを担当。2024年7月から現職。






 閉じる
閉じる





