第一生命HDのインド戦略
急成長を遂げたインド生命保険市場(2)
2025年9月16日
堅調な経済成長を背景に、インドの生命保険市場が成長を続けている。(連載前編を参照)。本稿では、大手生命保険会社の進出事例として、第一生命ホールディングス(HD、以下、第一生命)の事業戦略を取り上げる。同社はインドの生命保険市場の可能性にいち早く着目し、グローバル・ケイパビリティー・センター(GCC、注1)も設立した。特に(1)進出の経緯や(2)GCCの設置や活用について追っていく。(1)については、海外生保事業ユニット、ラインマネジャーの渡邊佳生氏と現地合弁会社スター・ユニオン・第一ライフ(Star Union Dai-ichi Life/以下、SUD)設立時の担当者で、現アカウンティングユニット、ラインマネジャーの熊野一穂氏に聞いた(ヒアリング日:7月9日)。(2)については、専務執行役員グループCIO(Chief Information Officer)兼CDO(Chief Digital Officer)のスティーブン・バーナム氏に聞いた(ヒアリング日:7月17日)。市場動向を分析した前編に続き、インド生命保険市場に関する連載後編だ。


人口動態、経済成長の可能性に着目して進出を視野に
第一生命は2007年、初めての海外市場としてベトナムに進出。その後もアジア市場を中心に、第2の成長市場を探していた。
その中でインドを選んだ理由は3つある。1つ目は、外資系生命保険会社の参入が可能になった2000年以降、インドの保険市場が活性化していたこと、2つ目は、若年層中心の人口構成、3つ目は、経済成長に伴って国民の所得が向上していることだ。各種統計調査によると、1人当たりGDPが1,000ドル(注2)を超えると、生命保険の加入率が急速に伸びるという統計データもある。その結果、今後の成長を踏まえ、インド進出の検討を開始した。
銀行との合弁契約締結に難航
第一生命はSUD設立に当たり、2007年にインドの国有銀行バンク・オブ・インディア(BOI)とユニオン・バンク・オブ・インディア(UBI)の3社間で、合弁契約を締結した。しかし熊野氏は、「契約の締結にあたり全てが順風満帆に進んでいったわけではない」と語る。合弁契約を締結するための銀行が1年以上見つからず、契約交渉もかなり難航した。転機が訪れたのは、当時のチダンバラム財務相が外資による出資を求め訪日したタイミングである。その際に、当時の役員が接触を試み、合弁契約を締結した銀行2行のうち1行(BOI)を紹介してもらったという。
また、銀行間との契約交渉が難航した理由に、「銀行と生命保険会社が担う役割分担の整理」を挙げた。当時のインドでは、銀行が生命保険会社を運営するのはまだ少数派だった。そのため、商品開発やシステム開発などあらゆる基幹業務を第一生命が受け持つという要求があったという。しかし、生命保険はドメスティックなビジネスで、各国で国民の所得水準や規制が異なる。日本で開発した保険商品やシステム技術をそのまま他国へ輸出して業務を進めるのは、必ずしも適切な戦略ではなかった。また、「短期的利益を求める銀行と、長期的利益を求める保険会社とでは、ビジネスモデルが異なり、価値観をそろえにいくのが困難だった」と述べた。
それでも、銀行との契約合意に至った決め手は何か。熊野氏は「まず、チダンバラム財務相の紹介というインド政府の後ろ盾があったこと。加えて、インドでの合弁案件で多くの成功実績を上げている地場大手法律事務所が契約交渉に入ったことも大きい」と当時を振り返った。これらの困難を乗り越え、SUDは2007年の設立から約2年の歳月を経て、2009年に本格的に営業を開始した。

インド拠点の保険料収入総額は順調に増加
2009年の営業開始以降、SUDの保険料収入総額は着実に増加している。直近10年の業績を見ても、右肩上がりだ(図参照)。
業績が好調な要因について、渡邊氏は「環境的要因と社内体制の強化が好影響をもたらしている」と述べた。環境面では、(1)新型コロナウイルス感染症がまん延した2020年度(2020年4月~2021年3月)以降、インド国民の保険需要が高まったことや、(2)中間所得者層の所得増が影響している。体制面では、 2021年度に実施した営業体制方針の刷新やデジタル活用による営業効率の向上を要因に挙げた。
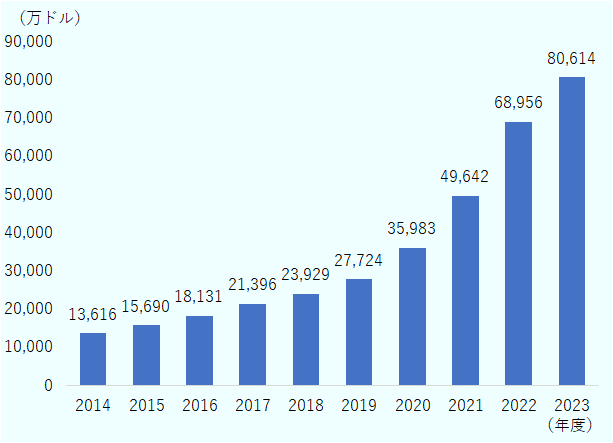
注:1ルピー=0.012ドルで換算。各年度の期間は、4月から翌年3月を指す。
出所:インド保険規制開発局(IRDAI)「Hand Book on Insurance Statistics 2023-2024」を基にジェトロ作成
今後のインドでの営業戦略については、中間・富裕層を主なターゲットとする都市部だけでなく、新規顧客開拓を進めたい地方部ともに、販売網を敷いていく方針だという。
SUDの営業は銀行窓口での販売が中心になるため、銀行支店がある地域の営業に依存する。国内には、UBIとBOI合わせて支店が約1万3,500存在する。しかし全支店が常時、保険を販売するわけではない。渡邊氏は、(1)まずは保険を継続的に販売する支店の増加と、(2)銀行員が保険販売資格を取得できるよう教育・指導も推進していくこと、に触れた。
日本の生命保険会社で初めてGCCをインドに設立
第一生命は、現在の中期経営計画(2024-2026年度)のIT・デジタル戦略で、「GCCの活用」を掲げている。また2025年6月、日本の生命保険会社として初めて、キャップジェミニ(フランスのIT大手)と、インドでGCCを設立するための複数年契約を締結したと発表した。GCCをインドに設立した主な理由として、バーナム氏は「インドにはIT・デジタル領域で優れた人材を育てるための充実した教育制度がある」ことを挙げた。国内には数多くの一流大学があり、IT技術にたけた卒業生を多く輩出している。


GCCは、ハイデラバード(インド南部)に設立される。特にハイデラバードは、インド国内の中でもグローバルで一流大学も多く、テクノロジーにたけたIT人材が豊富である。日本ではIT人材が不足しているため、第一生命は、ハイデラバードで優秀なIT人材の確保に取り組んでいくという。
課題は言語ではなく、文化の違い
インドにGCCを設立するに当たり、言語の障壁について多方面から疑問が出たという。しかし、バーナム氏は「言語の違いについては、問題視していない。課題はインドと日本の文化の違いにある」と述べる。日本とインドの橋渡し役としてバイリンガルの開発者を雇ったことにより、言語面での課題は軽減した。
しかし、依然として問題になったのは、日本とインドで仕事の進め方や考え方が違うことだった。日本では工程を細かく立て、順を追って業務処理するのが通例だ。これに対しインドでは、スピードを重視する場面が多い。
異文化が交わる中で円滑に業務を行えるよう、日本文化に理解のあるインド人を日本で採用し、その後、インドで働いてもらうといったスキームを検討しているという。また、第一生命の職員にインドまで渡航してもらい、異文化理解を深める機会を増やしていきたいと述べた。
大学と提携し、優秀なIT人材確保
インドの優れた人材は、国内で争奪戦になっている。第一生命としても、トップ人材を確保していきたい意向だ。バーナム氏は「インド工科大学(IIT)やプネ大学と提携し、両大学と良好な関係を構築できている」と述べた。
まずIITでは、日本人教授がインドの学生向けに講義している。そのほか、IITの教授が訪日する際には第一生命を訪問してもらい、同社の価値や歴史などを説明。IITに戻ってから、第一生命や日本企業で働く魅力について学生に紹介してもらっているという。
また、西部マハーラーシュトラ州立のプネ大学では、日本語(語学)の授業を第一生命がサポートしている。
バーナム氏によると、インドの大学と提携して人材を囲い込むスキームは、他社にはない第一生命ならではの強みだ。
GCCをはじめとしたIT・デジタル戦略について
第一生命は、中期経営計画で掲げるIT・デジタル戦略の中で「営業活動の活性化」と「社内業務の効率化」を検討している。
同社が近年開発した「デジタルバディ」(注3)は営業活動をサポートするデジタルツールであり、生命保険に関する商品知識や情報といったノウハウをAIに蓄積し、営業活動に活かしていくという。今後はデジタルバディのようなシステムツールをはじめ、ウェブサイトの構築や顧客に提供するアプリの開発は、GCCから導入していきたいという。
また、社内業務では職員一人一人の生産性向上を考えている。特に決算業務については、多くの時間と要員を費やすことになる。そのため、システムによる業務効率化を検討している。「商品開発や顧客管理、会計処理、人事管理など、当社の基幹業務をGCCのシステム開発を経て変えていきたい」とバーナム氏は語った。
国内市場の縮小に伴い、海外進出に要注目
第一生命は、いち早く海外市場の成長性に目を向けた。「インドの大学と提携した優秀な人材の確保」や「GCCの活用(海外を起点にしたシステム開発)」などは、日本の生命保険会社に他例のない斬新な取り組みだ。
特にインドの生命保険市場は、著しい成長を遂げてきた。2035年には、アジアで2番目の市場規模になると予想される。日本の保険会社はこれまで国内営業を中心に収益を上げてきた。しかし、今後は少子高齢化や人口減少に伴って、国内市場の縮小が想定される中、インドを含め、海外進出の加速に期待が集まる。
- 注1:
- GCCは、特定のビジネスプロセスや機能を担う多国籍企業の拠点を指す。人件費や賃料といったコストが低く、かつ優秀な人材が豊富な国に設立する。
- 注2:
- 2024年度のインドの1人当たりGDPは2,700ドル。
- 注3:
- 第一生命が開発した営業支援用AIチャットボット。顧客ニーズに応じた情報提供や商品提案をAIが支援することで、営業活動の効率化と顧客体験の向上を図る。
急成長を遂げたインド生命保険市場
シリーズの前の記事も読む

- 執筆者紹介
-
ジェトロ調査部アジア大洋州課
野本 直希(のもと なおき) - 2016年大手生命保険会社入社、2025年から現職。






 閉じる
閉じる





