実証データから読み解く、EC市場での成功要因(マレーシア)
2025年8月21日
マレーシアでは、消費者行動のデジタル化が進む。電子商取引(EC)は今や、主要な購買ツールの1つとして人々の生活に欠かせない存在だ(2024年3月27日付地域・分析レポート参照)。eMarketer(米国の市場調査会社)によると、マレーシアのEC 市場規模は2024年、約140億ドルに上った。2025年も、前年比15.5%増の予測になっている。東南アジア全体では同期間で9.9%増の予測なので、当地EC 市場の成長率は相対的に高いと言える。今後の拡大が期待できる市場と言えるだろう(図参照)。
ジェトロは、日本企業がマレーシアのEC市場の成長を取り込む支援を講じている。戦略的なEC活用により、グローバル展開を拡大させる効果的な施策を見いだすのがその狙いだ。その一環で、2024年11月~2025年3月当地ECプラットフォーム「Shopee(ショッピー)」のサイト内外で、特定のターゲット層に向けて配信するターゲティング広告などを通じ、デジタルマーケティング実証してみた。ちなみにショッピーは、マレーシアで最も利用度の高いプラットフォームだ。
本レポートでは、市場でのポジションや商品成熟度に応じた課題解決への道筋を考察。効果的なEC施策について解説する。
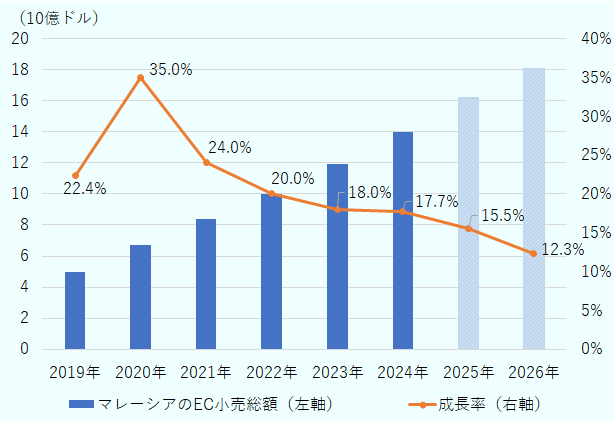
注1:2025年以降は予測値。
注2:成長率は、前年のマレーシアにおけるEC小売総額と比較した際の増加率。
出所:eMarketerからジェトロ作成
日本企業9社を対象に、ターゲティング広告を実施
本実証で採用した手法は、次のとおり。これらを通じて、商品ページへのアクセス数や売り上げの増加を図った。
- Shopeeに出店している日本企業9社の9商品を対象に、約4カ月にわたりターゲティング広告を実施。その効果を測定した(表1参照)。
ターゲティング広告とは、顧客の興味・関心に基づいて、特定のユーザーに対して広告を配信する手法だ。 - 特定ユーザーの選定にあたっては、業務委託先が保有・分析するデータ(注1)を活用し、日本企業の商品に対する潜在的な関心を推定できる(1)高所得者、(2)親世代、(3)オフィスワーカー、(4)日本文化愛好家の4つの属性の消費者をターゲットにした。
- 広告配信に合わせて、Shopeeサイト上の商品画像などのクリエーティブ(注2)を見直し、ユーザーの関心を引くよう改善を図った。
- ShopeeサイトでのSEO対策(注3)の一環として、検索キーワードを設定した。検索キーワード設定では、ユーザーが検索時に入力する可能性のあるキーワードを事前に指定し、検索行動を分析する。これにより、ユーザーがShopee上で該当キーワードを検索した際に自社商品が表示されやすくなるだけでなく、広告を検索結果の上位に表示することが可能になる。つまり、ユーザーへの訴求力が高まる。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 広告配信期間 | 2024年11月~2025年3月 |
| プラットフォーム | Shopee Malaysia |
| 参加企業 | メーカーや商社など日本企業または在マレーシア日系企業。計9社。 |
| ターゲット・定義 |
|
| 施策 |
|
出所:「マレーシアにおける日本企業のEC活用にかかるデジタルマーケティング実証事業」からジェトロ作成
今回の実証では、前述の施策に応じてパフォーマンスデータ(ページへの流入数や販売数など)の推移を分析。並行して、各社に応じた精度の高いターゲティング広告などを続けた。
その結果、マレーシアでEC販売するにあたって日本企業が取り組むべき対応を3つに類型化できた。類型ごとの特徴と実際に効果を発揮した企業の対応例を紹介する。
類型1:ターゲットを絞ることで売上増
当地で、商品の市場規模と認知度が既に一定水準に達している場合、不特定多数向けの広告よりも、対象を絞り込んだターゲティング広告が有効だ。こうした広告を打ち続けた結果、商品ページ流入数および購入率の改善が見られた。 具体的にはまず、複数のターゲット層に対して広告を配信し、パフォーマンスデータから効果の低い層を除外。商品との相性の良い層に絞って広告を打ち続ける。これを繰り返すことで注力すべきターゲット層を明確化し、広告費用対効果、ページ流入件数、商品購入率のいずれもが向上し、売り上げ増加につながった。
家庭用品メーカーA社の例
A社は、まず4つのターゲット層に対して広告を配信。広告のクリック率や購入転換率が低水準だった「日本文化愛好家」の広告を停止した。その3週間後には「親世代」を停止し、「高所得者」と「オフィスワーカー」に絞って広告を展開した。その結果、4層全てに対して広告を配信した時期と比較して、カートイン(注4)回数が1,000回以上増加するなど、改善がみられた。
さらに、適切なターゲットに対するShopee外広告も実施。これにより、本事業開始時と比較してページへのアクセス数が7,000件以上増加するなど、認知度が高まった。
類型2:適切なターゲットに異なるアプローチが必要なことも
競合企業や類似商品が市場に存在しない場合、商品ページへのアクセス数は一定程度確保しやすくなる。一方で、ページ訪問者を購入に至るまで誘導することに課題が生じる場合がある。
こうした場合に購入率が伸び悩む原因は何か。ページ閲覧には至っても購入を決断するための情報が不足し、「なぜその商品が必要か」が消費者に十分に伝わっていないことが考えられる。そのため、ターゲティング広告以前に、消費者に対してその商品を欲しいと思ってもらえるような需要喚起の取り組みが必要になる。
具体的には、商品の使用方法や必要性、効果を客観的根拠にもとづき示す広報素材の準備や、購入者による商品レビューの充実が有用だ。これによって、ユーザーに安心感を与え、購入を後押しすることができる。
その後、インフルエンサーなどを活用してブランド認知度を向上させ、購入を促進することも効果的だ。
独自の自動車関連用品を製造するB社の例
B社は、自動車保有率の高いマレーシアで潜在顧客が見込むことができた。そこで、自動車所有と親和性が高い「富裕層」「オフィスワーカー」の2ターゲット層に対する広告を実施したところ、アクセス数やカートイン数が増加。一方で、直帰率(注5)は40%に達した。
この場合、ターゲット自体は間違っていなかったと考えられる。ユーザーが商品に興味を示して商品ページまでアクセスしてもらえたからだ。ただし、商品説明が不十分とか、使用イメージが湧きにくいなどの理由から、購入を躊躇(ちゅうちょ)し、詳細情報の確認や同じブランドの他商品の検索や、購入に至る前に離脱しているものと推測される。
この例では、商品ページへの誘導後に購入への意思決定を促進する魅力的な商品画像や紹介動画などを用意することで、安定した購入率が確保できた。
類型3:ターゲットを含む戦略の変更が必要
商品の市場規模が一定程度あっても、競合企業や類似商品が多い場合、ターゲティング広告を行ってもアクセス数や商品購入数などに改善は見られないことがある。その場合、データを踏まえて戦略を軌道修正する必要が生じる。
対策としては、特定のターゲット層に対する広告を行う前に、検索キーワード設定により自社のブランドポジショニングを把握することが第1ステップになる。ShopeeなどのECサイトでは、ユーザーが実際に検索したキーワードを取得し、関心のある商品や情報を把握できる。これらのキーワードを「一般」「自社ブランド」「競合ブランド」などの属性に分類することで、各層からどのように認知・検索されているかが可視化できる(表2参照)。
例えば、他の属性と比べて自社ブランド名などからのアクセス数が多いと、ブランド認知度が高いと判断できる。検索キーワードはユーザーの関心や価値観を反映する。そのため、自社が「どの市場軸で、誰と、どのように競合しているか」を定量的に把握できるわけだ。
| キーワード属性 | 定義 | 好調な場合に考えられること |
|---|---|---|
| 一般 | 商品ジャンルやニーズを表す言葉。例えば「Japanese Tea」など、広範なカテゴリーを示す。 | ブランド認知度はまだ低い。一方で、商品の機能性や価格、訴求ポイントに競争力がある。 |
| 自社ブランド | 自社の商品名やブランド名を含む言葉。例えば、「ABC Green Tea」など、特定のブランドや商品を示す。 | ブランド認知が定着し、購入の意思決定に至る理由を備えている。 |
| 競合ブランド | 競合他社の商品名やブランド名を含む言葉。例えば、「DEF Matcha」など、競合他社のブランドや商品を示す。 | 競合の比較対象として認識されている。または、価格や品質などで優位性がある。 |
出所:「マレーシアにおける日本企業の EC 活用にかかるデジタルマーケティング実証事業」からジェトロ作成
具体的には、各キーワード属性における検索数、クリック数、購入数などの効果を分析。その後、ブランドポジショニングを踏まえて注力する属性のキーワードを設定。そのキーワードを検索したユーザーを対象にキーワード広告を配信することで、商品ページへのアクセス数の増加と購入への転換につなげていく。
特に新商品を展開する際には、ターゲット層や市場の反応がまだ明確でないことが多い。そのため、仮説を立てながら段階的にキーワード広告を配信し、ユーザーの反応を見て徐々に対象を絞り込むことが必要になる。
美容商品の自社ブランドを持つC社の例
C社は当初、競合ブランドの顧客に対して、自社商品への流入を目的にターゲティング広告や検索キーワード設定を続けた。しかし、それでも競合のキーワードからの商品ページへのアクセス数が増えなかった。
そこで、2025年2月末から一般の属性に該当するキーワードを増やしてみた。競合の顧客でない層の誘導に注力したことで、商品ページへのアクセス数は2月の3,800回から3月は6,700回に増加。パフォーマンスの改善につながった。
このように、自社が当初描いていた戦略に対してデジタルマーケティングの実施を通じて検証すること、必要に応じて軌道修正すること、が重要だ。
日本企業の成功要因と今後の展望
実証を通じて明らかになったのは、(1)企業規模や商品の市場での成熟度によって、直面する課題が異なること、(2)それぞれの課題に対応した施策の実行が不可欠なこと、だ。
とくに、明確な戦略や市場ポジショニングが定まっていないブランドでは、まずEC販売のための環境を整備する必要がある。例えば、広報素材の制作やプロモーションの計画、ブランドポジショニングといった基盤を構築した上で、特定のターゲットセグメントに向けて施策展開するのが効果的だ。
一方、商品数の多い大企業では、カテゴリー単位での戦略設計や上位モデル、関連商品のまとめ買いへの誘導といったアプローチの有無が、売り上げを左右する重要な要素になった。
各ブランドの事業フェーズや商品特性に応じ、多角的かつ柔軟にアプローチしていくことが大切だろう。
- 注1:
- 業務委託先は、利用者がデバイス(スマートフォンやタブレットなど)にインストールされたアプリケーションを通じ、一定のデータを取得できる。その結果として所有する生活者関連データ(個人情報を除く)および位置情報データなどを活用した。
- 注2:
- クリエーティブは、広告や販促活動に使用される画像、動画、テキストなどの制作物全般を意味する。商品の魅力を伝えるために重要な要素になる。
- 注3:
- 「SEO」は、検索エンジン最適化(Search Engine Optimization)の略。Googleなどの検索結果で自社サイトの表示順位を高め、自然検索による流入を増やすのが、SEO対策だ。
- 注4:
- カートインとは、ECサイト上でユーザーが商品をショッピングカートに追加する行動のこと。
- 注5:
- 直帰率は、ユーザーが最初に訪問したページだけを閲覧しサイトを離れてしまう割合のこと。

- 執筆者紹介
-
ジェトロデジタルマーケティング部ECビジネス課
梅田 健太郎(うめだ けんたろう) - 2023年、ジェトロ入構。同年から現職。

- 執筆者紹介
-
ジェトロ・クアラルンプール事務所
川本 暖乃(かわもと のんの)
2022年、ジェトロ入構。企画部情報システム課を経て、2024年9月から現職。

- 執筆者紹介
-
ジェトロ・クアラルンプール事務所
都築 佑樹(つづき ゆうき) - 2016年、ジェトロ入構。サービス産業部、岡山事務所、デジタルマーケティング部を経て、2023年11月から現職。

- 執筆者紹介
-
ジェトロデジタルマーケティング部ECビジネス課
中村 妍菲(なかむら いんふい) - 民間企業勤務を経て、2023年にジェトロ入構。






 閉じる
閉じる





