輸出・投資統計にみる対米関係の変化
米国関税措置のASEANへの影響(1)
2025年7月9日
2025年4月2日に米国のドナルド・トランプ大統領が発表した相互関税は、ASEAN各国にとって当初予想より高率で、大きな反響を呼んだ。
ASEANの多くの国・地域は外需依存度が高く、貿易相手国の通商政策や景況感の影響を受けやすい。とりわけトランプ第1次政権以降、主要国による対米輸出は拡大してきた。相互関税をはじめとする米国の関税措置は各国経済に影響を与え、ひいては各国の進出日系企業も含めたビジネス活動への影響が懸念される。
連載第1弾になる本稿では、米国の関税措置によるASEANのサプライチェーンへの影響を貿易統計から探る。併せて、日系企業への影響をジェトロの海外進出日系企業調査(以下、日系企業調査)から分析する。
米中投資によりASEANの対米輸出が拡大
第1次トランプ政権の発足(2017年)以降、米国におけるASEANからの輸入額は右肩上がりで増加。2024年には3,520億ドルと、過去最高を記録した。同年のASEANからの輸入額は、2017年比で2.1倍に増加し、2018年をピークに伸び悩む中国との差が縮まっている(図1参照)。
ASEANの中でも、最大の輸入先はベトナムだ。2024年の輸入額は1,366億ドルとなり、2017年比で2.9倍と大きく伸びた。タイ(633億ドル)やシンガポール(432億ドル)も、2017年比で2倍以上に増加。マレーシア(525億ドル)、インドネシア(281億ドル)やフィリピン(142億ドル)で、20~40%増になっている。これらASEAN主要国に比べて金額は小さいものの、ラオス(8億ドル、8.3倍)、カンボジア(126億ドル、4.1倍)も増加が顕著だった。

出所:米商務省統計に基づきジェトロ作成
米国におけるASEANからの輸入額は中長期的に拡大してきたが、特に直近半年~1年で急増した。米国大統領選挙の終盤にさしかかった2024年第3四半期に、四半期別で初めて900億ドルを超えた。2025年第1四半期には前年同期比27.9%増の984億ドルになり、1,000億ドルに肉薄する水準だった。
国別では、ベトナムからの輸入額が前年同期比36.7%増と顕著に増えたほか、マレーシアも3割以上の伸び率になった(図2参照)。
なお、相互関税の適用・90日間の停止措置が発表された2025年4月のASEANからの輸入額は前年同月比28.1%増の359億ドル。前月の363億ドルには満たなかったものの、2カ月連続で350億ドルを上回った。
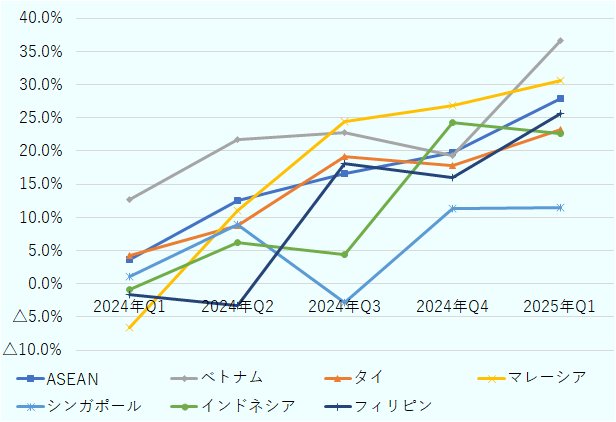
出所:図1に同じ
ASEANからの対米輸出が増加した背景には、何があるのか。中長期的には、中国や米国から、製造業の直接投資が拡大したことが大きい。
ASEAN事務局と国連貿易開発会議(UNCTAD)が発表した「ASEAN投資レポート2024![]() 」によると、中国からASEANへの直接投資は、米中貿易摩擦が始まった2018年以降、それまでの不動産・金融から、製造業中心にシフトした。2020~2023年、中国からの製造業投資は伸び率が年間平均33.3%で、急速に流入したことが分かる。この時期、米中貿易摩擦に加え、新型コロナ禍に起因する中国でのロックダウンなどにより、サプライチェーン分断の懸念が高まっていた。そのことで、中国製造業の海外展開が加速し、ASEANが中国企業の海外展開による恩恵を享受したと指摘した。
」によると、中国からASEANへの直接投資は、米中貿易摩擦が始まった2018年以降、それまでの不動産・金融から、製造業中心にシフトした。2020~2023年、中国からの製造業投資は伸び率が年間平均33.3%で、急速に流入したことが分かる。この時期、米中貿易摩擦に加え、新型コロナ禍に起因する中国でのロックダウンなどにより、サプライチェーン分断の懸念が高まっていた。そのことで、中国製造業の海外展開が加速し、ASEANが中国企業の海外展開による恩恵を享受したと指摘した。
また、米国からの投資も顕著に増えてきた。2023年には、前年の2倍に当たる740億ドルを記録し、ASEANへの最大の直接投資元になった。米国からの分野別投資で、金融が最大であることは従前から変わりないが、2016~2023年にかけての製造業投資は92億ドルになり、それまでの10年(2006~2015年)と比べて7.2倍に拡大した。
米国の関税措置次第で幅広い産業に影響か
米国による相互関税の発表はASEAN各国で予想以上に税率が高く、驚きをもって捉えられた。CMLV(カンボジア、ミャンマー、ラオス、ベトナム)に対する相互関税率は40%台と、世界的に見ても高い。タイ、インドネシア、マレーシアでも、ベース関税(一律10%)の2倍以上の税率設定だった(2025年4月3日付ビジネス短信参照)。相互関税の発表を受け、IMFや世界銀行などが軒並み世界の経済成長率見通しを下方修正した。ASEANの多くの国・地域の産業政策は、外国企業を誘致し、工業化や輸出を促進してきた経緯があり、外需依存度が高い。外需の影響を受けやすい経済構造であることに加えて、輸出先としての米国市場の重要性が高まっている中で、相互関税の発動による、輸出の減速、ひいては経済成長率の減速が懸念されている。
ASEANの中で外需依存度が最も高い国は、中継貿易拠点のシンガポールだ。世界銀行によると、同国の財・サービス輸出のGDP比は100%を大幅に上回っている。次いで高いのはベトナムで、2000年の53.9%から2023年には87.2%へと上昇し、この20年で外需依存度が急激に高まった。マレーシアやタイも6割を上回る。他方、内需主導型の経済構造となっているフィリピンやインドネシアは2割台にとどまる。
ASEAN各国の輸出統計に基づき、輸出先としての米国のシェアの推移を見てみよう。
まず、ベトナムでは、第1次トランプ政権前から米国が最大の輸出先で、対米輸出の割合は2017年に19.3%だった。それが、2024年には29.7%へと拡大した。また、タイでも、11.2%(2017年)から18.3%(2024年)に拡大した。このほか、カンボジアも対米輸出比率が約4割と高く、最大の輸出先になっている。外需依存度が高く、かつ対米輸出比率が高いベトナムやタイ、カンボジアにとって、米国が高い相互関税を発動すると、対米輸出の減退や投資の流出につながる可能性がある。国内経済への影響は大きいだろう。
米国の追加関税措置によるASEAN各国の産業への影響を分析するため、米国商務省の輸入統計から国ごとの輸出品目を確認すると、図3の通りだ。マレーシアやフィリピンをはじめ、多くの国でエレクトロニクス(HS85類)と一般機械(HS84類)のシェアが高い。
ASEAN各国の主要な対米輸出品目のうち、スマートフォン、パソコン、集積回路など半導体に関連する品目は本稿執筆時点で、相互関税の対象除外になっている。しかし、半導体に関税措置を導入することになると、影響は広範に及ぶだろう。
また、既に米国が追加関税を課している自動車・同部品(2025年4月3日付ビジネス短信参照)は、タイやインドネシアの主要輸出品目の1つだ。両国では、これらを生産する日系企業も多い。そのため、現地日系企業からはビジネスへの影響を懸念する声も出ている。
このほか、ベトナムでは衣類・履物や家具、タイではゴム製品、インドネシアでは衣類・履物やゴム製品、動植物油脂なども輸出シェアが比較的高い。相互関税は各国の幅広い産業に影響を与えるとみられる。
また、シンガポールでは、医薬品を含む医療用品が最大の輸出品目だ。医薬品は相互関税から除外されているが(本稿執筆時点)、医薬品向けの追加関税が発動すれば、影響が出る可能性もある。
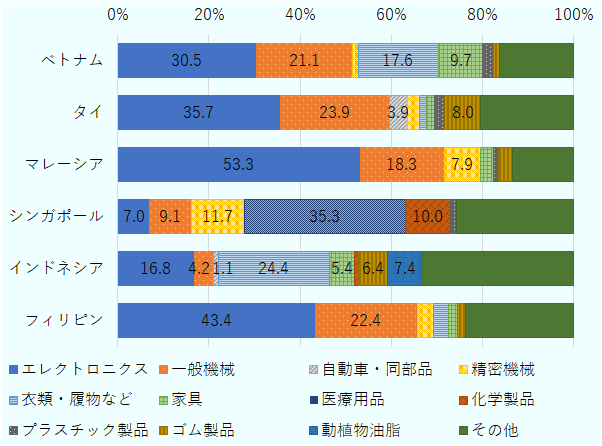
注1:米国輸入統計(2024)を基に、米国の対主要国輸入(主要品目別)をHS2桁ベースで作成。
注2:構成比が5%以上の品目(「その他」を除く)や、本文で言及している品目について、記載。
出所:図1に同じ
進出日系企業の対米輸出率は低水準も、間接影響を懸念
最後に、ASEAN各国で操業する日系企業への影響を見てみよう。
ジェトロは2024年8~9月、ASEANに拠点を置く企業を対象に、日系企業調査を実施した。そこで輸出売り上げのある企業に国・地域別の輸出比率を聞いたところ、1,700社が回答。米国向けの輸出比率は平均5.0%だった。この水準は、日本向け(46.4%)やASEAN向け(30.3%)と比べるとかなり低い。ただし、「輸送機器・部品」「電気・電子機器・同部品」「ゴム・窯業・土石」などの業種では、全体平均を上回っている(米国向けの輸出比率8~14%)。
もっとも、米国の関税措置の影響を直接受けるASEAN進出日系企業の規模を把握するには、売上高に占める輸出比率が高い企業の米国向け輸出について確認する必要がある。
1,700社のうち、売上高に占める輸出比率が50%以上の日系企業は737社あった。このうち94.2%の企業で、対米輸出比率は25%未満にとどまった。こうしてみると、米国の関税措置が在ASEAN日系企業に与える直接の影響は、限定的に思える。他方、全体の3.1%(23社)では、米国向け輸出比率が50%以上に上る。中には、100%の企業もあった。それ以外にも、取引先を経由して米国へ輸出するケースもある。米国が主要販路になっている日系企業は、先述の数値以上にありそうだ。このことから、ビジネスへの影響や懸念も、多岐にわたると想定できる。
米国による追加関税措置の状況は、刻々と変化している。相互関税の適用停止期限の延長なども報じられる中で、今後の動きを予見することは容易でない。しかし、既に適用されている関税措置によって影響を受けている対米輸出企業は現にある。
加えて、米国の措置だけでなく、中国をはじめ諸外国の報復措置がビジネスに影響する可能性もある。また、ASEAN各国で国内販売する企業では、米中対立の激化で中国から安価な製品が流入する可能性に、警戒感が高まっている。その場合、国内産業への影響がさらに大きくなるだろう。
米国関税措置のASEANへの影響

- 執筆者紹介
-
ジェトロ調査部アジア大洋州課 リサーチ・マネージャー
山口 あづ希(やまぐち あづき) - 2015年、ジェトロ入構。農林水産・食品部農林水産・食品課(2015~2018年)、ジェトロ・ビエンチャン事務所(2018~2019年)を経て現職




 閉じる
閉じる






