日本の製造業はGDPの約2割を占め、特に自動車等の部素材は世界的競争力を誇っています。デジタル化と脱炭素化により、製造業全体としてのさらなる成長が期待されており、外資系企業との連携が期待されます。
製造業
魅力的な注目市場分野

(1)半導体:政府により拡充される強力な投資支援
日本の半導体出荷額は2020年から2022年にかけて急激に増加しています37。これに伴い、日本政府は国内で半導体を生産する企業の合計売上高を2030年までに990.9億米ドル*(15兆円)以上とすることを目指しており、さらに同年までに792.7億米ドル*(12兆円)規模の官民による追加投資を予定しています38。
2023年に経済産業省は情報処理技術や情報通信技術等の進展、新型コロナウイルス感染拡大やロシアによるウクライナ侵攻等の社会情勢を踏まえて、「半導体・デジタル産業戦略」を改定しました。改定された同戦略ではIoT用半導体生産基盤の強化、日米連携による次世代半導体技術の確立、グローバル連携による将来技術の研究開発の3つを軸に定めています。グローバル連携による研究開発の一環として、「次世代半導体プロジェクト」が策定され、国際的な研究機関や企業との連携を通じて、先端設計や先端装置・素材の要素技術に関するオープンな研究開発拠点と将来の量産体制の立ち上げを見据えた量産製造拠点の2拠点の立ち上げが計画されています39。
さらに、日本政府はグローバル連携を促進すると同時に、外資系企業への投資促進施策として先端半導体の生産施設の設備および生産を行う計画に対して支援を行っています。2023年10月時点で最大助成額は合計約51.5億米ドル*(7,800億円)に及び、支援対象の関連事業者にはTSMC(台湾)やWestern Digital(米国)、Micron Technology(米国)等を親会社とする日本拠点も含まれています。TSMCの熊本県進出を起点とした電子デバイス産業全体の経済効果は10年間で約455.8億米ドル*(6.9兆円)にも上ると試算されており、その影響力の大きさがうかがえます40。また、TSMCに加えて、半導体製造大手PSMC(台湾)が宮城県に半導体製造施設を設立する際にも、経済産業省はPSMCからの生産拠点の整備や人材育成に関する要望を受け止め、支援を検討する考えを示しています41。
加えて、日本政府は次世代半導体の短TAT量産基盤体制の構築実現に向けたプロジェクトを実施しています。同プロジェクトにおいて、政府は先端設計や先端装置・素材の要素技術に関する研究開発拠点(LSTC、Leading-edge Semiconductor Technology Center)や将来の量産体制の確立を見据えた量産製造拠点(Rapidus)の立ち上げを行っており、国内に限らず海外の学術研究機関や企業と連携し研究開発を実施しています。例えば、日本のRapidusはIBM(米国)やImec(ベルギー)、Tenstorrent(カナダ)との共同開発パートナーシップや協力覚書(MOC)を締結しています。このように、今後も海外学術研究機関・企業との協働が見込まれます42。
上記の技術的な連携支援に加えて、日本政府はTSMC等の海外大手半導体企業の誘致をさらに強化し、国内半導体サプライチェーンの強化に向けた取り組みを一層推進しています。2023年5月、岸田文雄首相(当時)は複数の海外半導体大手幹部と意見交換を行い、日本国内の半導体産業活性化に向けて海外大手半導体企業による日本国内への投資を奨励し、半導体産業への支援ならびにグローバルサプライチェーン安定化への貢献の意向を示しました43。
日本の半導体市場への参入を支援する政府の政策に対応して、複数の外資系企業が新工場設立の計画を開始しています。Micron Technologyは広島県東広島市の生産拠点に最大33億米ドル*(5,000億円)の投資計画を発表しました44。PSMCとSBIホールディングス(日本)は仙台での半導体生産施設の設立に向けて提携を締結しています45。また、半導体設計事業者のIC LAYOUT DESIGN TECHNOLOGY CORPORATION(台湾)は神奈川県による企業誘致施策「セレクト神奈川NEXT」を通して県内に日本法人ゴールデンレイアウトテクノロジージャパンを設立しました46。
このように日本政府は海外からの日本への投資を積極的に促進し、半導体市場規模拡大に向けてさまざまなインセンティブを提供しています。これにより、海外の半導体関連事業者が日本に生産拠点を開設する絶好の機会となっています。
(2)産業用ロボット:労働人口減少により需要拡大
産業用ロボット市場において、世界市場シェア46%を誇る日本は、同製品の一大生産国といえます。2022年の日本における産業ロボット設置台数は50,413台(前年比9%増)に達し、新型コロナウイルス感染拡大以前の2019年の49,908台を上回る台数を記録しています47。
産業用ロボットの主要国としての日本の優位性をさらに強化するため、日本政府は2020年にムーンショット目標3のマイルストーンを設定し、2050年までにAIとロボットの共進化により、自ら学習・行動し人と共生するロボットの実現に向けた研究開発への支援を実施しています(図表10)。産業用ロボットは従来、製造業における自動化と生産性に焦点を当てていましたが、ムーンショット目標3の下では、技術とアイデアの融合を促進し、産業用ロボットの能力、安全性、適応性を向上させることを目指します。
図表10「ムーンショット目標3におけるマイルストーン」
| 年 | 目標 |
|---|---|
| 2023 | 人間主導でのAIロボットの技術開発、機械学習を進めるための要素技術開発。 |
| 2025 | これまでに学習した情報をもとにロボットの振舞いを生成し、結果を学習するAIロボットを実現。 |
| 2030 | 人間、AI、ロボットと相互作用しながら共進化し、自ら学習、行動、修復を行うAIロボットを実現。 |
| 2050 | AIとロボットの共進化により、自ら学習・行動し人と共生するロボットを実現。 |
また、日本では少子高齢化の進行により、製造業における労働者不足が深刻化しており49、工場や生産施設等での人間労働者に代わるAIを活用した産業用ロボットの需要が拡大すると予想されています。この背景から産業用ロボット分野で事業を展開する外国企業にとっては日本市場への参入機会が見込まれると考えられます。
産業用ロボットの需要に応じて日本市場に参入し、成功している外資系企業の代表的な実例として、ABB(スイス)が挙げられます。ロボティクス企業であるABBは日本に約600人の従業員と13拠点の販売・サービスネットワークを有し50、川崎重工業(日本)と協働型双腕ロボットにおける知識の共有やロボット活用の促進で協業した実績があります51。
また、製造業における生産ラインの可視化に応用されているデジタルツインの導入に関して、日本企業と外資系企業の提携が進んでいます。例えば、川崎重工業とMicrosoft(米国)による提携では、デジタルツインを活用した遠隔地からのロボット操作が実現しています52。これらの事例のように、メタバース技術等を用いたデジタルツインプラットフォームを通じて、製造ラインのシミュレーション機能を活用する外資系企業の事例も見られます。
日本政府は、産業用ロボット分野への投資を積極的に奨励しており、今後も前述のような外資系企業による日本企業との協業連携の成功事例が増えることが期待されます。
(3)自動車産業:政府施策の後押しにより進む脱炭素化と自動運転
日本の自動車産業は、製造業を牽引する基幹産業です。2022年の日本における四輪車生産台数は784万台と世界3位であり、日本は中国に次ぐアジア太平洋地域の主要な四輪車生産拠点として位置付けられています53。また、2021年の自動車製造業の製造品出荷額は、前年比5.5%増の約3,725.7億米ドル*(56.4兆円)であり、全製造業の製造品出荷額の17.1%を占めています。さらに、2021年度の自動車製造の設備投資額は約92.5億米ドル*(1.4兆円)であり、研究開発費は約237.8億米ドル*(3.6兆円)に上ります。また、自動車関連産業の就業人口は554万人(全人口の約8%)であり、自動車産業は日本経済に多大な影響を与えているといえます。貿易額に関しては、新型コロナウイルス感染拡大や円安の影響を受けたものの、2021年以降輸出入総額ともに増加傾向にあり、コロナ禍以前を上回っています(図表11)。
図表11「自動車の輸出入総額推移」

※ F.O.B.価格=本船渡し価格、C.I.F.価格=運賃、保険料込み価格
〔出所〕日本自動車工業会のデータを基にジェトロ作成54
日本のさらなる優位性の確保に向け、日本政府は自動車産業における脱炭素化や自動運転の促進に積極的に取り組んでいます。2021年6月、政府は自動車産業の脱炭素化に向けて「2050年カーボンニュートラルに伴うグリーン成長戦略」を改定し、自動車の電動化を促進する戦略を掲げました。同戦略の一環として、公共用の急速充電器3万基を含む充電インフラを15万基設置する計画があり、遅くとも2030年までにガソリン車並みの利便性を実現することを目指しています。また、充電インフラの普及を加速する施策として、2030年までに新築集合住宅での電気自動車等用充電設備を10~20万口設置する予定です55。
自動運転については、OEMメーカーがレベル3(条件付自動運転)の開発を進めており、政府はレベル4(特定条件下における完全自動運転)の導入に向けた取り組みを開始しています。特に自動運転は高齢化問題や公共交通機関の未整備、タクシー運転手の不足などの理由から、都心部よりも地方でのニーズが高く、地方の課題解決に向けた自動運転サービスの展開が目指されています。加えて、日本では地方での5Gネットワークが普及しており、日本市場は都市部に限らず地方での自動運転の普及が実現可能な環境にあると推定されます56。その一例として、経済産業省と国土交通省が共同で推進する自動運転レベル4等先進モビリティサービス研究開発・社会実装プロジェクト「RoAD to the L4」が挙げられます。同プロジェクトでは、2025年度までに自動運転に対応可能なエリアと車両を拡大し、50カ所で自動運転サービスを展開することを目標としています。対象のエリアは都市部に限定せず、福井県永平寺町等の地方においても自動運転移動サービスが展開されています57。2024年2月時点で、2025年度には都市部及び地方を含む26都道府県で自動運転移動サービスの実現が見込まれています58。 このように、脱炭素化と自動運転は日本の自動車産業の代表的なトレンドであり、政府が積極的に後押ししています。これにより、脱炭素化や自動運転に特化した外国企業が日本市場に参入しやすくなると推測されます。
(4)宇宙産業:外国企業との連携が増加中
日本の宇宙産業は2020年時点で264.2億米ドル*(4兆円)規模であり59、2021年の航空宇宙工業生産額はEUを除いて主要国の中で6位となりました60。内閣府が掲げる宇宙基本計画の下、2030年までに宇宙産業の市場規模を528.5億米ドル*(8兆円)に拡大することを目指し、官民連携により推進しています61。
日本政府は、国内の宇宙産業の強化を図るとともに、国際競争力を確保するために海外の組織や民間企業との連携に注力しています。その施策の1つとして、経済産業省は日本の中小企業と外国企業をマッチングさせ、商品開発や新規取引を支援する取り組みを行っています62。また、2018年に立ち上げられたSpace Port Japanは、日本におけるスペースポート(宇宙港)の開港を目指し、国内外の関連企業や団体との情報交換・連携とビジネス機会の創出を主要活動としています63。
さらに、日本と海外間の民間宇宙連携も活発に進んでいます。代表的な事例として、アジア最大の衛星通信事業者であるスカパーJSAT(日本)と大手通信・宇宙探査企業Thales Alenia Space(フランス)による新世代ソフトウェア定義衛星JSAT-31の構築契約が挙げられます64。
このように、政府の後押しや海外衛星通信事業者等の外資系企業との連携により、日本の宇宙産業への注目が高まっており、同市場は今後さらに成長することが期待されます。
-
*
日銀換算レート 1米ドル 151.38円で計算(2024年4月1日時点)
脚注
- 総務省「情報通信白書令和5年版」(「第4章第5節 23. 日本の半導体市場 (出荷額)の推移」)
- 経済産業省「半導体・デジタル産業戦略の現状と今後」(pp.163,175)。
- 前掲注38(pp.4,7,42)
- 前掲注38(pp.36,37)
- 河北新報社「宮城・村井嘉浩県知事が経済産業省に半導体拠点整備について財政支援を要望」
- 前掲注38(pp.42,43,49)
- ジェトロ「岸田首相、海外半導体大手幹部と面談、日本への投資拡大を呼びかけ」
- Micron Technology「マイクロン、日本にEUV技術を導入し、次世代メモリの製造を推進」
- SBIホールディングス「日本国内での半導体ファウンドリ建設予定地決定のお知らせ」
- 神奈川県 「車載ソフトウェア開発及び半導体設計を行う外国企業2社が県内に進出!」
- 国際ロボット連盟「日本のロボット設置台数 9%増 ― 国際ロボット連盟(IFR)レポート」, p.1
- 科学技術振興機構「ムーンショット目標『2050年までに、AIとロボットの共進化により、自ら学習・行動し人と共生するロボットを実現』プログラムの進捗状況(報告)」(p.7)
- 日銀短観「短観(概要)―2024年6月―」(p.6)
- ABB 公式ウェブサイト
- 川崎重工業「川崎重工と ABB、協働ロボット分野における協業に合意」
- 川崎重工業「Kawasaki DXが『Microsoft Build 2022』で紹介されました」
- 日本自動車工業会「世界生産・販売・保有・普及率・輸出」
- 日本自動車工業会「基幹産業としての自動車製造業」
- 経済産業省「新築集合住宅における電気自動車等用充電設備の積極的な設置について」
- ジェトロ「GVCの変化がもたらす影響 【自動運転×自動車】」(p.15)
- RoAD to the L4 公式ウェブサイト
- RoAD to the L4「RoAD to the L4プロジェクトの全体像 -レベル4自動運転社会実装の取り組み-」(p.26)
- 内閣府「宇宙基本計画の概要」
- 日本航空宇宙工業会「2024 はばたく日本の航空宇宙工業」(p.4)
- 前掲注59
- 経済産業省等「令和6年度『経産省×中⼩機構 共同開催 航空宇宙産業ビジネスマッチング』事業のご案内」(pp.5-8)
- Space Port Japan 公式ウェブサイト
- Thales Alenia Space「SKY Perfect JSAT selects Thales Alenia Space to build a new cutting-edge software-defined satellite “JSAT-31”」
製造業レポート
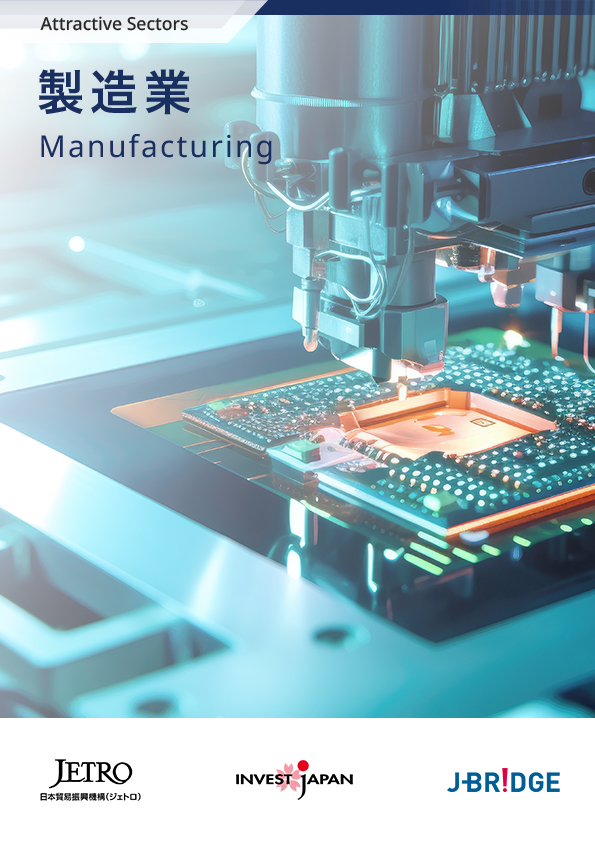
ウェブページでご紹介している内容を1つにまとめた資料を無料でダウンロードできます。フォームにご入力いただくだけで、日本市場における有望産業情報を手に入れることができます。ぜひダウンロードいただき、みなさまのビジネスの成功に役立ててください。
メールマガジン登録
このメールニュースでは、最新の投資環境情報やジェトロが支援した外国・外資系企業の動向等を紹介します。内容は自治体によるセミナー、インセンティブ、進出事例、規制緩和トピック、産業情報などです。
お問い合わせ
フォームでのお問い合わせ
ジェトロはみなさまの日本進出・日本国内での事業拡大を全力でサポートします。以下のフォームからお気軽にお問い合わせください。
お問い合わせフォームお電話でのお問い合わせ
-
- 拠点設立・事業拡大のご相談:
- 03-3582-4684
-
- 自治体向けサポート:
- 03-3582-5234
-
- その他の対日投資に関するお問い合わせ:
- 03-3582-5571
受付時間
平日9時00分~12時00分/13時00分~17時00分
(土日、祝祭日・年末年始を除く)

























