「香港知財取引調査(技術取引・共同研究編)」を読み解く
2025年9月24日
ジェトロ・香港事務所は今般、「香港知財取引調査(技術取引・共同研究編)」(以下、本マニュアル)を作成した。香港での技術取引における強み、契約交渉や締結の流れ、契約締結後の留意点などをまとめた。日本企業や大学が、香港企業やスタートアップ、大学などとの技術取引や共同研究などを検討する際に参考にしていただきたい。
香港で近年締結された技術契約(注1)として、例えば、2022年に香港理工大学(PolyU)が、大手情報通信プロバイダーであるNEC香港有限公司(NECHK)と提携し、高齢者在宅ケア向けにインテリジェントソーシャルロボットを共同で導入した事例が挙げられる。また、2022年11月に中国・深セン市で開催された第24回中国ハイテクフェア・クリーンエネルギー博覧会で、最新の日本製のプロ仕様低温予混合反応制御圧縮着火(RCCI-Pro)技術とHHFE-DGシリーズ水素複合燃焼エンジンシステムが紹介され、香港企業の辰隆科技發展に独占的にライセンス供与されることが明らかになった。
香港のイノベーションと技術研究における強みとして、質の高い研究機関を有することが挙げられる。例えば、クアクアレリ・シモンズ(QS)やタイムズ・ハイヤー・エデュケーション(THE)などの世界大学ランキングにおいてトップ50にランクインする香港中文大学と香港大学の医学部では、専門的で評判の高い臨床試験センターを備えている。また、香港には、世界的な研究協力の拠点としての発展を目指す政府の主要な取り組みとしてInnoHK(注2)が存在する。これによって、健康関連技術、人工知能(AI)およびロボット技術、持続可能な開発とエネルギーの分野で、様々な世界クラスの研究クラスターを設立した。現在までに、InnoHKは11の経済圏から20以上のトップ大学や科学研究機関を含む、グローバル化された人材の膨大なプールを集め、地元の大学と協力して香港サイエンスパーク(HKSP)に研究所を設立し、地元の大学と協力して研究開発を行っている。
本マニュアルは、「第1章 技術取引にとって魅力的なビジネス環境としての香港」「第2章 契約の交渉と締結」「第3章 契約後段階」の3章と付録で構成されている。第1章では、技術開発における香港の強みや法的環境をはじめ、日本企業のパートナー候補となる事例の紹介、香港政府が主催する技術取引につながり得るフェアや見本市などの知的財産権(IPR)取引プラットフォーム、香港市場参入前に検討すべきIPR関連のポイントについて解説する。第2章では、技術契約の交渉から締結までのプロセスや、契約締結前のデューディリジェンス(注3)、交渉の要点について説明する。第3章では、契約締結後の品質管理と紛争解決方法について紹介する。最後に付録として、秘密保持契約(NDA)、概念実証(PoC)、共同研究開発、ライセンス、技術譲渡、AIおよびソフトウェア使用の6つの場合に分けて契約書のサンプルを掲載している。
本稿では、主に第2章、第3章について解説する。その他の章や詳細については、ジェトロ「知的財産に関する情報」(香港)から、マニュアル〔英語原本(1.6MB)![]() 、日本語訳(1.6MB)
、日本語訳(1.6MB)![]() 〕を参照いただきたい。
〕を参照いただきたい。
香港での技術契約の知財取引は大きなポテンシャルを秘めている
第2章と第3章の概要を紹介する前に、本マニュアルを作成するに至った背景について簡単に説明したい。
中国国務院が2021年10月に公表した「『第14次5カ年(2021~2025年)規画』国家知的財産権保護および運用規画」で、香港の知的財産取引センターとしての発展を支持する方針を示した。これを受けて、香港政府も施政報告において知的財産取引センターとしての発展を推進していくことを表明している。さらに、2025年3月に開幕した第14期全国人民代表大会第3回会議で、香港の李家超(ジョン・リー)行政長官は、「香港政府は革新的な考え方で北部都会区と河套深セン・香港科学技術イノベーション協力区の発展を進め、国際イノベーション・テクノロジーセンターの開発を加速させる」と発表した。香港が国際的なイノベーション・テクノロジーハブへと発展できるのは、中国と世界の両方の利点が収束する世界で唯一の都市という独自の立場にあるからだとする。
香港は、国際性に富む高度な人材、金融・貿易における伝統的な優位性、堅牢な法律・紛争解決サービスを有しており、日本企業にとってIPR取引に大きなポテンシャルを秘める市場と言えるだろう。しかし、これまで、香港における日本企業のパートナーとなりうる連携先の探し方や、契約の際の連携先との交渉方法、各種類契約における留意点、契約締結後の品質コントロール、契約交渉前から締結後までの留意点について、日本語でまとめた情報は十分ではなかった。そこで、ジェトロ香港が特許庁からの委託を受け、日本企業が香港で技術契約や共同研究をする際に、参考にできるよう、本マニュアルを作成した。
契約の交渉と締結(第2章)
(1)交渉から締結までのプロセス
一般的なライセンス契約プロセスは次のとおり。ただし、技術契約は、各当事者の特定のニーズに合わせてケースバイケースで作成する必要がある点に留意いただきたい。
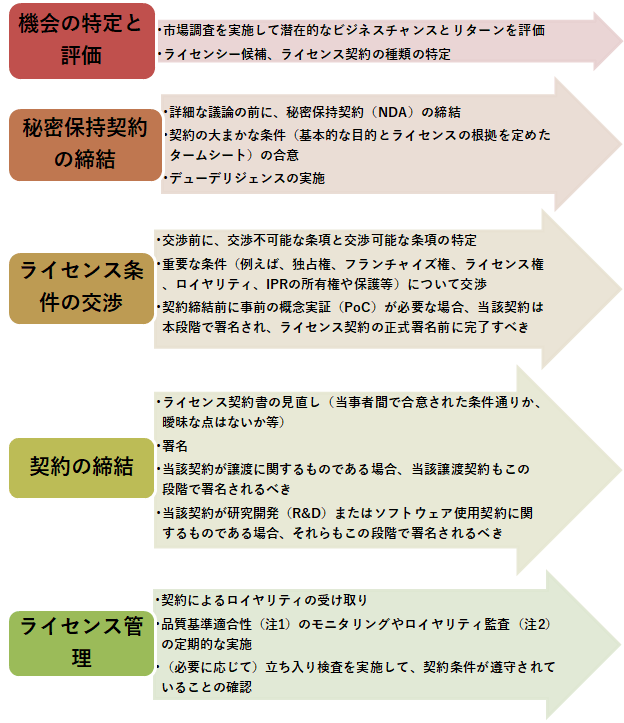
注1:ライセンスに基づいて製造された製品がライセンサーの要求に合致した品質を備えているか。
注2:IPR所有者が、ライセンスに基づいて支払われるべき適切な金額をライセンサーが受け取っているかどうかを確認および判断するための監査。
出所:本マニュアル(33ページ)
(2)契約締結前のデューディリジェンス
デューディリジェンスの対象となる分野には、例えば次のようなものがある。
- 財務デューディリジェンス:相手方の経営状態などに関する調査
- コマーシャルデューディリジェンス:相手方のビジネス上の評判などや、ビジネス市場(競合状況など)に関する調査
- オペレーショナルデューディリジェンス:相手方が事業運営する上での背景に関する調査
- 法律関連:相手方の権利や義務に影響を及ぼす可能性のある法的リスク(例えば、既存または差し迫った請求や訴訟など)、およびIPRに関する調査
デューディリジェンス調査の範囲に関する標準的な要件は定められてない。企業は、個々の取引をケースバイケースで検討する必要がある。
また、デューディリジェンスに必要な期間は、案件の規模や複雑さによって異なる。通常、中小企業の単純な取引の場合、デューディリジェンス期間は30日から60日程度だ。期間は、入手可能な情報量、対応時間、相手方とのコミュニケーションによって短縮または延長される可能性がある。
香港には、法律事務所や会計事務所など、多くのデューディリジェンス・サービス・プロバイダーがある。通常、契約の両当事者は、デューディリジェンス調査に必要な情報と文書を相互に開示し、提供する。しかし、不正行為の疑いなど、追加のデューディリジェンスが必要な場合は、証拠を得るために覆面捜査などを行うために調査会社に依頼する必要があるかもしれない。
(3)交渉の要点
ライセンスの条件は自由に交渉できるが、当事者間の期待は当然異なるものとなる。ライセンサー(知的財産権者)は限られたリスクで最大の利益を得たいと考え、ライセンシー(知的財産利用者)はライセンサーからの介入を制限した柔軟で広範な権利を望む。
技術契約で一般的に見られる主な条件を表に示している。契約交渉や最終決定の際の参考としていただきたい。
表:技術契約で一般的に見られる主な条件と交渉の要点(—は記載なし)
| 条項 | コメント | 当事者間でよく起きる争い |
|---|---|---|
| IPRの説明とライセンスの範囲 | ライセンス範囲は、使用範囲や権原に関する保証範囲(非侵害を含む)に影響を及ぼし、ひいてはライセンス契約の将来の執行方法に影響を与える可能性があるため、詳細かつ正確に記述すべきである。 | ライセンサー(特許権者)はより詳細な記述を望み、ライセンシー(特許権を利用する者)は大まかな記述を望む。曖昧さは争いにつながり、権原 に関する保証範囲や契約の効力に影響を及ぼす可能性がある。 |
| 独占性と譲渡可能性 | ライセンスには、独占的ライセンスと非独占的ライセンスがあり、譲渡可能な場合と譲渡不可能な場合がある。当事者は、IPRが適用される市場での競争などに照らして、各種の影響を慎重に検討すべきである。非独占的ライセンスは(複数のライセンシーにライセンスを付与できるため)収入増加につながる可能性があり、異なるライセンシー間の競争は商品の競争につながり、商品の品質を高める可能性がある。 |
ライセンシーは、事業や市場の需要に影響を与える他のライセンシーとの競争を避けるため、独占的ライセンスを望む。 一方、ライセンサーは、他者へのライセンス許諾の選択肢を維持するため、または商品を自ら販売するために、非独占的ライセンスを好む。これらの選択肢はどちらも、ライセンサーの売上と収益の増加につながる可能性がある。 |
| 販売地域と取引チャネル |
ライセンサーは販売地域を特定し、ライセンシーがライセンス地域外の他者に製品を販売することを禁止する適切な条項を盛り込むべきである。 ライセンスを特定のチャネルにのみ付与するのか、それともすべてのチャネルに付与するのかは、ライセンサーの潜在的収益に直接影響を与えるだけでなく、異なる市場でのIPRの使用にも影響を与える。 |
ライセンサーは自ら開拓するため特定の販売地域やチャネルを残しておくことを望むが、ライセンシーはすべての販売地域やチャネルを自ら開拓する自由と、ライセンスを受けた地域内のいかなる相手にも販売する完全な自由を望む。 |
| 期間と更新 | 期間が短いと製品の売上高が少なくなり、ライセンサーの潜在的収益が減少する可能性がある。しかし、自動更新の長期契約では、製品の品質基準の監視が不十分になる恐れがある。ブランド所有者は、業績目標を達成するための十分な時間を確保すると同時に、ライセンス要件の遵守状況を監視できるよう、両者のバランスを図るべきである。 | ライセンサーは契約を更新する前にライセンシーの遵守状況を確認できるよう、自動更新のない短期契約を望むが、ライセンシーは既存の条件に変更を加えない自動更新を望む。 |
| ロイヤルティと支払い |
ロイヤリティにはさまざまな計算方法がある。商標ライセンス契約の対価として最も一般的なのは、契約一時金の支払いと、ソフトウェアや技術などの継続使用に対する年間維持費の支払いである。 ライセンサーがそもそもライセンスを付与する主な目的はロイヤリティの徴収であるため、この条項の詳細については慎重に交渉すべきである。純売上高の計算から控除できる項目と支払うべきロイヤリティは、両当事者の合意次第である。 |
ライセンサーは適切な財務報告を伴う定期的な支払いを望むが、ライセンシーは最小限の報告要件でより長い支払い間隔を望む。 |
| 支払い条件と報告条件 |
両当事者は、報告書と支払いを提出するための合意された形式、手順、および定期的な期間について合意する必要がある。料金を計算するための適切な手順(必要な場合)と払い戻しに関する取り決めも事前に合意する。 ライセンサーは、ライセンサーの利益を保護するために、受諾後も報告書に異議を申し立てる権利を常に保持する。これは、ライセンサーが監査上の欠陥を発見した場合に特に重要になる。 |
ライセンサーは適切な財務報告を伴う定期的な支払いを好むが、実施権者は最小限の報告要件でより長い支払い間隔を好む。 |
| 支払いと報告の期間 |
両当事者は、売上高報告書の提出とロイヤリティの支払いについて、形式、手続き、標準的期間の点で合意する必要がある。料金計算の適切な手続きや払い戻しの制度についても、事前に合意しておくべきである。 ライセンサーは、ライセンサーの利益を守るため、受領後であってもロイヤリティ報告書に異議を申し立てる権利を常に留保すべきである。これは、ライセンサーが監査上の不備を発見した場合に特に重要になる。 |
ライセンシーは、ロイヤリティ報告書が受理された後、ライセンサーによる異議申し立てを認めないことを望む。このような場合には、ライセンシー側で追加の管理コストが発生する可能性がある。 一方、ライセンサーは、ライセンシーの権利を考慮せず、自らの利益のみの観点から、知的財産権を維持または放棄する絶対的な裁量を保持することを好む場合がある。 |
| 監査権 | これは、ライセンサーが生産・販売記録や会計帳簿などを検査・監査する権利を指す。これにより、ライセンサーは記録が正確であることや、適切に計算されたロイヤリティの支払いを受けていることを確認できるため、この条項は重要である。 | ライセンサーは、ライセンサーの都合の良い時に監査を行う完全な自由を望むが、ライセンシーは、ライセンサーによるこの権利の行使を限られた回数に制限し、合理的な通知がなされることを望む。 |
| 契約の解除、および契約解除または満了の効果 | この条項には、ライセンサーやいずれかの当事者が契約を解除する権利とその根拠、および解除の効果(ライセンシーはIPRの使用を直ちに中止すること、未払い金をすべて支払うこと、最終的なロイヤリティ報告書を提出することなど)が含まれる。 | ライセンサーは、実際の違反か差し迫った違反か予想される違反かを問わず、違反があった場合の契約解除について幅広い裁量を望むが、ライセンシーは、契約解除が重大な違反にのみ適用されることを望む。 |
| 条項 | コメント | 当事者間でよく起きる争い |
|---|---|---|
| ライセンスの登録 |
ライセンスの登録要件に関する法律は、法域によって異なる。一部の法域では、ライセンスの事前登録が必要であり、さもなければ、ライセンシーは第三者に対する賠償などの権利を失う。 したがって、ライセンサーは、ライセンス登録が必須かどうか、必須の場合はどの当事者が登録の責任を負うかについて、関連契約書で明確に定めておくべきである。 |
— |
| IPRの登録と維持 | これは、IPRの登録、保護、維持を意味し、ライセンサーがIPRを保護するために申請を継続的に行うことを指す。 |
ライセンシーはライセンサーに対し、すべての申請を入念に行い、IPRを確保および維持することで、独占権を保護すると約束するよう求めることができる。 一方、ライセンサーは、ライセンシーの権利を考慮せず、自らの利益のみを基準として知的財産権を維持するか放棄するかについて絶対的な裁量権を保持することを好む場合がある。 |
| IPRの行使 | 当事者にとっては、ライセンシーによるIPR行使をコントロールする完全な権利を含め、IPRに関する権利を維持することが重要である。ライセンサーは、そのような行使手続きが速やかに通知されるようにするとともに、自らの名においてかかる手続きを擁護または推進するか、ライセンシーにそうするよう指示できるような完全な裁量権を確保すべきである。 | 手続きの実施や、それに関する費用をどちらが負担するかについて、当事者の意見が異なることがある。手続きの混乱や遅延を避けるため、ライセンス契約を締結する前にこの条件について合意しておくことが賢明である。 |
| 条項 | コメント | 当事者間でよく起きる争い |
|---|---|---|
| ライセンサーの保証 | これは、ライセンス化された財産に関するライセンサーの約束を指す。 | ライセンシーはライセンサーに対し、第三者のIPRの無効または侵害があった場合の保証を要求することができる。 |
| ライセンシーの保証 | これは、取引に関するライセンシーの約束を指す。 | ライセンサーはライセンシーに対し、合意された範囲外でのIPRの使用など、製造物責任から生じるすべての責任を負うよう要求することができる。 |
| 補償 | これは、技術が第三者の権利を侵害していることが判明した場合の、各当事者の将来の義務に関するものである。 |
ライセンサーは通常、ライセンシーの違反によって被るすべての損失と損害を、ライセンシーが補償するよう要求することができる。 一方、ライセンシーは、責任のリスクを軽減または制限するために、補償義務をできるだけ少なくすることを好む。 |
| 条項 | コメント | 当事者間でよく起きる争い |
|---|---|---|
| 競業避止 | これは、いずれかの当事者の利益を損なう可能性のある、競争目的での機密情報の使用に関する制限事項に関するものである。 | 受領側が、開示側の事業を奪うなど、自己の利益のために機密情報を使用し、開示側の利益を損なう可能性がある場合、意見の相違が生じる可能性がある。 |
| 条項 | コメント | 当事者間でよく起きる争い |
|---|---|---|
| 概念実証が成功したかどうかの確認メカニズム | 概念実証が成功したかどうかを判断するための明確なメカニズムまたは基準は、当事者にとって重要である。これはまた、当事者が当該概念実証のさらなる実施のためにさらなる契約を締結する義務があるかどうかに影響を与える可能性がある。 | 概念実証の結果、さらなる交渉とさらなる契約の締結の基準を満たしているかどうかについて、意見の相違が生じる可能性がある。 |
| 条項 | コメント | 当事者間でよく起きる争い |
|---|---|---|
| 共同開発および単独開発された新技術のIPR所有権 |
新しく開発されたIPRを共同所有とみなすか、単独所有とみなすかを決定するための明確なメカニズムを設定する必要がある。 新たな知的財産権が共同で創出される場合、当事者は各当事者の関与の度合いに応じて所有権をどのように配分すべきかを決定する仕組みについて合意すべきである。新たな知的財産権が独立して創出される場合、当事者は独立した創出を証明する仕組み(証拠によって裏付けられるもの)について合意し、紛争を回避すべきである。 |
特定の新規IPRが各当事者のバックグラウンドIPRを利用したため共同所有とすべきか、一方の当事者のみが独自に作成したかについて、意見の相違が生じる可能性がある。 |
| 条項 | コメント | 当事者間でよく起きる争い |
|---|---|---|
| 譲渡および引き渡し方法 | 特定の技術またはIPRを譲受人に譲渡および提供する方法について明確なメカニズムを設定する必要がある。 | 明確なメカニズムが設定されていない場合、特定のIPRの権原と所有権が正常に移転されたかどうかについて、例えば、オンラインプラットフォームの場合はアクセスとパスワードが適切に渡されたかどうか、物理的な製品または機械の場合は手渡しされるかどうかなど、意見の相違が生じる可能性がある。 |
| 条項 | コメント | 当事者間でよく起きる争い |
|---|---|---|
| 成果物に対する権利 | 成果物に対する所有権は、最初から明確に決定しておく必要がある。 | 顧客(ライセンシー)は、AIソフトウェアを使用して作成された成果物の所有権を保持したい場合があるが、プロバイダー(ライセンサー)はすべての所有権を保持したい場合がある。 |
| サードパーティ製ソフトウェアの責任制限 | 成果物にオープンソースソフトウェアまたはサードパーティ製ソフトウェアが組み込まれるかどうか、および関連するIPRまたはデータセキュリティリスクを考慮する必要がある。これは、上記の「保証と救済措置」のセクションにも関連する。 | 顧客(ライセンシー)は、バイアスなどに関連するリスクを軽減する表明と保証を含めたいと思う一方で、プロバイダー(ライセンサー)は制限とリスクに関する免責事項を含めたいと思うだろう。 |
| トレーニングデータ | 顧客データがトレーニング目的で使用できるかどうかについての明確な決定を契約に記録する必要がある。 | 顧客(ライセンシー)は、自社のデータがAIのトレーニングに使用されるのを防ぎたい場合がある(そのAIは競合他社に提供される可能性がある)が、プロバイダー(ライセンサー)はできるだけ多くのデータをAIのトレーニングに組み込みたい場合がある。 |
| 条項 | コメント | 当事者間でよく起きる争い |
|---|---|---|
| 言語 | 当事者が2つの言語で契約を締結するのは珍しいことではない。しかし、不明瞭な場合にどちらの言語が優先されるかを明記するよう注意すべきである。 | 1つの契約書内で異なる言語を翻訳することは、その解釈に関して争いを引き起こす恐れがある。 |
| 準拠法と法域 | 契約を統治する法律を明確にすることが重要である。訴訟が発生した場合、裁判所はこの条項を尊重し、当事者間で合意された特定の法律を使用する。この条項は、当事者が異なる法域に属する場合に特に重要である。 | 両当事者とも、特にそれぞれの当事者が異なる法域に属する場合には、自己の準拠法と法域を使うことを望む。 |
| 紛争解決 | この条項は、当事者同士が争いをどのように解決するかを定めるものである。訴訟、調停、仲裁など、さまざまな方法がある。 | 紛争解決メカニズムがあれば、紛争解決から生じるリスクや費用を当事者が管理するのに役立つ。 |
出所:本マニュアル(39~46ページ)
また、契約の締結にあたっては、日本と香港の契約慣習や準拠法の違いにも留意する必要がある。
香港企業を含む非日本企業は、自分たちに非常に有利な契約案を出発点として提示し、契約条件の交渉を経て、当事者双方にとって許容できる中間点での合意を目指すことがよくある。一方、日本企業は最初から双方にとって中立的な契約案を提示し、それに関してほとんど、あるいは全く交渉を行わないこともある。
各国・地域の企業は契約交渉においてそれぞれ異なるスタイルや好みを持ち、そのような違いは異なる伝統的な慣習によるものであることに注意すべきである。相手方が同じ契約慣行に慣れていない可能性があることを念頭に置き、その違いが必ずしも信頼の欠如によるものではないことを理解する必要がある。双方にとって許容できる条件で交渉を行い、合意に達することは、将来の当事者間の紛争を回避するという共通の目標のために重要なプロセスだ。
技術契約における知的財産権の紛争に関しては、契約内容に、(1)ライセンシーが第三者からの請求にどのように対処するか、(2)ライセンシーが契約に違反した場合にライセンサーがライセンシーに対してどのように請求を行うか、を決定するために、必要な保証条項、補償条項、知的財産権保護および執行条項が含まれている必要がある。当事者間でこれら詳細について合意しておけば、紛争発生時に、裁判所または仲裁人がどちらの当事者が違反しているかを判断する際の助けとなる場合がある。
また、知的財産権の所有権をめぐる紛争が発生することもよくある。したがって、(1)各当事者に属する既存の技術と知的財産権、(2)いずれかの当事者の既存の知的財産権に基づいて作成された新しい技術と、各当事者の関与度をどのように配分するか、(3)いずれかの当事者の既存の知的財産権とは無関係に作成された新しい技術と、その当事者がそのような新しい技術が独立して作成されたことをどのように証明するかについて、明確な合意書を締結することが重要である。
契約後段階(第3章)
(1)品質管理
技術契約を締結した後も、当事者は契約の遵守を継続的に監視・確認すべきだ。これは、ライセンス契約によってライセンサーの商標を付した商品の製造・販売をライセンシーに認める場合に、ライセンサーの商品の評判や品質を保護し、商標の価値を維持するために特に重要である。そのために、ライセンス契約において品質管理条項を設けたり、商標の使用や製品の製造に関する明確なガイドラインを定めたりすることが有用である。
(2)紛争解決方法
IPR所有者は、香港における特許権、商標権、著作権、さらにはドメイン名に関する権利を守るため、個人や企業に対して民事訴訟を起こすことができる。
しかし、争いを解決するための方法として、訴訟が最善かつ最も効率的な方法ではない場合もある。香港は、アジア太平洋地域における国際的な法律および紛争解決サービスの主要な中心地となってきた。当事者が訴訟に至ることなく意見の相違を解決できる、仲裁や調停といった他の代替的な紛争解決メカニズムもある。
詳細については、香港の裁判外紛争解決手続(ADR)関連のマニュアル![]() (1.1MB)を参照いただきたい。
(1.1MB)を参照いただきたい。
まずは基本的な考え方を把握
本稿では、香港での技術取引・共同研究に関する技術契約の留意点などについて、本マニュアルに沿って解説した。両契約は、各当事者の特定のニーズを満たすためのものであり、ケースバイケースで起草すればいい。ただし、契約内容や契約締結後の品質管理と紛争解決方法について基本的な考え方を把握しておくことは有用だ。
本マニュアルが、日本企業が香港での技術取引や共同研究を検討、展開する際に参考になることを期待したい。
- 注1:
-
詳細は、「香港知財取引調査(技術取引・共同研究編)
 (1.5MB)」17ページ「セクション3:日本企業の潜在的なパートナー」に記載。
(1.5MB)」17ページ「セクション3:日本企業の潜在的なパートナー」に記載。
- 注2:
- 香港をイノベーションと技術の中心地にすることを目的とした、香港政府の国際的な研究開発(R&D)拠点構築プロジェクト。国際的に著名な大学や研究機関が香港科学園(HKSTP)に研究室を設立し、世界レベルの共同研究を行う。
- 注3:
- 新規事業を開始するにあたって契約を締結する前に、発生する可能性のある問題や責任を特定することを目的として、個人または企業に対して行う詳細な調査のこと。

- 執筆者紹介
-
ジェトロ・香港事務所
島田 英昭(しまだ ひであき) - 経済産業省 特許庁で特許審査/審判、特許審査の品質管理や審判実務者研究会などを担当後、2022年8月ジェトロに出向、同月から現職。




 閉じる
閉じる






