旺盛な消費市場、日本製品にもチャンス
フィリピンの投資環境(2)
2025年4月15日
フィリピンでは、5%の経済成長率が近年維持されており、人口は1億人を超えている。今後も高成長や人口増が予測されており、消費市場の拡大も期待できる。また、フィリピン市場の特徴について、日系企業は「宵越しの金を持たない」と表現する。特に「食」への関心が高く、支出割合も高いという。また、フィリピンからの訪日外客数も毎年増加傾向にあり、消費者の日本ブランドへの関心も高まりつつある。
この連載では、マニラ首都圏に進出する日系企業へのヒアリング(注1)を通じて、フィリピンの投資環境を探る。後編に当たる本稿では、富裕層と中間層をターゲットにした消費市場に焦点を当てて考察する(前編は「製造業、「豊富な人材」に強み」)。
フィリピンの成長潜在性、人口ボーナス期が続く
消費の中心を担う若い世代は、今後も増加が見込まれる。フィリピン国勢調査によると、2020年時点の平均年齢(中位年齢)は25.3歳と、ASEAN諸国のなかではラオスに次いで2番目に若い。特に、人口に占める0~14歳未満の比率が30%と高い。国連経済社会局(DESA)の推計値によると、フィリピンの人口は2015年が1億500万人だったが、2023年には1億1,500万人となり、2060年は1億4,000万人まで増える予測だ。さらに、生産年齢人口(15~64歳)の増加も見込まれ、2023年時点では全体の6割を占める。人口ボーナス期は、2050年ごろまで続くとみられる。
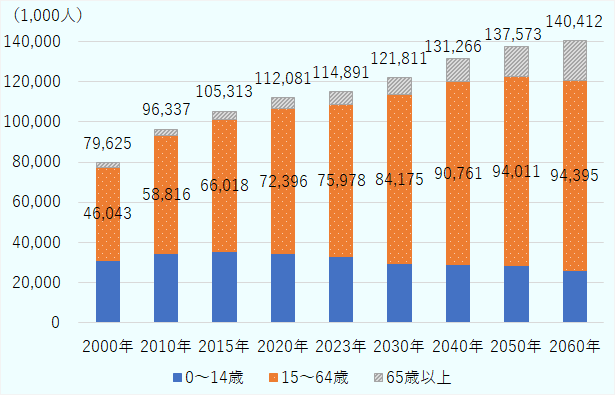
出所:国連経済社会局(DESA)を基にジェトロ作成
富裕層・中間層の拡大、ターゲット層を見定めた販売戦略を
2024年11月公開のジェトロ「2024年度海外進出日系企業実態調査(アジア・オセアニア編)(注2)」の結果を非製造業のみに絞ると、約7割の日系企業がメリットとして「市場規模/成長性」を挙げている。実際に現地の日系企業からも、これに注目しているとの声が聞かれた。2023年のフィリピンの一人当たりGDPは3,805ドル。新型コロナ禍での落ち込みはあったものの、右肩上がりで増えている(図2参照)。また、2030年は中間層にあたる下位所得層が、2025年に比べて8.5ポイント上昇し、33.5%まで拡大する見通しだ(図3参照)。富裕層だけでなく、中間層の拡大も期待されている。
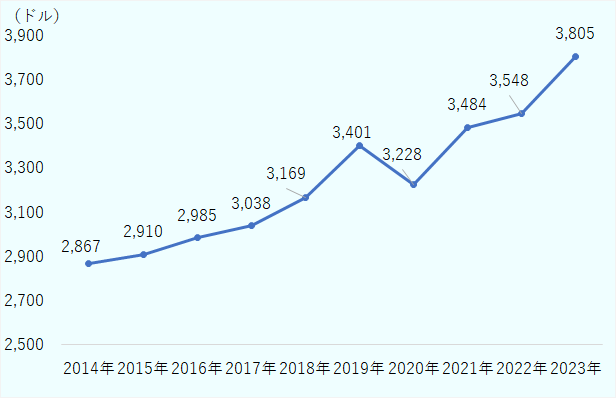
出所:世界銀行
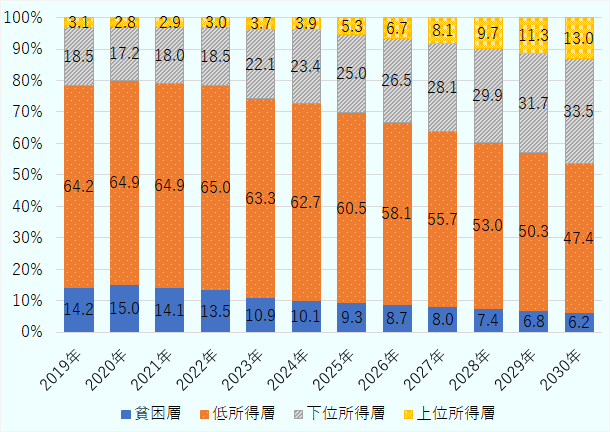
注:年収1,000ドル未満を「貧困層」、1,001~5,000ドルを「低所得層」、5,001~1万5,000ドルを「下位所得層」、1万5,000ドル超を「上位中間層(富裕層を含む)」と定義する。
出所:ユーロモニターを基にジェトロ作成
教育事業を手掛ける日系企業A社は、現状の顧客は富裕層が中心だが、今後の中間層の拡大に期待しており、フィリピンでの事業を拡大している。同社の教育サービスの価格は現地では高水準だが、それでも「フィリピンの富裕層は教育の重要性を認識し、生徒数や教室数の伸びは他のASEAN諸国と比較しても好調」と話す。現在の顧客は私立校に通う富裕層が中心だが、その他の層でも所得や教育志向が高まることを見込んで、ターゲットを中間層まで広げているという。
一方、フィリピンは現状、低所得層が厚いため、富裕層や中間層だけだと市場規模が限られるとの声も聞かれた。耐久消費財を販売する日系企業B社は「フィリピンは人口に占める中間層の割合は必ずしも順調に伸びておらず、幅広い層をターゲットにしている」という。同社は、フィリピン国内市場で、富裕層や中間層だけでなく、国内の約6割を占める低所得層もターゲットに、低価格帯のものから幅広く商品群をそろえている。
商品の価格帯として、限られた富裕層をターゲットにするのか、拡大が今後見込まれる中間層を取り込むのか、大多数を占める低所得層まで狙うのかによって戦略が分かれる。フィリピンは所得格差が大きい国のため、ターゲットを見極めた商品展開や販売戦略が必要だ。
「宵越しの金は持たない」消費活動、食への消費が旺盛
フィリピンの消費市場は、富裕層と中間層の拡大だけでなく、「宵越しの金は持たない」というフィリピン人の習慣にも支えられている。フィリピンの制度上、給与は月2回の支給が定められている。その背景には、給与のうち貯金ではなく、消費に充てる割合が高いことがある。とりわけ「食」に対しては、消費意欲が旺盛だ。
フィリピン統計庁(PSA)によると、2023年の家計支出に占める食品・飲料の割合は4割にのぼる。食事の間に間食(メリエンダ)を挟む習慣があり、それを含めると1日に4~5回食事するのが一般的だ。回数だけでなく、食への関心も高い。そのため、日系企業は口々に「フィリピン人は、想像以上に食にお金をかける」と話す。さらに、日本食は特別なものと捉えられることが多く、価格への許容度が高いという声も聞かれた。

日系食品メーカーC社は、地元の伝統料理は肉とコメが中心で、野菜をあまり食べる習慣がないという。また、フィリピン人は特に甘さや塩辛さが極端で濃い味のものを好むため、肥満症や糖尿病になる人も多い。一方、日系の小売・卸売業D社によると、一部の富裕層・中間層を中心に健康意識が高まっている。近年では、健康的なイメージのある日本や韓国の食品をよく購入しているという。
島国ならではの物流停滞や地域差に注意
一方で、フィリピン特有の課題もある。例えば、物流面だ。国内最大の港湾・マニラ港などの混雑については、多くの日系企業が指摘した。オペレーションが遅いことや、台風などによる急な営業日の変更で、所要時間が読めないという声もある。また、通関手続きやコールドチェーンの未整備といったことが課題として挙げられる。小売・卸売業D社からは「食品医薬品局(FDA)による輸入食品の検査や通関手続きに時間がかかる。コールドチェーンの未整備により、温度調整が必要な生鮮食品や酒類、賞味期限が短い食品の仕入れが難しい」との意見があった。
さらに、島国ならではの課題も聞かれた。食品メーカーC社は「商品をフィリピン全土に行き渡らせるには、時間とコストがかかり難しい」と話す。加工工場をマニラ首都圏のあるルソン島と中部セブ島に分ける事例も見られる。また、「売れ筋商品には地域差はない」との声もあったが、ミンダナオ島はイスラム教徒が多いため、同地域で食品を展開するにはハラル対応も検討する必要がある。
日本ブランドへの関心高まる、ウェットな関係構築を
フィリピン人は英語を使えるため、欧米の文化に触れる機会が多い。かと言って、必ずしも欧米系の小売・サービスがフィリピン市場を席巻しているわけではない。フィリピンには、これまで進出してきた日系企業や政府開発援助(ODA)などが積み上げてきた日本ブランドへの信頼がある。最近では、日本食やアニメ好きの人も増えてきた。
さらに、フィリピンからの訪日外客数は増え続けていて(2025年1月17日付ビジネス短信参照)、2024年は約82万人のフィリピン人が訪日した。小売・卸売業D社からは「何度も日本を訪問する富裕層・中間層がいて、ガストロノミーツーリズム(注3)を楽しむ人が増えてきている」との声があった。何度も日本を訪問することで、日本の「本場の味」や地方産品の魅力を知るフィリピン人が増え、それがフィリピン国内での日本の商品・サービスの需要につながっているという。食品関連の企業では、ニッチな日本商品や日本で人気の健康志向商品の取り扱いを増やしているところもある。日本への理解が深まる中で、日本らしい商品への関心も高まっている。
日本ブランドの知名度向上や販売促進に向けては、SNSを活用した自社製品やサービスの広報も重要だ。特に、フィリピン国内はフェイスブックの利用者が多く、消費者とのコミュニケーションツールとして影響力が大きい。企業からのプロモーションだけでなく、消費者の声を拾うことを目的に活用できる。
一方、フィリピン市場で展開するにあたり、パートナーの重要性を強調する企業もある。耐久消費財を販売するB社は「消費者と接点があるパートナー企業とのウェットな関係構築が重要」と話す。企業の代表同士で、直接コミュニケーションする機会を大事にしているという。フィリピン消費市場でのビジネス展開には、SNSでの戦略に加え、フェイス・トゥ・フェイスのコミュニケーションも外せない。
- 注1:
- ヒアリング期間は2025年1月20~24日。電気電子機器・部品、輸送機器・部品などのメーカーや工業団地運営会社、小売り・サービス業、商社など、合計13社にヒアリング実施。
- 注2:
- 日系企業調査では、2024年8月20日~9月18日に、アジア・オセアニア地域に進出する日系企業に対してアンケート調査を実施した。
- 注3:
- ガストロノミーツーリズムとは、その土地の気候風土が生んだ食材や歴史などによって育まれた食を楽しみ、食文化に触れることを目的とする観光のこと。
フィリピンの投資環境
- 製造業、「豊富な人材」に強み
- 旺盛な消費市場、日本製品にもチャンス

- 執筆者紹介
-
ジェトロ調査部アジア大洋州課 課長代理
庄 浩充(しょう ひろみつ) - 2010年、ジェトロ入構。海外事務所運営課、ジェトロ横浜、ジェトロ・ビエンチャン事務所(ラオス)、広報課、ジェトロ・ハノイ事務所(ベトナム)を経て現職。

- 執筆者紹介
-
ジェトロ調査部アジア大洋州課
西村 公伽(にしむら きみか) - 2024年、ジェトロ入構。アジア大洋州課でASEANおよびオセアニア関係の調査を担当。

- 執筆者紹介
-
ジェトロ・マニラ事務所
西岡 絵里奈(にしおか えりな) - 2016年、ジェトロ入構。途上国ビジネス開発課、ジェトロ・プノンペン事務所、ビジネス展開支援課、対日投資課DX推進チーム、ジェトロ島根を経て、2023年9月から現職。






 閉じる
閉じる





