幸福の国・ブータンへの投資機会とは
デジタル技術や独自指標のブランド化がポイント
2023年12月12日
国民総幸福量(Gross National Happiness:GNH)という独自指標で知られ、2023年12月には後発開発途上国(LDC)卒業を予定しているブータン。これまで豊富な自然資源を主とする観光産業や、水力発電で生み出した電力を輸出し堅実な経済成長を維持してきた。他方、今後ブータン政府としては、ポストコロナ時代における、よりバランスのとれた持続可能な成長のため、外国投資を積極的に呼び込みたい考えだ。デジタルデータの医療への活用といった技術協力、また都市部や海外への若年層の流出という課題に直面する中、日本の自治体をモデルとする取り組みも行われており、日本との関係強化が期待される。日系企業や自治体にとっての参入チャンスや障壁を探るべく、ブータン市場の魅力や課題について、独立行政法人 国際協力機構(以下、JICA)南アジア部の若林康太氏に聞いた(取材日:2023年10月6日)。
外国企業による投資を誘致
人口約78万人の内陸国であるブータンは、インドと中国という大国に挟まれ、地理的な重要性を持つ。主要産業の1つである観光産業においては、外資系の高級ホテルが点在するが、日系企業の参入は見られない。観光に限らず、日本企業の現地法人はほとんどなく、多くはODAプロジェクトベースで事業を展開している状況だ。
ブータン政府は、外国企業による投資を呼び込むべく、「グリーンで持続可能な経済の発展」やブータンの産品などをGNHのコンセプトに合わせて生産する「ブランド・ブータンの推進」といった外国直接投資(FDI)施策を展開している。若林氏は投資拡大への課題として、小規模な国内市場や金融コスト、成長途上の民間セクター、資機材の輸入依存、政府の許認可取得など煩雑な手続きを挙げた。また、山岳国としての地理的制約も障壁の1つであるとした上で、これらの課題をブータン市場の投資機会と捉えることもできるという。
市場規模が小さく、法制度が十分に整備されていないからこそ、国単位での実証事業が行いやすいことは、日本企業にとって魅力となり得る。実際にブータンでの実証事業を実施している日本企業も存在する。例えば、実用的なルール構築に前向きなブータン政府は、山がちな国土環境も生かしつつ、日本企業などと連携してドローンの活用を進めていくことを模索している。急峻(きゅうしゅん)な山岳地域に集中する小中規模集落への物流改善など、開発課題の解決も見据えたJICAの技術協力も予定されている。

デジタルプラットフォームの浸透
さらに、デジタル分野における協力・投資余地もある、と若林氏は指摘する。前述した山岳国としての地理的制約を乗り越える手段として、デジタル技術の促進やITのプロフェッショナル人材を育成する動きが見られるという。同氏は、具体例として「デジタルヘルスプラットフォーム![]() 」の構築を挙げた(図参照)。
」の構築を挙げた(図参照)。
ブータン政府は国民のデータを1つのプラットフォームに集約させることを構想しており、本プラットフォームを用いて国民の医療・健康関連データを一元化し、予防医療などを通じた保健・医療の質の向上や、創薬研究などを通じた産業振興に役立てたいとしている。
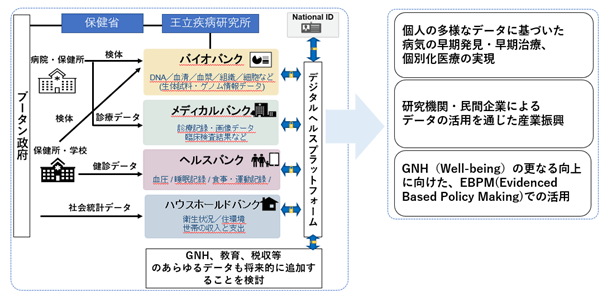
出所:JICA作成、提供
ブータン駐在を経験した若林氏は、デジタルプラットフォームの導入が比較的容易であるのは、ブータンが持つ強いガバナンス力に加え、現状では規制が十分に整備されていないこと、さらに山岳国である地理的制約による障壁などがあることの裏返しかもしれない、と実感を持って話す。
同氏によると、首都ティンプーにある同国初のIT産業向け施設「テックパーク![]() 」に欧米のIT企業が複数入居しているほか、IT専門学校の設立などIT人材育成の取り組みも散見され、今後、IT産業において投資先として注目を集める可能性がある。ブータン政府や関連機関によるプロモーションにも注目したいと考える。
」に欧米のIT企業が複数入居しているほか、IT専門学校の設立などIT人材育成の取り組みも散見され、今後、IT産業において投資先として注目を集める可能性がある。ブータン政府や関連機関によるプロモーションにも注目したいと考える。
GNHブランドを生かす
また、ブータンでは若年層の失業率が30%に迫っており、就業機会を求めて海外に移住・永住する若者も多い。この対策の一環として、若者の還流に成功している島根県隠岐郡の離島、海士町との交流はとても興味深いという。海士町では、知識の暗記やスコア重視の学習ではなく、生徒が「自ら考え、地域の課題を発見し、解決する能力を身に付ける」ことを目的とした教育手法を取り入れたことで、地域唯一の高校での教育の魅力化を実現した。海士町は人口約2,300人の小さな町だが、この教育魅力化の取り組みを通じて、少子高齢化や若者の島外流出を乗り越え、8年間で生徒数が倍増した。地域ならではの資源や課題を生かしたブランディングが、若者の地域への還流を呼んでいると考えられる。
2024年までの教育改革実現に取り組んでいるほか、地方から都市部、都市部から海外への若年層の流出という課題を抱えるブータンにとって、国づくりの1つのモデルとなる可能性がある。若林氏は「GNHというブランドをいかに活用し、グローバル戦略を練っていくかが重要。また、若年層の高い失業率という課題に対しても、ブータンらしさを生かした、魅力ある就業機会の創出が必要」と指摘した。


- 執筆者紹介
-
ジェトロ企画部企画課海外地域戦略班(南西アジア担当)
金子 優(かねこ ゆう) - 2019年、ジェトロ入構。総務部総務課、ビジネス展開・人材支援部新興国ビジネス開発課を経て、2023年4月から現職。




 閉じる
閉じる






