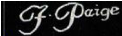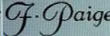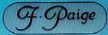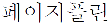知財判例データベース 商標権侵害損害賠償訴訟で、損害額の立証困難を理由に弁論全体趣旨と証拠に基づいてその額を認定した事例
基本情報
- 区分
- 商標
- 判断主体
- 特許法院
- 当事者
- 原告 個人A、B社 vs 被告 C社
- 事件番号
- 2017ナ2523
- 言い渡し日
- 2018年12月07日
- 事件の経過
- 原告一部勝、2019年5月3日確定
概要
原告個人Aは原告B社の代表者であって、下表に記載された本件各商標の登録商標権者であり、原告B社は本件各商標の専用使用権者である。特許法院は、原告個人Aの不正競争防止法に基づいた損害賠償請求に対しては、不正競争防止法が保護の客体として規律する対象は周知性のある標識そのものではなく、その標識によって出所が区別される「他人の商品」若しくは「他人の営業」又は「正当な権利者の信用や名声」であることから、営業活動自体は移転されずに周知性のある営業標識のみ移転される譲渡・譲受があり、譲受人がその商標に基づいた営業を行っていないならば、少なくともその期間の間には特別な事情がない限り、その譲受人は、従前の譲渡人が取得した周知性の承継を理由として不正競争防止法に基づいた損害賠償請求をすることができないと判断すべきであるとした。一方、原告B社の商標法に基づいた損害賠償請求に対しては、弁論全体の趣旨と証拠調べの結果に基づいて、被告C社は原告B社に対して本件各商標に関する専用使用権侵害行為による損害を賠償する義務があると判決した。
「本件各商標」、「被告各標章」は次のとおりである。
本件各商標
| 区分 | 登録番号 | 登録日 | 標章の構成 | 指定商品 |
|---|---|---|---|---|
| 本件第1商標 | 第863387号 | 2011年5月3日 |  |
第25類の衣類、靴、スポーツ専用衣類など |
| 本件第2商標 | 第771893号 | 2008年12月9日 |  |
第25類の靴、スポーツ専用衣類、外套、既製服など |
被告各標章
事実関係
訴外D社は2007年から本件各商標を使用し、2013年6月頃に同社が不渡りを出すや、原告個人Aは、本件各商標に関する商標権を競売落札して2014年8月に自身の名義で各商標権の移転登録を終え、原告B社は2014年8月頃に本件各商標と関連した商品を発注し始め、2014年11月以後から本件各商標が付された衣類をオンラインショッピングモールで販売した。なお、訴外D社は2011年頃に本件各商標のサブブランドである「F.paige」商標の使用も開始していた。
一方、2013年2月25日に訴外D社との間で、被告C社の代表者(社内理事)が代表理事をしている訴外E社は「訴外E社は、2013年9月1日から2015年8月30日までの2年間に2億ウォンを支払う対価として、その製造又は販売する製品に「F.paige」商標を使用することができ、その商標のメインブランドである「paige Flynn」(페이지플린=paige Flynnのハングル)ブランドをホームショッピングの放送中に広報用として使用することができる」という内容のブランド使用契約を締結した。すると、同日に訴外E社との間で被告C社は「上記商標をC社が製造又は販売する製品に使用することができる」内容のブランド使用契約を締結した。被告C社は当該ブランド使用契約によって2013年9月から2015年3月3日まで被告C社が製作、販売する女性衣類商品のラベル、広告物などに「被告各標章」(個別には「被告第○標章」という)を表示し、ホームショッピングの放送、オンラインショッピングモールなどを通じた販売を行った。
こうした中、原告個人Aは、被告C社を相手取って本件各商標、被告第1標章及び「F.Paige by 페이지플린」標章の使用差止等を求める仮処分を申し立てたが、2015年3月3日に、上記当事者間で被告C社が上記各標章を使用しない旨の調停が成立した(本件は、原告個人Aと原告B社が2014年11月24日から2015年3月3日までの損害賠償を求めたことに関するものである)。
判決内容
不正競争防止法に基づいた損害賠償請求
イ.原告個人Aの損害賠償請求
原告個人Aは、本件各商標に基づく営業を行っていなかったので、従前に譲渡人が取得した周知性の承継を理由に不正競争防止法に基づいた損害賠償請求をすることはできないと判断しなければならない。
ロ.原告B社の損害賠償請求
原告B社の請求が認容されたとしても、それによる損害額は商標法上の損害賠償請求額を超えないと認められるので、認容金額を超えての不正競争防止法に基づく損害賠償請求は理由がない。また、認容金額範囲内の選択的請求については、これと選択的関係にある商標法に基づく損害賠償請求を認容している以上、これについて別途に判断は行わない。
原告B社の商標法に基づく損害賠償請求
イ.前提事実
原告B社主張の侵害期間の間、被告C社が被告第1、2、4、6標章(以下「本件侵害標章」という)を使用したことを前提にその侵害の成否について判断する。
ロ.専用使用権侵害の成否
被告C社が本件各商標と類似の本件侵害標章を本件各商標の指定商品と同一・類似の女性服などの衣類に使用する行為は、本件各商標の保護範囲に属するので、被告の行為は原告B社の本件各商標に対する専用使用権侵害行為に該当する。そうであれば、被告は原告B社が受けた損害を賠償する責任がある。
ハ.損害賠償責任の範囲に関する判断
原告B社に損害が生じた事実は認められるが、損害額算定のための基礎資料が被告C社に偏重しており、本件各商標の使用が被告の売上高又は利益増加に寄与した比率など損害額を立証するために必要な事実を証明することも極めて困難なので、旧商標法第67条第5項(注1)により、法院が弁論全体の趣旨及び証拠調べの結果に基づいて認定することができる、以下の事情を考慮して相当する損害額を認めることとする。
- 侵害期間の間、被告の売上高30億ウォン余りに被告の平均売上対比営業利益率3.2%を乗じると、被告の利益額は9,700万ウォン余りになり、
- 所得税法による2014年度の衣服卸売業の標準所得率は6.4%であるところ、侵害期間の間の被告の売上高に標準所得率6.4%を乗じると、1億9,000万ウォン余りになるが、これを被告が本件侵害標章が使用された商品を販売して得た純利益を算定するのに参考にする余地があり、
- 原告B社は原告個人Aに本件各商標の専用使用権に対する使用料として9,000万ウォンの前払金及び総売上高の3%を経常ロイヤリティとして支払うことと約定したが、上記基準と同一に第三者に使用権を許諾すると仮定すると、被告が原告会社に支払うべき使用料に相当する損害額は前払金に経常ロイヤリティ9,100万ウォン余り(=被告の売上高3,035,373,892ウォン×ロイヤリティ率3%)を合算した1億8,000万ウォン余りになる。被告も一般的な衣類商標権の通常使用料は売上高対比2~5%水準であると主張しているので、被告の上記売上高を基準に5%を適用して計算した金額が1億5,000万ウォン余りである点を考慮すると、原告B社と原告個人Aが本件各商標の専用使用権について約定した使用料は不合理な程度に過多であるとは言い難い。
- さらに、原告個人Aが本件商標に対する商標権を買い取った価格が1億500万ウォン余りであり、侵害期間が原告B社が製品を市場に販売し始めた最初の3カ月程である点、その他本件訴訟過程で示された諸般の事情などをともに考慮する。
小結論
被告C社は、原告B社に、本件各商標に対する専用使用権侵害行為による損害賠償として2億ウォン、及び本件訴状送達の翌日から本件判決言渡日までは民法で定めた年5%、その翌日から支払完了までは訴訟促進等に関する特例法による年15%の各比率で計算した遅延損害金を支払う義務がある。
専門家からのアドバイス
本件は、競売で競り落とした商標権の譲受人が、当該商標権を侵害した者に対して商標法違反と不正競争防止法違反を理由に損害賠償請求をした事件である。
不正競争防止法に基づく損害賠償請求に関連して、特許法院は、営業活動自体は 譲受人に移転されておらず、その商標に基づいた営業も行われていなかったので、従前の譲渡人が取得した周知性の承継を理由として不正競争防止法に基づいた損害賠償請求をすることはできないと判断した。これは、過去に大法院が示した「不正競争防止法が周知の商品標識を保護する目的や趣旨は、商品標識主体の投資や労力によって構築された顧客吸引力や名声等の商品標識に化体された営業上の信用が、第三者によって侵害されるのを防止するところにある」という判例の内容に沿ったものといえ、当該法理の理解に参考になると思われる。
一方、商標権侵害に対する損害賠償責任の範囲についての判断と関連し、特許法院は、旧商標法第67条第5項を適用して弁論全体の趣旨と証拠調べの結果に基づいて認定することができる損害額を算定しているところ、こうした損害額の算定方法は具体的な事例理解のための参考となろう。 なお、本件は特許法院の判決に対して被告が上告し、大法院に係属中にある。
注記
-
旧商標法第67条第5項 法院は、商標権又は専用使用権の侵害行為に係る訴訟において損害が生じたことは認められるが、その損害額を立証するために必要な事実を立証することが当該事実の性質上極めて困難な場合には、第1項乃至第4項の規定にかかわらず、弁論全体の趣旨及び証拠調べの結果に基づき、相当する損害額を認定することができる。
ジェトロ・ソウル事務所知的財産チーム
ジェトロ・ソウル事務所 知的財産チームは、韓国の知的財産に関する各種研究、情報の収集・分析・提供、関係者に対する助言や相談、広報啓発活動、取り締まりの支援などを行っています。各種問い合わせ、相談、訪問をご希望の方はご連絡ください。
担当者:大塚、李(イ)、半田(いずれも日本語可)
E-mail:kos-jetroipr@jetro.go.jp
Tel :+82-2-3210-0195




 閉じる
閉じる