世界を牽引する中国のeスポーツ
2025年1月10日
2024年夏、サウジアラビアで史上初の「eスポーツ・ワールドカップ」が開催された。8週間にわたり計22種目で約500チーム1,500人のプレーヤーが技を競い合った。賞金総額は6,000万ドルを超え、総合優勝チームは賞金700万ドルを手にした(2024年9月2日付ビジネス短信参照)。日本でも、「ストリートファイター6」部門で優勝した日本人選手が賞金40万ドルを獲得したことで話題になった。
2023年9~10月に中国浙江省杭州市で開催された「第19回アジア競技大会」では、初めてeスポーツが正式メダル種目として採用された。2026年に愛知県名古屋市で開催予定の同大会でも、引き続きeスポーツが正式種目として採用されることが決まっている。
「eスポーツ」とは、エレクトロニック・スポーツ(electronic sports)の略称で、コンピュータゲームなど電子機器を用いて行われる対戦や競技をスポーツと捉えて定義した呼称である。近年では、単なるゲームではなく、プロ選手も存在する競技として社会的認知が進むとともに、ゲーム産業とスポーツ産業の中間に位置し、市場の拡大が進む1つの産業分野としても着目されるようになってきた。
eスポーツ産業の世界最大の市場と言われているのが中国である。市場調査・コンサルティング会社のNiko Partnersの調査(注)によると、eスポーツ業界の世界全体の売上高のうち中国は34%を占めるという。
eスポーツ競技タイトルの多くを運営するテンセントや、世界初かつ世界最大のeスポーツ運営専門会社である英雄体育管理(VSPO)など、中国にはこの分野でのリーディングカンパニーも多い。
本稿では、世界で広がるeスポーツ産業の中国での状況について解説する。
eスポーツの歴史
まず、eスポーツの歴史を簡単に振り返る。1960年代にコンピュータ技術を活用したゲームが開発され、1970年代に入ると家庭用ビデオゲーム機やアーケードゲーム機が登場し、コンピュータゲームの産業化が進んだ。1970年代のアーケードゲーム全盛期、米国などで競技大会が開催されるようになったが、この時期の競技はハイスコアを競い合うものであった。1991年にカプコンが発売した対戦型格闘ゲーム「ストリートファイターⅡ」は、プレーヤー同士が直接対決するスタイルを浸透させた。また、この頃急速に普及したインターネットが、オンライン接続によるコンピュータゲームの個人間またはチーム間の対戦を容易にし、1990年代には大規模な競技大会が世界中で開催されるようになった。
2000年代に入ると、韓国などを中心にインターネットカフェが急速に普及し、オンラインゲームを楽しむ人口が拡大していった。各国で協会や運営組織が作られ、プロチームも結成された。また、この頃からeスポーツ競技大会のテレビ中継や各種配信サービスが始まり、観戦者としてのファン層の拡大が、産業としてのeスポーツ発展を後押しした。
中国におけるeスポーツ
中国では2000年から2015年まで、家庭用ゲーム機の販売が禁止されていた。当時、個人でプレーするゲームが世界の主流だったが、中国での主流はPC(パソコン)ゲームから始まり、モバイルゲームにシフトしていった。つまり、「ステージをクリアする」ことではなく「相手プレーヤーに勝つ」ことをゲームの目的とする習慣が、中国では他国に先駆けて根付いていた。これが、中国でオンラインゲーム競技が普及する背景の1つとなったと考えられる。
2003年3月に中国初のeスポーツ公式大会として「CEG(China E-sports Gaming)」が開催され、同年11月には国家体育総局がeスポーツを第99番目のスポーツ正式競技として認定した。また、中韓両国政府が主催するeスポーツ大会「International E-sports Festival(IEF)」も、2005年に開始され現在も続いている。2005年に「War Craft」世界大会で中国人選手が初優勝すると、中国国内でのeスポーツへの注目度が高まり、2010年代にはIT系など多数の大手企業がeスポーツ業界に参入し、発展が加速する。
eスポーツゲームのうち、最も競技人口が多いとされるのが「リーグ・オブ・レジェンド(League of Legends)」(略称「LoL」)である。LoLは、米ライアット(Riot Games)が開発し2009年にリリースしたゲームタイトルだが、わずか2年後の2011年にはテンセントが株式の過半数を取得、2015年には完全買収が完了し、ライアットはテンセントの100%子会社となった。テンセントはこのほか、eスポーツの著名な競技タイトルである「フォートナイト」を手掛ける米エピックゲームズ、「クラッシュ・ロワイヤル」などを開発したフィンランドのSupercellなどにも出資し、傘下企業としている。2023年の杭州アジア競技大会のeスポーツ競技7タイトルのうち、4つはテンセントが開発または販売したゲームであった。また、オリンピック形式で行われるeスポーツ大会であるWESG(World Electronic Sports Games)は、アリババが所有、運営するなど、多くの大手中国企業がこの分野に参入している。
2016年に上海市で設立された「英雄体育管理(VSPO)」は、世界初かつ世界最大のeスポーツ運営専門会社である。VSPOは、2018年のジャカルタ大会からeスポーツが公開競技化された(2023年の杭州大会からは正式メダル競技となった)アジア競技大会の運営に携わるほか、多数のeスポーツ公式世界大会の運営を担っている。先述のサウジアラビアeスポーツ・ワールドカップの運営は、同国のムハンマド・ビン・サルマン皇太子兼首相が中心になって設立したEsports World Cup Foundationが担ったが(2023年10月25日付ビジネス短信参照)、VSPOも共同運営企業として名を連ねている。
2011年には、不動産大手の大連万達集団の創業者、王健林氏の息子で投資家の王思聡氏がプロeスポーツクラブを設立した。これを機に、他のスポーツと同様に、eスポーツのプロチームが多数設立されるようになり、いわゆる「スター・アスリート」が登場し始める。
「LoL World Championship」では、2018年から連続して中国チームがタイトルを獲得したほか、2020年の世界大会決勝は上海市で開催され、中国国内のファンを歓喜させた。その後も、世界的な大会で中国チーム、中国人選手がタイトルを手にするようになり、スターとファンが形成されることで、プロスポーツとしての産業化が加速することになった。

出所:Bruce Liu, CC BY-SA 3.0, via Wikimedia Commons.
産業としてのeスポーツ
2024年12月に北京市で開催された「2024中国eスポーツ産業年会」で、中国音像デジタル出版協会が公表した「2024年中国eスポーツ産業報告」によれば、中国におけるeスポーツの産業全体の収入額の推移(図1参照)およびeスポーツゲームのユーザー登録数の推移(図2参照)は次の図の通りである。
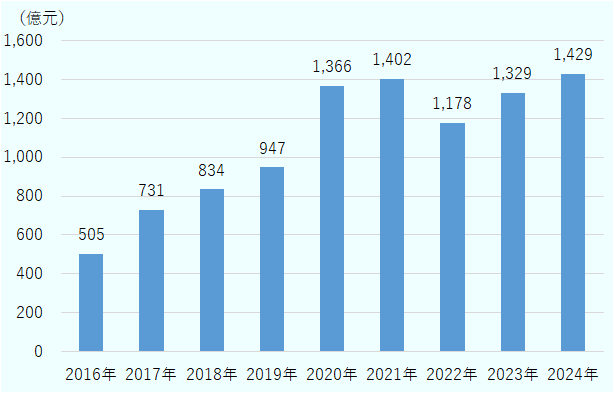
注:1元=約22円。
出所:中国eスポーツ産業報告
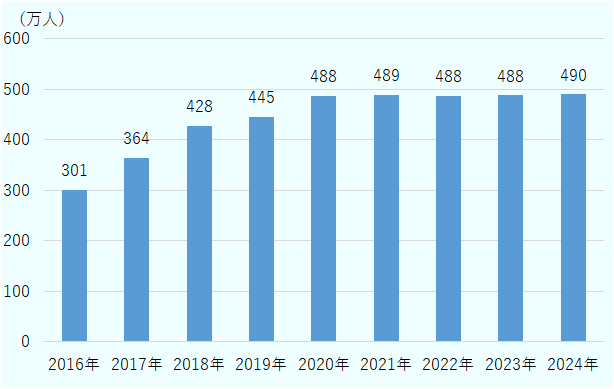
出所:中国eスポーツ産業報告
これらの図から見て取れる通り、2020年以降、収入総額およびユーザー登録数は頭打ちの状態であり、中国のeスポーツ産業は既に発展段階から成熟段階に入っている可能性がうかがえる。
また同報告書によれば、eスポーツ産業収入に占める項目別の比率は図3の通りで、ライブ配信収入が8割以上を占めている。
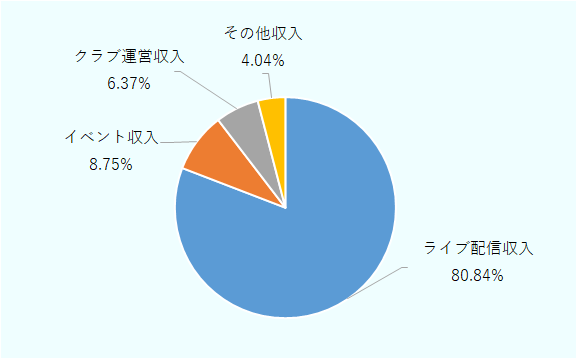
出所:中国eスポーツ産業報告
いまや、各種映像配信プラットフォームでのeスポーツ競技のライブ配信には、多数のスポンサーが付く。eスポーツが、単なるゲームではなく、スポーツに近い産業形態として成り立つのは、ライブ配信を視聴する人、すなわちファンの存在があるためである。
かつて、コンピュータゲームのコミュニティと言えば、プレーする人だけに閉じられていた。これが、LoLなどの超人気タイトルと、プロゲーマーおよびプロチームの登場により、コミュニティはゲームをプレーしない人たちにまで広がった。少しだけプレーしてみたことがあるという経験者も、eスポーツの潜在的な観客となった。
2012年から2014年にかけ、プロゲーマー(eスポーツ選手)を主人公とした小説「マスターオブスキル(中国語名:全职高手)」が刊行され、2017年にはテンセント・ピクチャーズによってアニメ化されて人気を博した。このような関連コンテンツも、プレーヤーでないファン層の拡大に貢献している。
ファン層が拡大すればするほど、スポンサー企業が増える。前述の2024年サウジアラビア・eスポーツ・ワールドカップは、サウジアラムコなど開催国企業のほか、アディダス、アマゾン、ユニリーバ、ソニーなど約20社のグローバル企業がスポンサーとして参加している。また、Moonton(上海沐瞳科技)、ファーウェイ傘下のHonor、テンセント傘下のLevel Infinite、TikTokなど中国系企業もスポンサーに名を連ねている。
中国政府の関連政策
前述のとおり、国家体育総局がeスポーツを第99番目のスポーツ正式競技として認定したのは2003年であり、中国政府は比較的以前からeスポーツ振興に積極的であった。2019年には、「プロゲーマー」も正式な職業として認定された。
国家体育総局は2016年、「体育産業発展第13次5カ年規画」において、新興体育産業の1つとして「eスポーツ(電子競技運動および管理)」を加えた。また同年には、同局の指示のもと、大学対抗eスポーツトーナメントが開始された。同じく2016年には、教育部によって、専門学校の新たな科目として「eスポーツ」が設置され、さらにeスポーツ専門学校の設立が許可された。
各地方政府も、独自のeスポーツ振興策を打ち出している。例えば、広東省では2021年10月、広州体育学院、広東省eスポーツ協会、広州市内のゲーム開発企業の3者が「eスポーツ教育産業戦略協力協定」を締結し、産学連携によるeスポーツ人材育成基地が同省広州市に設立されるなどした(2022年1月20日付ビジネス短信参照)。
また、各地方政府の支援によりeスポーツ専用スタジアム・アリーナの建設も進んでいる。2018年に重慶市で世界初のeスポーツ専用アリーナが開業して以来、上海市、広東省深セン市、北京市、杭州市、四川省成都市などに続々と専用アリーナが開業している。
中国政府では、スポーツ振興関連部門が積極的にeスポーツ振興策を進める一方、近年では教育関連をつかさどる部門において、未成年者のゲーム依存症を問題視し、未成年者のゲームプレー時間を制限する規制などが出されている。
2019年10月に国家新聞出版署が公布した「未成年者のオンラインゲーム依存の防止に関する通知」では、未成年者のゲームプレー時間を平日1.5 時間、週末3時間に制限した。さらに、2021年8月に同じく国家新聞出版署が公布した「未成年者のオンラインゲーム依存を防止するための管理強化に関する通知」では、オンラインゲーム運営業者に対し、未成年者へのサービス提供を1週間のうち原則、金・土・日の各曜日のそれぞれ1時間ずつに限定するよう求めた。
アジア競技大会で、eスポーツ競技に出場した中国人選手の平均年齢は20歳だという。多くの選手が10代前半からトレーニングを開始するが、政府によるゲームプレー時間の制限が選手育成の足かせになる、との懸念の声も聞かれる。
すでに世界中で1つの競技スポーツとして、また、新たな産業分野として認知されつつあるeスポーツだが、本稿で解説した通り、その普及・発展には中国が大きくかかわっている。eスポーツがさらに発展し、社会に浸透するには、ゲーム自体を制作するメーカーやクリエーターのみならず、プロ選手や所属するクラブ、選手を育成する学校、競技を行うためのスタジアム・アリーナなどの施設、大会の様子をファンに届けるメディアや解説者、さらにファン層を拡大させうる関連アニメなどのコンテンツやグッズ製造・販売など、多くのステークホルダーがバランスよく成長していく必要がある。そして、特に中国において、そのために欠かせないのが政府による政策的な支援であるが、今後、政策面でeスポーツの振興と、若者のゲーム依存症による社会への弊害の防止・抑制とのバランスをどのように取っていくか注目される。
- 注:
- レポート名称は「Esports in Asia and MENA」、発行は2023年5月。データは2022年時点のもの。

- 執筆者紹介
-
ジェトロ・北京事務所 次長
森永 正裕(もりなが まさひろ) - 1998年、アジア経済研究所入所。ジェトロ・上海事務所、JOGMEC・北京事務所長(出向)、研究企画課長、ジェトロ・成都事務所長などを経て現職。

- 執筆者紹介
-
ジェトロ・北京事務所
馮 梓原(ひょう しげん) - 日本の大学を卒業し、2024年4月からジェトロ・北京事務所勤務。




 閉じる
閉じる






