アジア大洋州地域の人材確保・賃金高騰の現状と対応際立つ人材不足、給与外の待遇改善にも創意工夫(マレーシア)
2024年3月21日
マレーシアでは、ASEAN主要国と比して人材不足の深刻さが際立つ。そのため投資環境上のリスクも、離職率の高さなど人材関連に集中している。人手は足りていても、職種によっては優秀な「人材」の獲得競争が激化している、との指摘もある。
ジェトロの「2023年度海外進出日系企業実態調査(アジア・オセアニア編)」(以下、日系企業調査)から、人手不足の現状や打開に向けたヒントを探る(注1)。
投資リスクは人材関連に集中
日系企業調査では、投資環境上のメリットとリスクについて聞いている。メリットとしては、マレーシア進出日系企業の8割が、(1)「言語・コミュニケーション上の障害の少なさ」を挙げた(81.2%)。次いで、(2)「駐在員の生活環境」(58.9%)や(3)「安定した政治・社会情勢」(53.4%)などを好感している。(3)に関しては、当地政情の安定が見通せるという見方が大宗を占めることが背景にある。2023年8月の州議会選挙(2023年8月15日付ビジネス短信参照)以降しばらくは、大きな選挙の予定がないためだ。
他方、投資環境上のリスクは図1の通りだった。(1)「人件費の高騰」(66.0%)を筆頭に、(2)「従業員の離職率の高さ」(49.8%)、(3)「労働力の不足・人材採用難」(44.0%)が次いだ。「人件費の水準」「ビザ・就労許可手続き」「離職率の水準」が上位に挙がった前回調査と同様に、引き続き課題は人材関連に集中したかたちだ。特に(2)は、ASEAN主要6カ国の中で最も回答率が高い。シンガポール(40.2%)やタイ(32.0%)以上に深刻である。
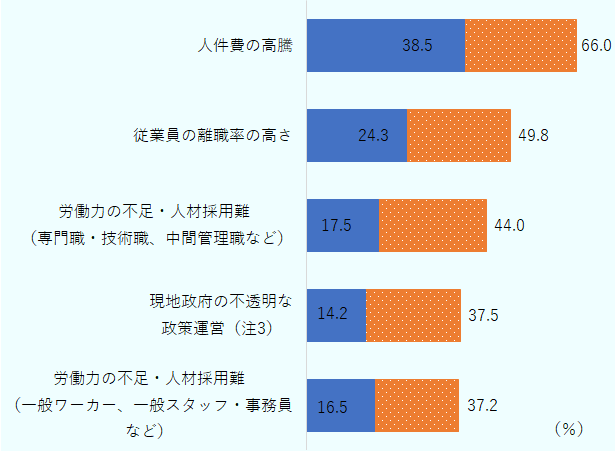
注1:有効回答数309。
注2:オレンジ色は、ビジネス環境上のリスクとして回答した企業の割合。青色はリスクとして特に当てはまると回答した企業の割合。特に当てはまるものは最大3項目まで選択可能。
注3:政策運営とは、産業政策、エネルギー政策、外資規制などを指す。
出所:ジェトロ「2023年度海外進出日系企業実態調査(アジア・オセアニア編)」
2024年の昇給率は4.3%、ASEANでは中位
最大のリスクに挙がった「人件費の高騰」にき、調査時点で、マレーシアの基本給(平均値)は、職種を問わずシンガポールに次ぐ高水準だった。2022年5月に実施された最低賃金引き上げの影響も尾を引き、2023年7月には零細企業にも賃上げ対象が拡大。中でも高給なのが非製造業マネージャーで2,074ドル、次いで製造業マネージャーで1,643ドルだった。
日系企業調査によると、当地で2024年の昇給率見通しは平均4.3%と、2023年を0.3ポイント下回る水準だ。業種別にみると、製造業の昇給率見通しは、前年比0.5ポイント低下して4.1%、非製造業は0.3ポイント低下して4.4%。昇給率に関しては、ASEAN主要6カ国の中で中位水準にある。
英保険ウイリス・タワーズ・ワトソン(WTW)が2023年10月に実施した調査で、マレーシア企業の給与は、2024年に5.0%上昇する見通しだ。前年の5.6%より低下したが、それでも平均昇給率はこの数年上昇を続けている。WTWによると、インフレ率が鈍化傾向にあるものの、人材難は継続しており、自己都合による退職率は2022年の16.5%から2023年には18.5%に上昇した。この傾向は2024年も続く。全般的に、人材獲得や維持が難しい状況が続くとWTWは予測している。
マレーシアの人手不足感は、失業率からも読み取れる。2023年6月時点で失業率は3.4%、同11月にさらに3.3%に低下し、2020年2月以来の低水準で下げ止まった。一方、消費者物価指数の上昇率は2022年8月(4.7%)をピークに低下基調が続く。2023年11月には1.5%と、2年8カ月ぶりの低水準に落ち着いた(図2参照)。物価の安定が賃金上昇を一定程度和らげている可能性がある。
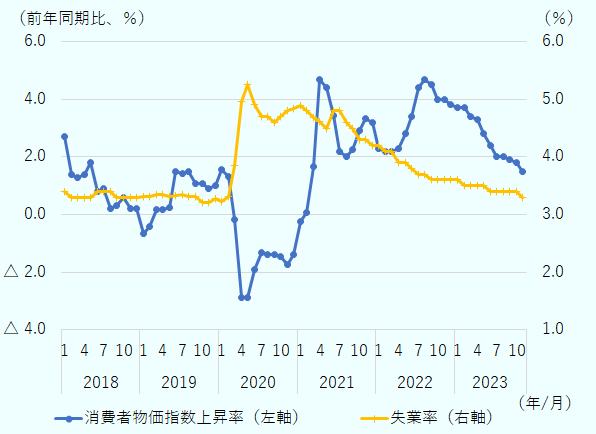
注:消費者物価は2010年基準。
出所:マレーシア統計局
人材不足の深刻度が主要国中トップ
マレーシアでの人材確保を取り巻く状況を振り返ると、新型コロナ対策としての政府による外国人労働者の新規受け入れ凍結を背景に2021年以降、労働力不足が慢性化した。配車サービス(e-hailing)など、ギグエコノミーへ労働力が移動したことも、不足に拍車をかけた。新型コロナが落ち着くと、経済活動回復に伴う需要増も相まって、生産や操業に必要な人員の確保が難しい状態が続いた。
外国人労働者の新規受け入れは2022年2月、約2年ぶりに全面再開。しかし、受け入れ手続きに遅れが出る状況が長く続いた。しかも政府は、製造業ライセンス取得の要件として、2024年末を期限にマレーシア人を全従業員比で8割以上にすることを義務付けた(2022年7月22日付ビジネス短信参照)。その結果、外国人労働者を大幅に増員しづらい状況が続いている。一方非製造業では、新型コロナ禍からの回復に伴い、転職活動が活発化。労働市場の流動性が高まった。
日系企業調査によると、当地日系企業では、人材不足に直面している割合が63.5%に上り、主要6カ国で最も高かった(図3参照)。製造業で特に不足感が強いのが、化学・医薬(73.7%)、非製造業では建設業と情報通信業(いずれも71.4%)だ。これらに限らず、有効回答が10社以上あった全12業種で「不足」の比率がいずれも5割を上回った。特に建設業では、新型コロナ後に建設工事が一斉再開した結果、人手が逼迫している。例えば、半導体関連の大型投資が相次ぐマレーシア北部のペナン州やケダ州で、工事の遅れが目立つ。そのペナン州を含め、人手不足の割合はいずれの地域も5割を超えている。企業数の特に多い地域〔セランゴール州(注2)、マレーシア南部のジョホール州、首都クアラルンプール〕では、いずれも6割を超えた。
図3:マレーシアで人材不足に直面している割合(業種別、地域別)
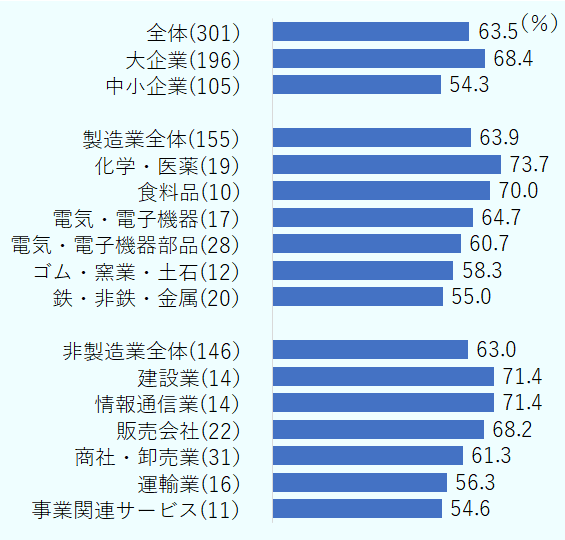
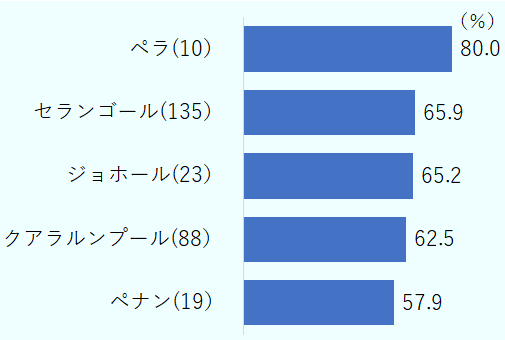
注:有効回答数10社以上の業種と地域。
出所:ジェトロ「2023年度海外進出日系企業実態調査(アジア・オセアニア編)」
製造業では人材不足感が改善
2023年(8~9月)の雇用状況について、前年同期と比べて人材不足が「改善」したと回答した企業の割合は20.7%だった(図4参照)。ただし、「悪化」もほぼ同率の18.8%あり、調査時点では前年来の不足感が続いていると理解できる。
業種別に見ると、製造業で「改善」割合が、非製造業で「悪化」割合が高い。製造業では先述の通り、2022年に外国人労働者の新規受け入れを再開し、年後半には労働者を比較的安定して確保できるようになったため、雇用情勢が改善した可能性が高そうだ。「インドネシア人を雇用したことで(人手不足が)改善」した中小企業(金属製品、マレーシア中部在ペラ州)もあった。
一方で一部製造業では、2022年後半以降、世界的に需要が減退。こうした業界ではむしろ、人余りの状態が発生したことから、人手の調整に苦慮する声もあった。この傾向は、本調査を実施後の半年間で、さらに強まっている。特にセランゴール州では、工場作業員などの余剰人員対策に追われる企業もある。
ただし、こうした製造業の状況「改善」も、地域別に明暗が分かれた。例えば、セランゴール州で雇用状況「改善」回答が58.1%。これに対し、ジョホール州では「悪化」34.8%が「改善」の17.4%を大きく上回った。
図4:マレーシアにおける雇用状況の変化(2022年比)
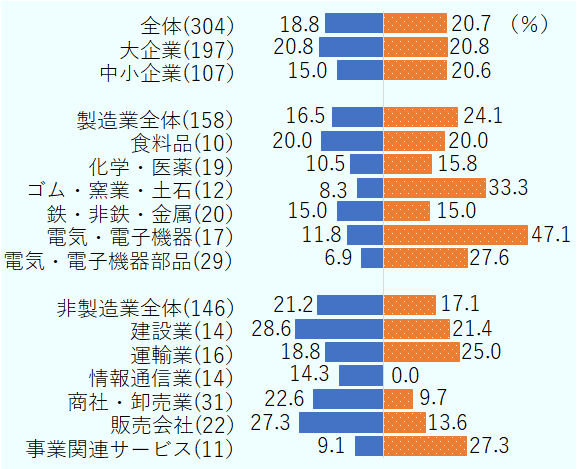
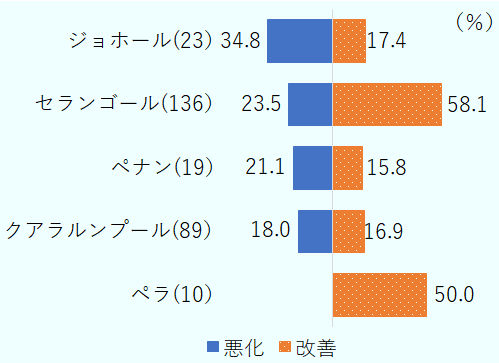
注:有効回答数10社以上の業種と地域。
出所:ジェトロ「2023年度海外進出日系企業実態調査(アジア・オセアニア編)」
職種別には、特に一般管理職と専門職種で人材が不足している(表1参照)。地域別では、一般管理職は全ての州で深刻度合いが5割を超えた。工場作業員は特にジョホール州とネグリセンビラン州、IT人材はクアラルンプールとペナン州、専門職種はジョホール州とペナン州でそれぞれ、特に高い数値を記録した。IT人材については、総数は足りているものの、特に優秀な人材の獲得争いが激化しているとの指摘もあった(情報通信、在セランゴール州)。
| 州・都市名 | 上級管理職(ディレクターなど) | 一般管理職(マネージャーなど) | 一般事務職 | 工場作業員 | プログラマーなどのIT人材 | 専門職種(法務、経理、エンジニアなど) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 総数 | 深刻度合い | 総数 | 深刻度合い | 総数 | 深刻度合い | 総数 | 深刻度合い | 総数 | 深刻度合い | 総数 | 深刻度合い | |
| セランゴール | 74 | 37.8 | 83 | 61.4 | 81 | 34.6 | 67 | 61.2 | 66 | 51.5 | 77 | 74.0 |
| クアラルンプール | 35 | 62.9 | 47 | 78.7 | 46 | 39.1 | 13 | 46.2 | 23 | 60.9 | 37 | 75.7 |
| ジョホール | 9 | 33.3 | 15 | 73.3 | 15 | 33.3 | 12 | 66.7 | 11 | 54.5 | 13 | 84.6 |
| ペナン | 8 | 37.5 | 9 | 66.7 | 9 | 66.7 | 9 | 55.6 | 7 | 71.4 | 9 | 88.9 |
| ペラ | 5 | 20.0 | 8 | 62.5 | 8 | 12.5 | 8 | 50.0 | 5 | 20.0 | 6 | 50.0 |
| ネグリセンビラン | — | — | 5 | 80.0 | 5 | 0.0 | 5 | 80.0 | — | — | 5 | 60.0 |
| マレーシア全土 | 141 | 42.6 | 174 | 67.8 | 171 | 35.7 | 121 | 58.7 | 120 | 53.3 | 155 | 73.5 |
注1:「深刻度合い」とは、人手不足の深刻度を尋ねた設問で「とても深刻」または「やや深刻」と回答した企業の構成比。
注2:有効回答数5社以上の職種。ただし「該当なし」の回答は、計上対象から除外した。
注3:太字は50を超える項目。
出所:ジェトロ「2023年度海外進出日系企業実態調査(アジア・オセアニア編)」
IT人材や専門職種など高度人材は、根本的に問題含みだ。具体的には、国内での育成が十分でなく、既存の職業訓練を経た人材と産業界のニーズとのミスマッチが存在する。このことは、政府も認識しており、2024年度国家予算では、技術・職業教育訓練(TVET)の改革に68億リンギ(約2,100億円、1リンギ=約31円)を割り当てた。その狙いは、既存制度を見直し、産業界との連携を強化するところにある。
賃金以外の待遇改善にも重き
在マレーシア日本企業は、人手不足にどのような対策で臨んでいるのか。それを探るため、採用や定着に向けた具体策や成功事例を尋ねたところ、福利厚生の充実や給与増のほか、従業員の定着に苦心するコメントが多数寄せられた(表2参照)。
福利厚生に関しては、食事に関する待遇向上が目立った。具体的には、手当の増額や回数を限った無料支給などだ。手当の増額が工場作業員の離職率低下に直結した例(化学品、在セランゴール州)も聞かれる。こうした目配りは無視できない。
非製造業種・職種では、新型コロナ以降広まった柔軟な勤務体系を継続することが定着へのカギになりそうだ。「事務職のリモートワーク継続」(電気・電子機器部品、在ペナン州)、「フレックスタイム制を導入したことで特に主婦層から支持が得られた」(窯業・土石、在ジョホール州)といった具体的な指摘もあった。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 福利厚生の充実 |
|
| 給与増 |
|
| 採用上の工夫 |
|
| インセンティブの付与 |
|
| 社内制度の変更・改善 |
|
| コミュニケーション強化 |
|
注:州や連邦直轄地によって休日の設定は異なる。例えば、金曜日と土曜日を週休日とする州が複数ある。そのほか、選挙の結果などで新規の休日が急遽(きゅうきょ)発表されることもある。
出所:ジェトロ「2023年度海外進出日系企業実態調査(アジア・オセアニア編)」
給与そのものの増額も当然、重視される。定期的にベースアップしたり、出勤率に応じてインセンティブを支給したりする例が見られた。そのほか、「賞与支給回数を年1回から2回に増やしたら、定着率が上がった」(電気・電子機器部品、在セランゴール州)という声も聞かれた。
従業員の定着を狙う例も見られる。例えば、採用にあたって在マレーシア日本人大学生やシニア層へのアプローチに注力する、あるいは各種インセンティブを付与して従業員のモチベーションを維持向上する、といった取り組みが多数挙がった。
社内制度の変更や改善により、中長期的に人材の維持・確保に努める例もある。例えば、評価制度の改定や拡充、人材育成の強化などだ。ジョホール州のゴム製造業では、制度変更の一環として「地域の休日カレンダーに合わせ、休日を設定した結果、従業員の不満が減った」という。ジョホール州は、北部のケダ、クランタン、トレンガヌ各州ともに、金曜と土曜を週休日に設定している。
マレーシアに特徴的な取り組みとして、アニュアルディナー(注3)などの各種イベントが、社内の円滑なコミュニケーションに寄与し、ひいては離職の抑制にもつながる場合がある(写真)。人材の定着・採用の具体策に触れたコメントは、約90社から寄せられたが、そのうち食事会などの行事に言及した企業は15社に上った。このような取り組みが、給与とはまた違った側面から従業員の維持に有効であることがうかがえる。社内で緊密に情報共有したり、可能な限り現場に入ったりなど、従業員を尊重する姿勢を示すことも大切だ。

(2023年11月、在セランゴール州中小製造業提供)
- 注1:
-
日系企業調査のうち、マレーシアでの結果を抽出し「ASEAN6カ国の比較とマレーシアの特徴
 (1.75MB)」として分析した結果を参照。なお、当該調査全体については、2023年度海外進出日系企業実態調査(アジア・オセアニア編)から確認できる。
(1.75MB)」として分析した結果を参照。なお、当該調査全体については、2023年度海外進出日系企業実態調査(アジア・オセアニア編)から確認できる。
- 注2:
- セランゴール州は、首都クアラルンプールの近郊。
- 注3:
- 従業員を慰労するため、年に一度、企業が経費を負担し開催するパーティー。コロナ禍下で中止していたアニュアルディナーや社員旅行を、2022年末以降は再開する企業も多かった。

- 執筆者紹介
-
ジェトロ・クアラルンプール事務所
吾郷 伊都子(あごう いつこ) - 2006年、ジェトロ入構。経済分析部、海外調査部、公益社団法人日本経済研究センター出向、海外調査部国際経済課を経て、2021年9月から現職。共著『メイド・イン・チャイナへの欧米流対抗策』(ジェトロ)、共著『FTAガイドブック2014』(ジェトロ)、編著『FTAの基礎と実践-賢く活用するための手引き-』(白水社)など。




 閉じる
閉じる






