特集:変わりゆく中東とビジネスの可能性ウクライナ情勢受けての中東、物価上昇と食糧安全保障が課題に
2022年8月29日
中東地域は、2021年に入って経済は回復基調にあったが、2022年2月からのロシアによるウクライナ軍事侵攻の影響を受け、物価上昇や物流コスト増、食糧確保への懸念が発生している。資源輸入国にとっては、原油価格の高騰というエネルギー問題も課題となっている。
本稿では、経済面を中心に、中東・北アフリカ(MENA)各国におけるウクライナ情勢を受けた現状を概観する。MENAのジェトロ事務所所在国を中心に、湾岸産油国のサウジアラビア、アラブ首長国連邦(UAE)に加え、ロシアとの接近を図るイラン、資源や小麦の輸入国として影響が大きいトルコ、イスラエル、エジプトを主に取り上げる。
中東経済は回復基調も、ウクライナ情勢によるリスク顕在化
中東地域の経済は、新型コロナウイルス感染拡大と油価急落のダブルショックで低迷した2020年から、2021年はワクチン接種の進展によるコロナ禍からの回復や、世界の需要回復による油価上昇などを受け、経済は回復に向かっていた。各国の経済成長率は軒並み前年比で増加し、ジェトロのアンケート調査では、進出日系企業の2021年の業績は前年比20.1ポイント増となる65.2%の企業が黒字となっていた(2022年3月2日付地域・分析レポート参照)。
IMFの経済見通し(2022年4月)では、2022年のMENA地域の実質GDP成長率予測は5.0%で、国別でもサウジアラビア(7.6%)、エジプト(5.9%)、イスラエル(5.0%)、UAE(4.2%)など、多くの国で高い成長見込みとなっていた(2022年5月9日付ビジネス短信参照)。しかし、IMFは4月時点で「ウクライナ情勢の影響で、先行きについては不確実性が高く、下振れリスクがある」とし、食糧価格やエネルギー価格の上昇、資源や小麦の輸入国の対外債務の増大、激しいインフレなどの懸念があると言及していた。IMFが想定したリスクは現実のものとなり、各国でウクライナ情勢を受けた影響が顕在化しつつある。
原油価格が高騰、産油国UAEでもガソリン価格上昇
ウクライナ情勢の影響を見ると、まず資源・エネルギー面では、産油国ロシアによる原油供給に懸念が生じたことから、原油価格が3月より急激に上昇した。米国エネルギー情報局(EIA)の統計によると、3月8日には米WTIが1バレル当たり123.64ドル、北海ブレントが133.18ドルとなる最高値を記録した(図参照)。その後も、欧州などによるロシア産原油の段階的輸入禁止決定などの影響で、油価の高値が続いている。
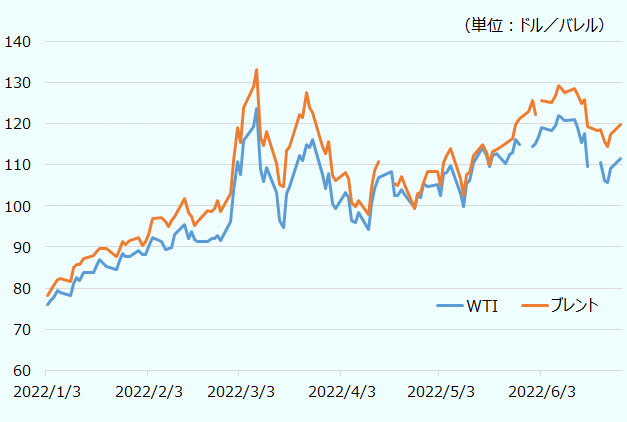
注:数値が未発表の日付もある。
出所:米国エネルギー情報局(EIA)を基に作成
近年では、油価は2020年3月に1バレル当たり20ドル台まで下落し、4月には史上初のマイナス価格を記録するなどの低迷が続いていたが、2022年に入っての油価高騰は、サウジアラビアやUAEなどの中東産油国の国家収入増にも大きく寄与すると考えられる。その半面、トルコなど資源輸入国にとっては貿易収支の悪化が想定される。S&Pグローバルの貿易統計(Global Trade Atlas)で2021年のロシアの国別原油輸出額(国別順位)を確認すると、中東ではトルコが日本に次ぐ12位(21億583万ドル)と上位に位置するなど、ロシアへの高い依存度を示していた(表1参照)。
今後の油価の見通しについても、ウクライナの戦況などに大きな変化がない限りは、当面は高値が続くとする見方が多い。バイデン米大統領は7月の中東訪問に当たって、サウジアラビアから原油増産の確約を得ることができなかった。8月3日のOPEC閣僚会合でも、OPECプラス(注)は9月の増産幅について、8月を下回るわずか日量10万バレルの小幅増産にとどめるとした(2022年8月5日付ビジネス短信参照)。また、湾岸諸国は6月に開催した湾岸協力会議(GCC)閣僚会合にロシアのラブロフ外相を参加させるなど、ウクライナ侵攻後もOPECプラスのメンバーのロシアに一定の配慮を示している(2022年6月7日付ビジネス短信参照)。
| 順位 | 輸出先 | 輸出額(2021年) |
|---|---|---|
| 1 | 中国 | 35,379,891,165 |
| 2 | オランダ | 17,310,142,762 |
| 3 | ドイツ | 9,261,649,319 |
| 4 | ベラルーシ | 6,700,299,887 |
| 5 | 韓国 | 6,413,360,759 |
| 6 | ポーランド | 5,410,713,469 |
| 7 | イタリア | 4,221,981,899 |
| 8 | 米国 | 3,702,949,882 |
| 9 | フィンランド | 3,010,447,647 |
| 10 | スロバキア | 2,497,231,189 |
| 11 | 日本 | 2,236,135,793 |
| 12 | トルコ | 2,105,830,777 |
| 13 | チェコ | 1,657,660,889 |
| 14 | ハンガリー | 1,650,825,809 |
| 15 | リトアニア | 1,457,266,051 |
| 16 | 英国 | 1,426,686,612 |
| 17 | スペイン | 1,268,555,376 |
| 18 | インド | 935,437,907 |
| 19 | ルーマニア | 764,047,355 |
| 20 | ブルガリア | 732,327,925 |
| — | 世界 | 110,968,246,742 |
注:太字はMENAの国。
出所:S&Pグローバル貿易統計(Global Trade Atlas)
他方で、世界的なエネルギー価格上昇は、中東各国の国内の燃料価格にも影響を及ぼしている。湾岸諸国の多くは補助金を投入することで国内のガソリン価格維持を図っているが、2015年から同価格を変動制としているUAEでは、2022年7月時点では年初から約8割の値上げになるなど、自国民のように補助支援を受けられない外国人を中心に、ガソリン価格上昇の負担が増している(2022年8月2日付ビジネス短信参照)。
天然ガスについては、欧州がロシアに代わるエネルギー輸入相手国を探す必要に迫られたことから、カタールがドイツなどとの液化天然ガス(LNG)供給に関する協力強化を進めている。また、東地中海ガス田(EastMed)の活用可能性も模索されており、6月にはイスラエルとエジプトがEUと天然ガス供給に関する覚書に署名した。両国の海上ガス田の輸出供給能力はそれほど大きくはないとみられるが、今後両国からの欧州への輸出が本格的に開始される見込みとなっている(2022年6月16日付ビジネス短信参照)。
激しい物価上昇、物流コストも高止まり
燃料価格の上昇とも相まって、中東地域でも世界各国と同様に、激しい物価上昇に悩まされている。ただし、トルコやイランなど、ウクライナ情勢の影響のみではなく、それ以前からの通貨安がインフレに大きな影響を与えている国もある。2021年に通貨リラ安が急速に進んだトルコでは、2022年6月時点の消費者物価指数(CPI)上昇率が前年同月比で78.62%と、過去20年間で最も高い水準にまで上昇した(2022年7月12日付ビジネス短信参照)。特に運輸、食品・飲料、住宅・光熱費など、国民の生活に関わる分野の物価が大きく上昇している。同様に、米国の制裁によってビジネスが困難な状況にあるイランでも、通貨リアル安が進んでいたことから、イラン暦1401年第3月(5月21日~6月20日)は前年同月比52.5%のCPI上昇率となった。特に生活に影響の大きい食品・飲料が82.6%増、レストランが86.4%増と高くなっている。
一方、これまでは原油収入を補助金などに充てて物価上昇を抑えこんできた湾岸産油国でも、徐々にインフレの傾向が見え始めている。UAEの2022年6月のCPI上昇率は5.84%となり、まだ低い水準ながらも、1月の1.74%からは上昇傾向となっている(2022年8月2日付ビジネス短信参照)。同じくサウジアラビアでも、6月のCPI上昇率は前年同月比2.3%といまだ低いが、教育や食品の一部では10%以上の上昇率を示すなど、少しずつ国民の生活に影響が及んでいる(2022年7月25日付ビジネス短信参照)。
さらに、企業にとって影響が大きい物流コストも、新型コロナ感染拡大などによる高騰を経て、2022年内は高止まり傾向が続くとみられる。日系物流企業の近鉄エクスプレスドバイ法人は、ロシアとウクライナの上空が飛行できないことで航空ルートが変更となり、より多くの燃料を積む必要があることから、航空貨物を搭載可能な総量が減少し、輸送費が上昇するなどの影響が出たとしている(2022年6月3日付地域・分析レポート参照)。
小麦輸入停止などを受け、食糧安全保障が大きな課題に
ロシアやウクライナからの小麦輸入の停止を受けて、中東各国でもパンなど小麦由来の食品を主食としていることから、食糧安全保障も大きな課題となっている。前述のS&Pグローバルの貿易統計(Global Trade Atlas)で、2021年のロシアとウクライナの国別小麦輸出額(国別順位)を確認すると、ロシアの輸出先は1位トルコ、2位エジプト、6位スーダン、7位サウジアラビア、10位イエメン、12位イスラエルと、多くのMENAの国々が上位を占めている(表2参照)。同じくウクライナの輸出先も、1位エジプト、3位トルコ、5位モロッコ、7位イエメン、8位サウジアラビア、9位チュニジア、11位レバノンとなっている(表3参照)。こうした統計からも、両国からの小麦輸出停止はMENA各国の食糧事情に深刻な影響を与えたことがうかがえる。
| 順位 | 輸出先 | 輸出額(2021年) |
|---|---|---|
| 1 | トルコ | 1,803,290,737 |
| 2 | エジプト | 1,552,598,413 |
| 3 | アゼルバイジャン | 292,350,709 |
| 4 | ナイジェリア | 253,531,748 |
| 5 | カザフスタン | 214,860,002 |
| 6 | スーダン | 202,781,486 |
| 7 | サウジアラビア | 195,442,452 |
| 8 | バングラデシュ | 190,278,029 |
| 9 | ラトビア | 175,954,178 |
| 10 | イエメン | 152,662,765 |
| 11 | カメルーン | 137,248,103 |
| 12 | イスラエル | 118,162,495 |
| 13 | リビア | 108,447,864 |
| 14 | アルジェリア | 105,631,494 |
| 15 | タンザニア | 101,074,720 |
| 16 | ケニア | 98,824,991 |
| 17 | セネガル | 96,573,103 |
| 18 | コンゴ民主共和国 | 96,188,798 |
| 19 | パキスタン | 95,696,653 |
| 20 | エチオピア | 76,342,265 |
| — | 世界 | 7,301,689,411 |
注:太字はMENAの国。
出所:S&Pグローバル貿易統計(Global Trade Atlas)
| 順位 | 輸出先 | 輸出額(2021年) |
|---|---|---|
| 1 | エジプト | 858,048,477 |
| 2 | インドネシア | 726,860,366 |
| 3 | トルコ | 446,387,457 |
| 4 | パキスタン | 353,763,881 |
| 5 | モロッコ | 231,866,303 |
| 6 | バングラデシュ | 217,047,674 |
| 7 | イエメン | 206,261,500 |
| 8 | サウジアラビア | 186,199,314 |
| 9 | チュニジア | 162,904,454 |
| 10 | エチオピア | 161,452,767 |
| 11 | レバノン | 160,149,248 |
| 12 | リビア | 146,425,731 |
| 13 | 韓国 | 96,309,793 |
| 14 | フィリピン | 92,971,530 |
| 15 | ケニア | 89,282,356 |
| 16 | イスラエル | 88,536,349 |
| 17 | ナイジェリア | 87,752,161 |
| 18 | タイ | 77,817,970 |
| 19 | イラン | 73,120,397 |
| 20 | ベトナム | 67,129,256 |
| — | 世界 | 5,068,375,639 |
注:太字はMENAの国。
出所:S&Pグローバル貿易統計(Global Trade Atlas)
現地紙「アラブ・ニュース」(2022年4月12日付)では、政治・ビジネスリスクコンサルタントの発言を引用して、「ロシアとウクライナは、中東への小麦の最大の供給国。エジプトが特にこの2カ国からの輸入に依存しているが、チュニジア、リビア、レバノン、トルコ、イエメンもまた、両国からの供給停止と価格上昇に脆弱(ぜいじゃく)だ」と報じている。
特に両国に小麦供給の大部分を依存してきたエジプトでは、食品価格の上昇が民衆の暴動などの政情リスクにつながりやすい傾向があるため、緊急の対応を迫られた。政府は小麦の輸入相手国の多角化を図るとともに(2022年2月22日付ビジネス短信参照)、3月には食品輸出の禁止などの食料確保を試みた(2022年3月18日付ビジネス短信参照)。また、7月にはロシアのラブロフ外相の訪問を受け入れ、アフリカへの穀物輸出継続に関する約束を取り付けるなど、同国との関係維持にも努めている(2022年8月5日付ビジネス短信参照)。
これらの課題に対しては、トルコや国連が仲介役を務めている。ロシアとウクライナはトルコとともに、7月22日に黒海経由でのウクライナからの穀物輸出再開に関する合意文書に署名した(2022年7月26日付ビジネス短信参照)。この合意では、国連の支援の下、黒海を通過する商業船の安全を監視するための「共同調整センター」を設置するとしたが、戦争が継続していることもあり、今後安定した輸出につなげられるかは注視する必要がある。
これまで見てきたように、MENA各国の経済は回復基調に入っていたが、インフレや食糧問題などの分野で、ウクライナ情勢を受けた不安要因が足元に出始めている。今後も国によってばらつきがあるものの、その影響について見ていく必要があるだろう。

- 執筆者紹介
-
ジェトロ海外調査部中東アフリカ課課長代理
米倉 大輔(よねくら だいすけ) - 2000年、ジェトロ入構。貿易開発部、経済分析部、ジェトロ盛岡、ジェトロ・リヤド事務所(サウジアラビア)等の勤務を経て、2014年7月より現職。現在は中東諸国のビジネス動向の調査・情報発信を担当。




 閉じる
閉じる






